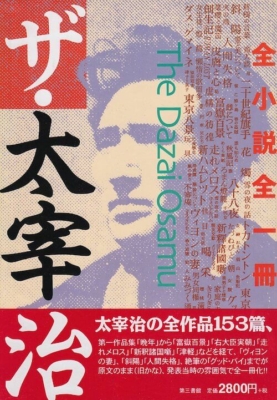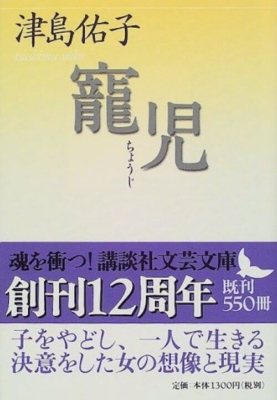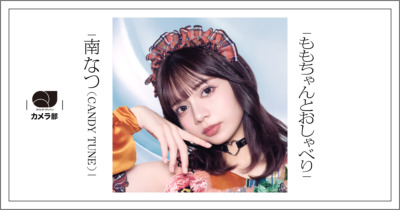家族の中に必然的に表れる死と生
津島作品には、作家が自身の心中を見つめた一連の作品がある。第17回女流文学賞を受賞した『寵児』(講談社文芸文庫)は津島の第2長篇であり、子を為して産むことで、男に拠らずして家族をつづけていこうとする女性が語り手である。母系家族を描いた初期の代表作だ。また、1988年に発表した『真昼へ』(新潮文庫)では我が子を突然失った哀しみと向き合い、家族の中に必然的に表れる死と生という契機について思いを巡らせている。
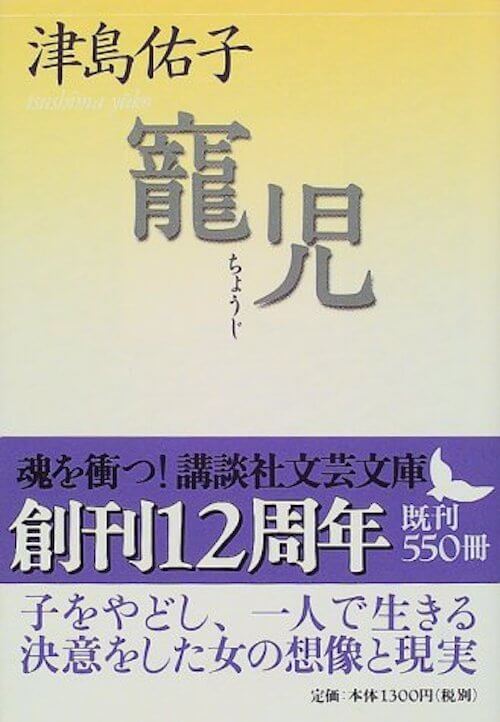
その2年前、子供の死から半年という時期に書き始められた『夜の光に追われて』(講談社文芸文庫)では千年以上の王朝文学「夜の寝覚」作者に自らを重ね、自身と小説との距離を取るという手法が採用される。この手法は後に、自らを『ジャングル・ブック』、あるいは『家なき子』の登場人物になぞらえるふたりの子供が、さまざまな時代で生と死を体験する『笑いオオカミ』(2000年/新潮社/第28回大佛次郎賞)、母子が歴史の中で転生しながら時間を超越していく『ナラ・レポート』(2004年/文藝春秋/第16回芸術選奨文部科学大臣賞ほか)などに結実していく。晩年の津島は、アイヌなどの民族文学との交流を積極的に行っていた。画一的な価値観によって可能性が塗り潰されることを拒み、それぞれの声で物語が発せられることを希望したのだ。石原燃がデビュー小説の舞台を、日系移民による独自の民俗・文化が築かれたブラジル・サンパウロにしたことには、この影響を感じる。

石原燃版の「レクイエム」
『津島佑子 土地の記憶、いのちの海』(河出書房新社)に作者が津島香以名義で発表した「社会との向きあい方」という文章に、娘から見た津島佑子像が描かれている。「子を失った母親」という紋切り型に押し込まれるのを拒否するため、あえて喪に服さない態度をしてみせたというエピソードなどはやはり「赤い砂を蹴る」の、恭子の葬儀場面などに重なる。「母は『死』という、人の力ではどうしようもない喪失をなんとか受け止めてようとしたのだと思う」と石原(津島)は書く。社会の準備した既存のイメージを拒否することは、たとえばアウシュビッツや原爆についての知識を養うことにもつながったのだと。

──私たちが生きる社会は喪失と再生の繰り返しであり、そこに豊かさがある。それは命のはかなさの実感から生まれる発想であり、現代の不幸は、喪失することの意味を見失っていることではないか。
母・津島佑子をこうして理解した延長線上に今回の「赤い砂を蹴る」がある。そうした意味では、これは石原燃版の「レクイエム」なのである。見事な鎮魂曲だと思う。
候補作をまだ読み終わっていないので今回はここまで。「赤い砂を蹴る」いい小説だと思うが、選考はどうなるか。今回の芥川・直木賞については、7月15日の本家選考会までに杉江が語学番組『テレビでドイツ語』出演などでおなじみの、マライ・メントラインさんと候補作について語り合う対談をお届けする予定である。日本の文学界を代表する両賞をマライさんはどう読むか。お楽しみに。