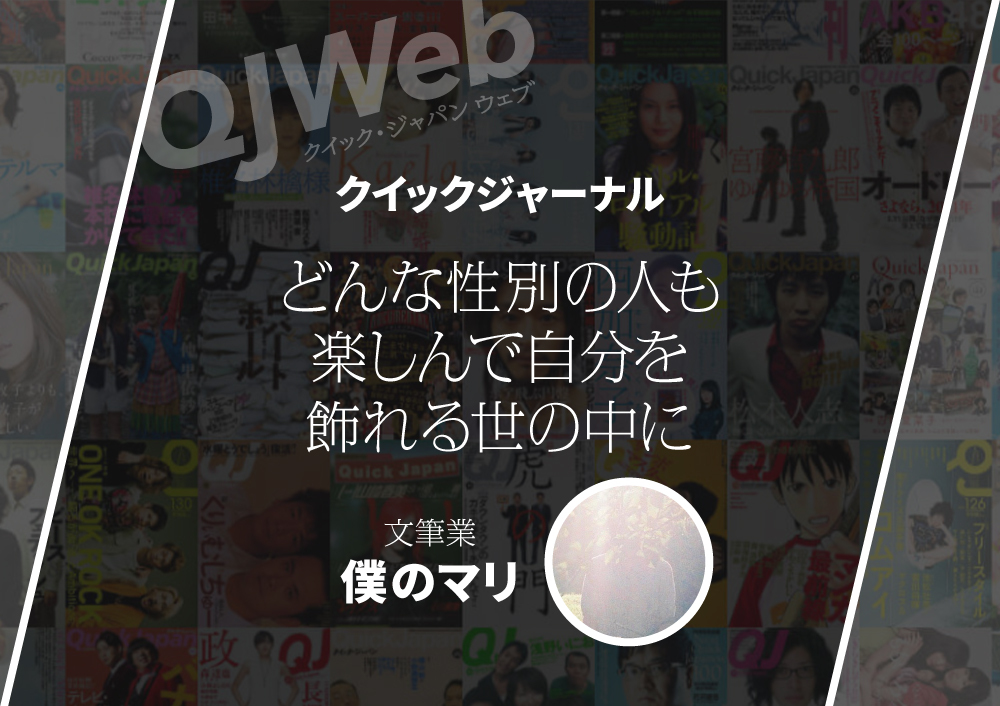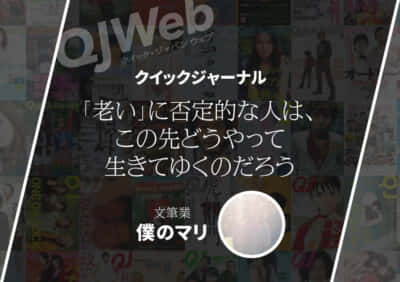『北京2022 オリンピック』に出場した高梨沙羅選手への「メイク批判」がインターネット上で波紋を呼んだ。性別問わずメイクを楽しむ今の時代、改めてメイクについて文筆家・僕のマリ氏が考える。
春、いつもと違うメイクに心踊った日
春が芽吹いている。柔らかい光や、突然の強い風に当たりながら、太陽の暖かさを享受している。
花屋に並ぶ春の花や、桜味のお菓子を目にするたびに、今年も大好きな季節が来たと思う。冬の重いセーターやコートを脱ぎ、薄手のカーディガンに袖を通す。
爪に明るい色を乗せれば、気分も華やいだ。薄づきの口紅やパステルカラーのアイシャドウをまとうと、なんとなく気持ちも丸くなって、いつもの景色も違って見える。
先日買ったマニキュアはミモザのような色で、気に入ってよくつけている。昔はピンクや赤ばかりだったけれど、最近は青や緑も選んで塗っている。ブラウンやグレーのネイルも素敵だし、ゴールドも外せないし、爪がいくつあっても足りないくらいだ。
「女の子ってこんな魔法みたいな楽しみがあったんだね」
以前、男の子の友達が深い青のマニキュアを塗っていて、「めっちゃかわいい」と褒めたら「恋人がくれたんだよね」とはにかんでいた。「爪がかわいいと気分上がる。会社にはさすがにつけていけないけど、女の子ってこんな魔法みたいな楽しみがあったんだね」と言っていた。
マニキュアも素敵だったが、その「魔法」という言葉が頭に残って、折に触れて考えている。
家にある20本あまりのマニキュアは、全部微妙に違う色、質感で、仕事やお出かけ、普段使いと分けている。いつも寝る前に明日の予定や服を考えて選び、塗らない日はほとんどないかもしれない。
もう10年以上そういう習慣で生活を送っているので、あんまり深く考えたことはなかったけれど、この儀式は確かに「魔法」なのかもな、と思う。「今日の自分は爪までかわいい」と思うだけで、なんだか機嫌よく、穏やかに過ごせる気がする。

髪をセットして、身体にクリームを塗り込み、化粧をして、アクセサリーをつけて、爪を塗り、香水を振る。時間がないときは大変だけれど、すべてがうまくいってカチッとハマったとき、鏡を見るのが楽しかったりする。
それが誰かのためのこともあれば、自分が自分を好きでいられるように繰り返す営みのような側面もある。肌にいいものをつけて、いい香りをまとい、好みの色を選ぶ、その装いやおしゃれが心のケアにもなり得る。
化粧やマニキュアが女性の世界だけに完結せず、どんな性別の人も楽しんで自分を飾れる世の中になったことが、素直にうれしい。
スキージャンプ・高梨沙羅選手への「メイク批判」
先月開催された『北京2022 オリンピック』でスキージャンプ女子ノーマルヒルの日本代表だった高梨沙羅選手が、素晴らしいジャンプを見せたものの、メダルを獲ることはできなかった。
しかし4位という大健闘を見せた彼女に賛辞を送りたいのだが、「メイクにうつつを抜かしていないで練習しろ」という心ない批判が飛び交った。
あまりにも的外れな暴言で取りつく島もないのだが、あえて指摘するならば、
(1)オリンピックに出るほどのアスリートが練習していないわけがない
(2)マナーとしてメイクをする人も多く、高梨選手は25歳の大人の女性である
(3)オリンピックという大舞台において、メイクをすることで自分を鼓舞できる可能性もある
相当なプレッシャーに押し潰されそうになるなか、メイクすることで「お守り」のような効果が発揮されたのではないだろうか。
子供のころから第一線で活躍してきた彼女が、年ごろになりメイクをしただけで批判に晒されるのはお門違いだ。アスリートである前にひとりの人間である。

先日、高梨選手がオリンピック後最初の実戦となったW杯個人第17戦で優勝した。今季3勝目、W杯通算63勝目だ。
今後もどうか高梨選手がオリンピックでの批判を跳ね返し、競技もメイクも楽しめるように願っている。
「女装コンテスト」に出演した、ひとりの男の子の話
メイクのことで思い出すことがある。
高校3年生のとき、文化祭の実行委員になった。文化祭を楽しみたいといろいろ企画を考えて、「女装コンテスト」を開催した。1年生から3年生まで自薦・他薦問わず参加者を募り、思い思いの服装・メイクで全校生徒の前に出て、投票でグランプリを決めるのだ。
男子が多い学校だったので人数はすぐに集まって、10人ほどがエントリーした。ほとんどの参加者がおもしろ半分で参加していたので、セクシーなドレスを選んだり、ミニスカートを履いたりして笑いを誘おうとしていた。メイクも真っ赤な口紅だったり、ばさばさのつけまつ毛をつけたりと、過剰な女らしさを見せていたように思う。
だがしかし、ひとりだけまったく違う雰囲気の男の子がいた。露出もなく、派手さもなく、「普通の女の子」の服装で、自分で施したメイクはほんのりと色づき、彼は静かに体育館の花道を歩いた。それまで笑いや悲鳴に包まれていた場内が一転、しんと静まり返ったのを覚えている。
きっとそれは、彼の女の子の姿を笑っていいかわからなかったのだと思う。なんだかそれくらい、切実なものを感じた。時代が時代だったので、今ほどジェンダーに対する知識や理解がなく、ただ呆然と観ることしかできなかった。
結局グランプリは違う男の子が受賞して、翌年も「女装コンテスト」があったかどうかわからない。しかし心に残るものがあった。

あれから年月が経ってふと、あの子は今どうしているのだろう、と思う。彼(もしくは、彼女)にとって、自分らしくいられる世界になっただろうか。もう二度と会うことはないのに、時折ふと思い出してしまう。
【関連】加齢は「劣化」ではない。痴漢、不審者など、若い女性が“なめられる現実”からの救い
【関連】“マンガでもあり得ない”を可能に変える羽生結弦の“主人公感”。「正直、すごくオリンピックが怖い」乗り越えた先にある最高の物語
関連記事
-
-
マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】
『DAIENKAI 2025』:PR -
ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】
『DAIENKAI 2025』:PR