「コンプラだからやめとこう」の先の話
過去大会でもそうだったように、2021年大会でもネタの人権意識の面を批難する声が相次いだ。
ももに関してはスタイル自体が外見に関するステレオタイプ(固定観念、偏見)に基づくもので、マイクロアグレッションにつながり得る。ルッキズムだと指摘する声もあるが、ルッキズムの核は美醜の基準を恣意的に規定することであり、問題の核から少しずれるように思われる。もものネタは「ブサイクいじり」ではなく、「◯◯っぽい見た目」という属性のレッテル貼りだからだ。

ゆにばーすに関していえば、なんら新規性のない実によくあるジェンダー・バイナリ(性別二元制)とヘテロノーマティヴィティ(異性愛規範)に基づくネタだった。こちらに関しては「下ネタだ」という指摘が多くあり、確かにセクシャルな部分もあったものの、問題の本質は上記のようなポイントにあるだろう。さらにいえば、そういうふうに男と女の登場する話題をなんでもかんでもエロで括ること自体ヘテロノーマティヴィティ的な発想といえる。
例によって上記の個々の単語の意味を解説することはしない。読者それぞれが記事に誘発されて自分で調べる状況を作り出すのが、筆者が文章を書く仕事を通して実現したいことだからだ。
これらのネタが非難を受けたことは、放送できるものと判断したテレビ局側の問題でもあるし、指導が不十分な事務所側の問題でもあり、ひいては初等教育で基礎的な人権教育がなされないこの国の教育の問題でもある。
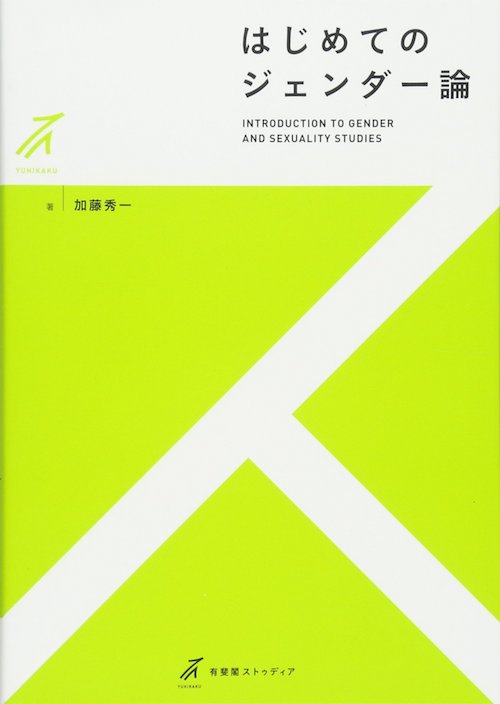
誰もが知識の素地を持っている状況ではなく、気づいた人間が自助努力でどうにかアップデートしていくしかないこの原始時代において、どこまで個人の至らなさを問えるのか、という土台がアンフェアな設問ではある。だからこそお笑いファンが先陣を切って、違和感を口にしつづけることに意義がある。そうでもしないと、お笑いに限らずそれぞれの愛するカルチャーがどんどんダサくなっていく。「嫌なら観るな」は反論としてズレている。
現状の芸人たちの認識としては、人権意識として適切か否かという尺度よりも、「コンプラ」だから、「ポリコレ」だから、「怒られるからやめとこう」といったスタンスが支配的だろう。こういったスタンスの土台にある勘違いが、コンプライアンスやポリティカル・コレクトネスをさもつい最近できたもののように認識していること。ずっとあったのだ。「一般常識」とか「社会性」とか呼ばれるものとして。
「カタワ」や「バイタ」や「ルンペン」といった言葉を使うのをやめようという気運が高まった時期にも、現代の一部の芸人や一部のファンのような反応を示す人がいたのだろう。「そんなこと気にしてたら映画が撮れなくなる」とか「音楽は自由だ」とか、今と似たような見当外れの反論があったのだろう。
現代、「カタワ」や「バイタ」や「ルンペン」を封じられてお笑いなんかできるかよ、と主張する芸人は見た覚えがない。そもそもそんな言葉をわざわざ使ったとて何もおもしろくない。今起こっていることもそういうことだ。
最低限のリテラシーがあれば回避できる問題だし、本来そうであってこそプロだろう。今も昔も、時流に即して適切なユーモアを生み出すことは芸人の“腕”の主たる要素だ。そして今後ますます重要度が増していくのだろう。
ももに関して言えば、「ヤンキー」とも「オタク」とも「ヤカラ」とも「陰キャ」ともひと言も口にしていないあたり、彼らなりの線引きの意識と取ることもできる。
映画やNetflixのドラマなどでも、もものネタのようにステレオタイプを戯画化したキャラクターがおもしろおかしく描かれることがある。ただ、製作者側がそれをわかった上で風刺としてやっていることが明示されたり、物語上の扱いによって固定観念を覆す表象がなされたりして、最終的には偏見へのカウンターとして機能することがある。その仕組みをお笑いに導入できれば、今の持ち味を活かしたままむしろポジティブなネタに昇華することもできるだろう。
関連記事
-
-
マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】
『DAIENKAI 2025』:PR -
ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】
『DAIENKAI 2025』:PR












































