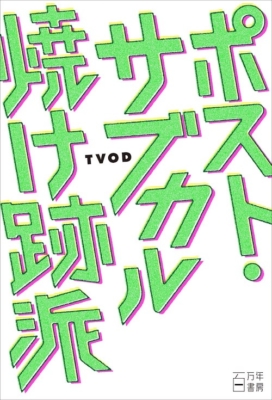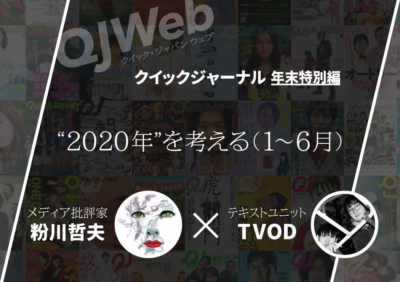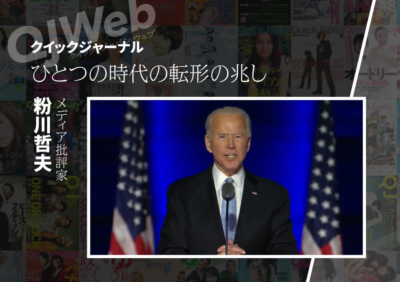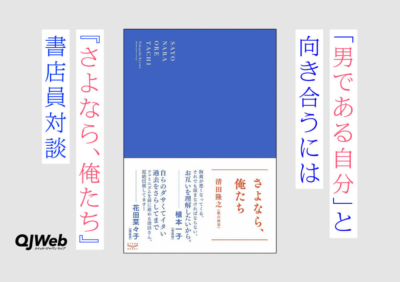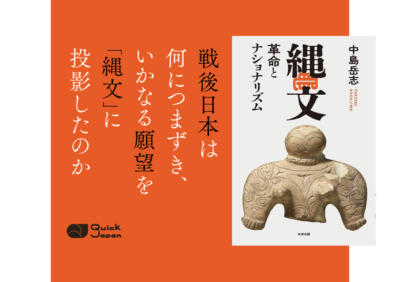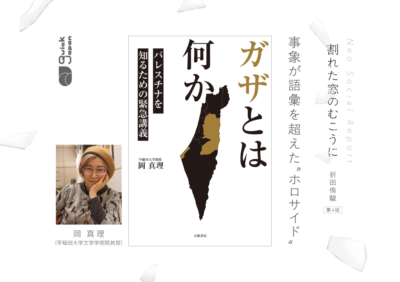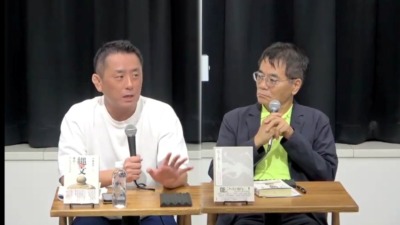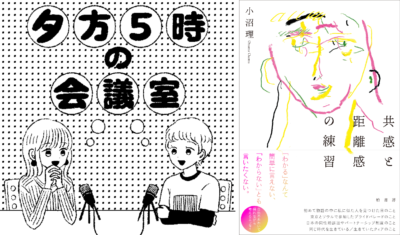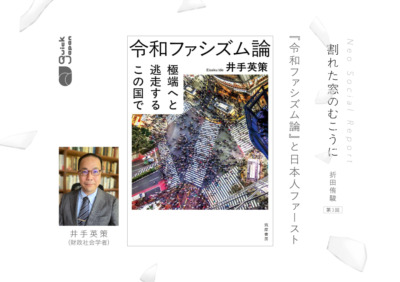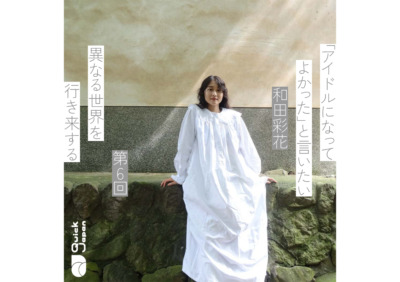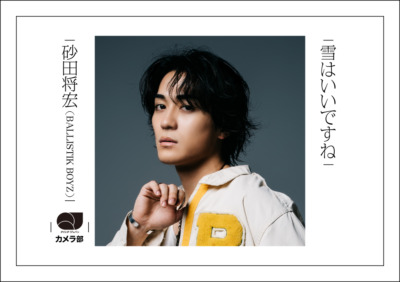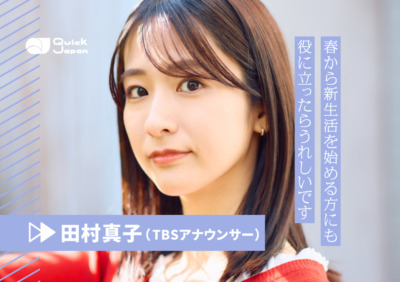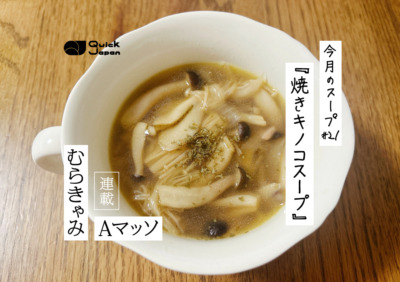コロナ禍におけるアート
パンス ここ十数年の日本の「ネット右派」に特色があるとすれば、未だに冷戦体制みたいな構造で世界を見ているという点にあると思っています。それがアメリカvs中国になり、いまやトランプの熱狂的支持者となりつつあります。彼らに限らず、テキストベースのネットでのコミュニケーションを見る限りでは、敵対性の設定というのはむしろ加速しているように映るのですが、ちょっと回り道をして、COVID-19下の文化を振り返ってみます。
生活が閉ざされた状況を逆手に取るような表現がいくつか見受けられました。「Zoom」を使ったようなものです。Zoom風の画面上でマイクリレーをするラップ・ミュージック(5月20日)、小津安二郎の画面がZoom的ということで作成された動画(4月28日)など。
パンス 生活においても、オンライン上で「飲み」を行うのがちょっとしたブームになり、僕も何度かやりました。
プシクさんの、コロナのインパクトを「世界革命」とするビジョンがとても興味深いです。それは「上からの革命」といった感じでしょうか? ウイルスを「上」と考えるかどうかも難しいところですが……。さしずめ、4~5月ころは、先の表現など、革命状況に対する人々の反応がうねりのように見受けられる時期でした。
プシク 今の「冷戦」は、イデオロギーのではなくて経済テクニックで、トランプが大いに活用しました。そういえば、旧右翼もネトウヨも儲からないことはしませんね。コロナの「革命」は、組織のではなく、「分子革命」です。気づかないところで(身体細胞の中でも)起こる激動です。当然この「革命」への便乗や応用もあるわけで、ITやギグエコノミーはいまウハウハです。
その点で、今追い詰められているのはアーティストじゃないでしょうか? ちょっと前までは「創造的」と思われていることがありふれたツールでできてしまうからです。映画のスプリット・スクリーンの歴史を意識すると、とてもZoomなんか使えません。しかし、アートは、「危機」のさなかで再生するはずです。ただし、「逆手に取る」という技法は、デュシャン先生で終わっているのでは?
コメカ 危機状況のなかでの日本のアーティストの動き方には、個人的には危うさを感じるものも多かったです。4月には星野源が「うちで踊ろう」という楽曲の弾き語り動画をインスタグラムにアップし、それに対して自由に演奏を重ねたり、動画を使って二次創作を行うことを呼びかけましたが、当時首相であった安倍晋三が「コラボ動画」を星野の許諾なく発表しました。「危機」のさなかでの有名アーティストによる情報技術の使い方が、権力に簡単に上塗りされるようなある意味で稚拙なものでしかなかった。
「逆手に取る」ことすらできておらず、用意された情報環境に対してあまりにも素直にそこに臨んでしまっているアーティストが多いように思います。5月にはリアリティーショー『テラスハウス』出演時にSNSで多くの誹謗中傷を浴びた木村花さんが自死される痛ましい出来事がありましたが、ツイッターなども含め、WEB世界が人々を「動員」する装置として機能している現状をどう捉えればいいのかということも、この一年改めて考えつづけました。