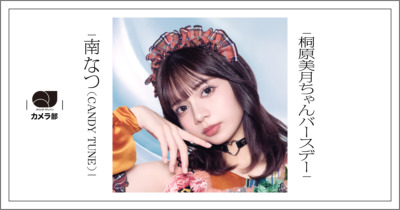自分と他者との境界を曖昧にする『となりの庭』
9月はもうひとつ、自分と他者との境界をテーマにした展示に触れていた。画家・今村文さんの『となりの庭』だ。

花や植物を主なモチーフとし、半透明の紙に切り絵を貼りつけた水彩画や、色をつけた蜜蝋を溶かし、漆喰に焼きつける「エンコスティック」と呼ばれる蜜蝋画を制作している今村さん。
本展のステイトメントの中で、今村さんは「庭」を「他者との境界」としている。自己を認識し、他者と関係するための境界。しかし、庭という境界があることで多くの苦しみが生まれているのではないかと彼女は言う。そうした境界の隔たりを、花や虫を行き交わせることによって曖昧にしていこうというのが本展の、「庭」の主眼なのではないかと感じた。
今村さんの絵の朧気(おぼろげ)な風合いは消え入りそうに儚く、どこか懐かしい気持ちにもなる。私は絵に明るくないが、その質感に見惚れてしまい、うっかり触れそうになることしばしばだった。もちろん、実際には触れてはいないけれど、この「触れたくなる」衝動を起こさせることこそ、作家自身が望んでいたことではなかったか。
――作品を作ること、展示をすること、それぞれは庭を作る事に似ている。
ステイトメントの冒頭で、彼女はそう書いている。
庭をつくること。すなわち境界を創造しながらも、他者と触れ合う余地を残すことは共存する。
自他の境目がなくなることで、傷つけたり、傷つけられたりすることが多々あった。一方で、自他の境目がくっきりし過ぎていることもまた孤独や傷つきにつながっていく。
媚びるわけではない。
しかし、読んでくれた人との間に何かを――『となりの庭』で言うところの花粉や虫を――行き交わせられる作品を、私もつくっていきたいと思った。
*
植物に対する動物の特徴は、自分が自分であるという輪郭をはっきりと持っていることだと思う。中でも人間はとりわけ「食って食われて」の食物連鎖において、一方的に「食って」おり、他者に侵食されることを長らく避けてきた。
そうした生物としての人間のあり方は、他者との関わり方にも関連があるのではないか。あるいは、ほかの生き物(一例として植物や虫)のあり方から、他者との関わり方を学べるのではないか。
そんなことを考えさせてくれた9月の展示だった。
佐々木ののかの「クイックジャーナル」は毎月中旬ころ、月1回の更新予定です。