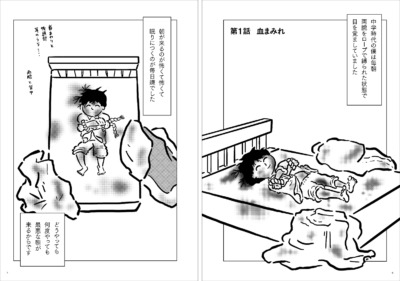菅義偉首相が「自助・共助・公助」を理想の社会像とし、多くの論争を呼んだことは記憶に新しい。
「家族と性愛」を看板に掲げる文筆家・佐々木ののかが、フランス出身東京在住の写真家ジェレミー・ベンケムンの『無常』(bookshop/galleryタタ/2020年8月14日~9月6日)と、画家・今村文の『となりの庭』(nidi gallery/2020年8月21日~9月3日)というふたつの展示から、「自助」が求められる社会で見落とされがちな、他者と「溶け合い、触れ合う」悦びについて考える。
クィアアーティストが問う、自と他の境界とアイデンティティ「無常」

ジェレミー・ベンケムン『無常』は、メインビジュアルをツイッターのタイムラインで見かけてから、観るのを楽しみにしていた写真展。真っ赤な背景にふたりの(おそらく)女性がキスをするように近接し、その境界が水面のように揺れて溶け合っている。他者との関係性を表現していることは、展示会場でステイトメントを読む前から伝わっていた。

ジェレミー・ベンケムンさんは、フランス・カンヌ出身の写真家で、現在は東京を拠点に活動している。国内外のファッションや広告の仕事を手がける傍ら、プライベートワークでは性やヌードをテーマにした作品をつくり、クィアアーティストとしてセクシュアリティを模索している。
展示は、10点近い写真とひとつの映像作品からなり、多くはメインビジュアル同様に作品表面が揺らいでいる。映像作品では、昭和歌謡やフランスのシャンソンに合わせて3つの写真の表層が変化していくのだが、人物だと思っていた写真が少しずつ風景に転じ、また人物に戻っていく映像を観て、私はとある本で読んだ文章を思い出した。
『植物の生の哲学 混合の形而上学』(エマヌエーレ・コッチャ/勁草書房)には、「種から落ちた場所から動くことなく一生を過ごす植物は、光合成により酸素を作り出し、あらゆる生物が住まう環境を整える。つまり植物は世界と溶け合い、世界を作り出し、世界に存在している」と書かれていて、その文章に感銘を受けた。同時に植物のようには生きられない人間の自分に引け目を感じていた。
でも、自分以外の人間や動物、植物といった他者と接することで<私>は確実に変容している。自分の輪郭を濃くすることが求められがちな現代の人間社会において、物理的に自然の風景になるのは難しくても、植物的な生き方を意識することはできるのではないか。
全ては神羅万象から成る
液体の様な世界で生きる私たちは
なぜ自分自身を定義しようとするのか
会場で販売されていたZINE冒頭のステイトメントで、作者はそう問いかける。
かく言う私もその塩梅が難しく、他人に際限なく肉薄したかと思えば、自分を守ろうとして殻に閉じこもることを繰り返している最中だ。でも、他者と溶け合っていろいろなものを交換しながら混交物である自分を受け入れられたら、どんなに素晴らしいだろう。
そんな憧れと願いを託すようにZINEとプリントを買い、私は会場をあとにした。
関連記事
-
-
マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】
『DAIENKAI 2025』:PR -
ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】
『DAIENKAI 2025』:PR