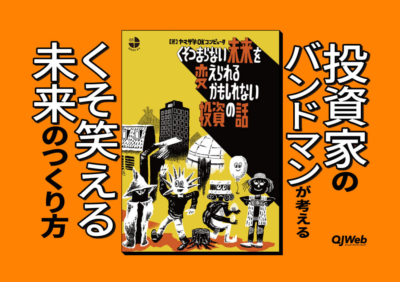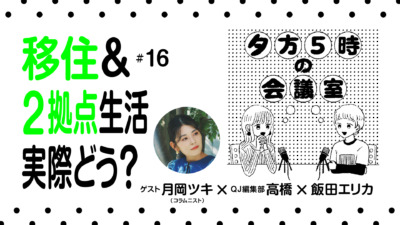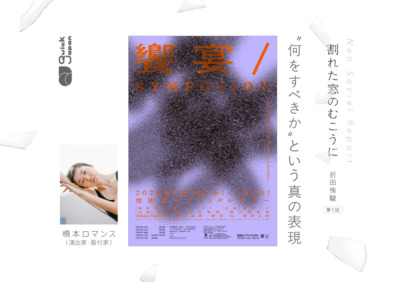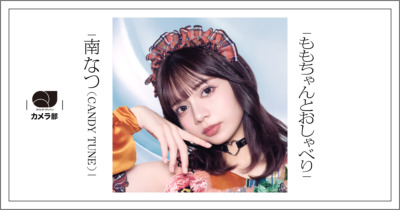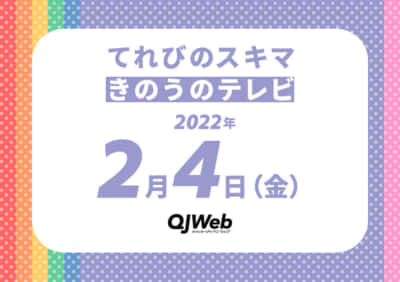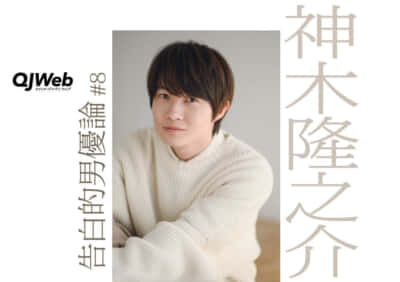美しい真紅の花に宿る、グロテスクな「母子の愛」
性器やセックスをつくったのが「新水晶宮」なら、映画『リトル・ジョー』は、誰にでも愛される“子供”をつくった作品といってもいい。
バイオ企業の研究室に勤める主人公のアリスはシングルマザーで、息子・ジョーとふたりで暮らしていた。仕事熱心で家庭を顧みる余裕もなく、日夜研究に勤しみ、人を幸せにする真紅の花「リトル・ジョー」の開発に成功する。しかし、花の研究に携わる人間たちに少しずつ不穏な変化が訪れる、というのが大枠の筋書きだ。
人間たちに変化をもたらす原因とされているのが、花粉。受粉しても実らない不稔性(ふねんせい)の花として開発されたリトル・ジョーは、生き延びるために花粉をまき散らし、吸い込んだ人間を“感染”させ、愛させる。
展開だけを辿れば、「遺伝子を組み替えて自然に介入した人間への裁き」といった人間中心主義へのカウンターとも取れるかもしれない。しかし、私はそれ以上に本作品から「家族」への強い執念を感じた。
リトル・ジョーは、アリスが息子にちなんでつけた名前で、彼女にとっては“もうひとりの息子”と呼んでも差し支えない。一方で、“本当の”息子であるジョーは、家庭を顧みずに研究に没頭するアリスを応援しながらも、ひとりで過ごす時間の長さに寂しさを感じていた。
そんな折、アリスが会社に内緒で持ち帰った一輪のリトル・ジョーによって、ジョーにも変化がもたらされる。劇的な変貌を遂げるわけでもなく、外形的には「親離れ」や「反抗期」とされる程度のものだが、アリスの焦燥感との対比によりいっそう距離を感じずにはいられない。ディストピアを描いた物語であるため、リトル・ジョーの存在によって親子の絆が分かたれていく過程は「悲劇」に位置づけられているとも読める。しかし、私は逆に、本作から親子の絆へのアンチテーゼのようなメッセージを受け取った。
アリスの“もうひとりの息子”であるリトル・ジョーが、“母”の愛を求めて人々を感染させていく様は、美しいビジュアルをもって不気味に描かれる。この“母子の愛”をなんの疑いもなしに受け入れていく過程のグロテスクさこそが、本作の本旨ではないだろうか。
場面ごとに同系色のトーンでそろえられた映像は、一貫して美しかった。しかし、均一なものが美しいという感性は、雑多なものが共存するという本来の意味での「多様性」をも一色に染め上げてしまう恐れがある。
「多様性を尊重しよう」と叫びながら、自分にとって不快なものは排除してシンプルで美しくしたい。映画『リトル・ジョー』の美しい同系色の世界は、そうした欲望や感性への警鐘にもなっている、とする見方は、いささか意地悪過ぎるだろうか。
人間中心主義、強固過ぎる母子の愛、そして「多様性」とは名ばかりの排除の礼賛。あらゆる角度から現代社会を乱反射した、皮肉なまでに美しい作品だ。
*
8月に鑑賞した、家族や性を「つくる」ふたつの作品。
「新水晶宮」は既存のイデオロギーから解き放たれるような、『リトル・ジョー』は既存の価値観に対するアンチテーゼを唱えるような印象だったから、並べて語るのは無理がある。
けれど、「当たり前」との距離の取り方を教えてくれるという意味で、私はどちらの作品を観たあとも息がしやすくなったのだった。
よい作品とは、それが好きにつけ嫌いにつけ「ここではないどこか」へ、高速で飛ばしてくれる乗り物だ。私にとって展覧会に行くことは、遠くの世界で深呼吸して戻ってくる旅のようなものなのである。
-
映画『リトル・ジョー』
2020年7月17日(金)より全国ロードショー
原題:『Little Joe』
監督・脚本:ジェシカ・ハウスナー
脚本:ジェラルディン・バヤール
出演:エミリー・ビーチャム、ベン・ウィショー、ケリー・フォックス
配給:ツイン関連リンク
関連記事
-
-
4年目の今、重荷だった「王子様」を堂々と名乗れる。Last Princeが語る、プリンスを背負う勇気と楽しさ
Last Prince:PR