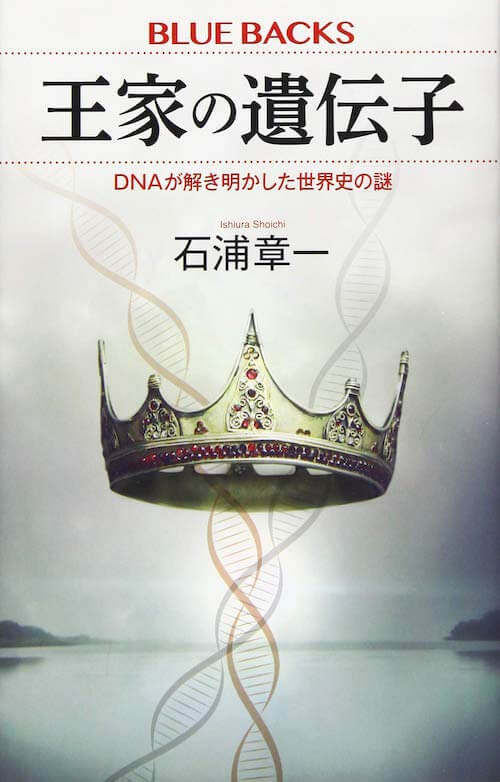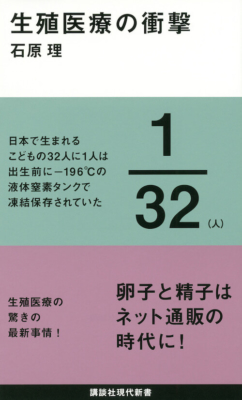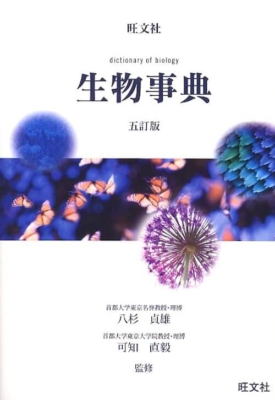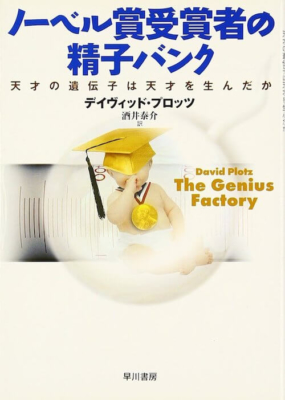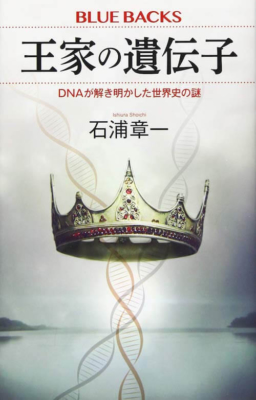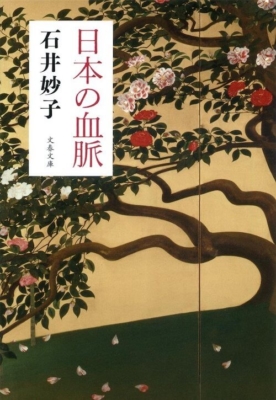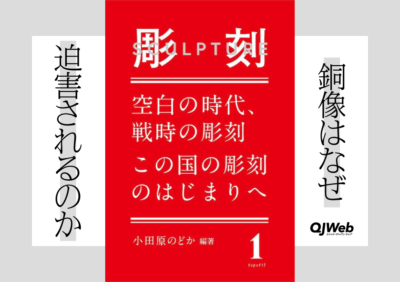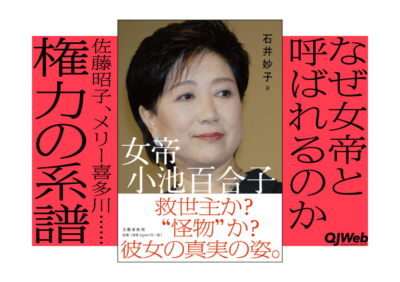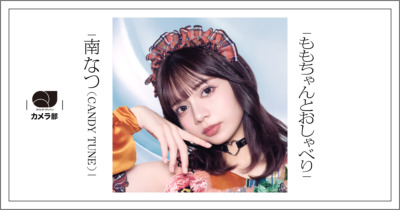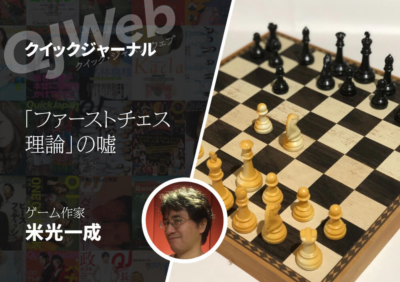スポーツ界と人種
芸能界以上に、スポーツ界はより身体能力に左右される世界とあって血筋や遺伝が強調されがちである。そこでは個人というレベルを超え、人種による遺伝形質の違いから身体能力の優劣が説明されたりする。特に黒人の身体能力は生まれつき優れているというイメージは根強い。だが、アメリカ研究者の川島浩平による『人種とスポーツ 黒人は本当に「速く」「強い」のか』(中公新書)を読むと、こうしたイメージが歴史的、文化的に作られたものだとわかる。たとえば、アメリカの黒人の場合、長い間就ける職業が極めて限定され、その限定された中で最も有望な世界が、芸能界であり、スポーツ界だったという歴史的背景を抜きには、多くの優れたアスリートが輩出された理由は説明できない。
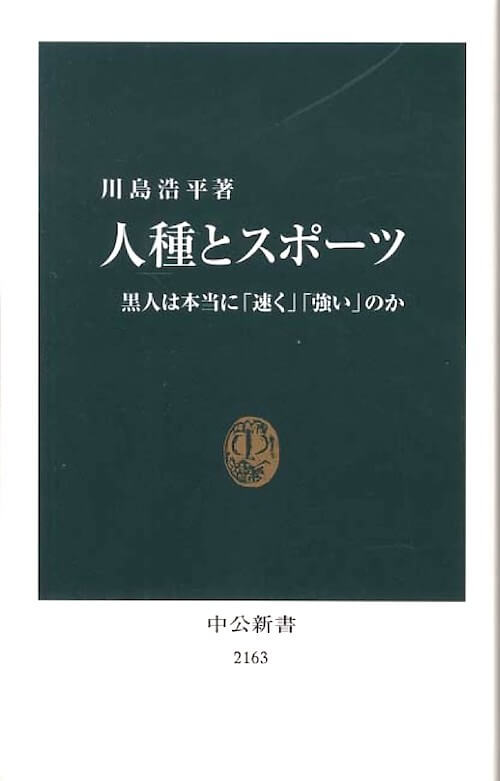
またひと口に「黒人」と言っても、そこには西アフリカ、東アフリカ、中央アフリカ、南アフリカを出自とする多種多様なエスニック集団がすべて含まれる。そうした出自に加え、国籍や文化の違いによって優秀なアスリートが輩出される競技も異なってくる。たとえば、カリブ海に位置するジャマイカとドミニカ共和国は、いずれも西アフリカを出自とする黒人が多いが、ジャマイカがウサイン・ボルトをはじめ一流スプリンターを擁する陸上短距離王国であるのに対し、ドミニカはベースボール大国として知られる。
そもそも人種とは遺伝的要素のみにもとづくものではない。分子生物学者の石浦章一は『王家の遺伝子 DNAが解き明かした世界史の謎』(講談社ブルーバックス)で、史料や語り継がれてきたものだけではわからなかった歴史的事実が、関係する人物の遺伝子を解析することで明らかになった事例を多数紹介している。それでも遺伝子から何もかもわかるわけではないとして、人種という概念についても次のように説明する。
人種とは、単に肌の色だけでなく、社会・経済・文化的要素を大きくともなう概念であり、遺伝子解析によって判別できるような生物学的基盤をもつものではない。「遺伝子が何もかも決定する」という、魅力的だが短絡的な考えに陥るのはきわめて危険だ。
『王家の遺伝子 DNAが解き明かした世界史の謎』石浦章一/講談社
しかし、黒人の身体能力に対するステレオタイプなイメージはなかなか消えそうにないし、「分かりやすい親子物語」に人々は飛びつきやすい。遺伝や血筋といった概念は、それほどまでに私たちを呪縛している。それは遺伝子やDNAといった科学用語がなまじ一般に定着しているせいでもあるのだろう。これらの言葉は、ときには「企業の遺伝子」「文学のDNA」などといった具合に、精神や文化の継承を表現する場合にも隠喩的に使われる。この手の用法はすでに1960年代末から70年代にかけて雑誌の記事タイトルにちらほら見られるものの、頻繁にメディアに登場するようになったのは1990年代後半以降だろう(あまりに安易に使われ過ぎて、いまや半ば陳腐化しているともいえるが)。この背景として当時、人間(ヒト)の持つ全遺伝子情報であるヒトゲノムを解析する国際協力プロジェクトが進められていたことも見逃せない。