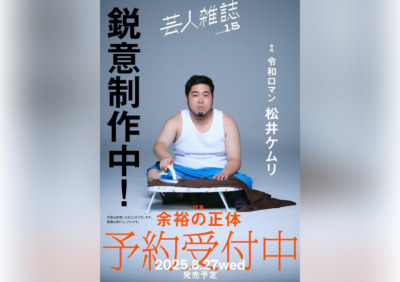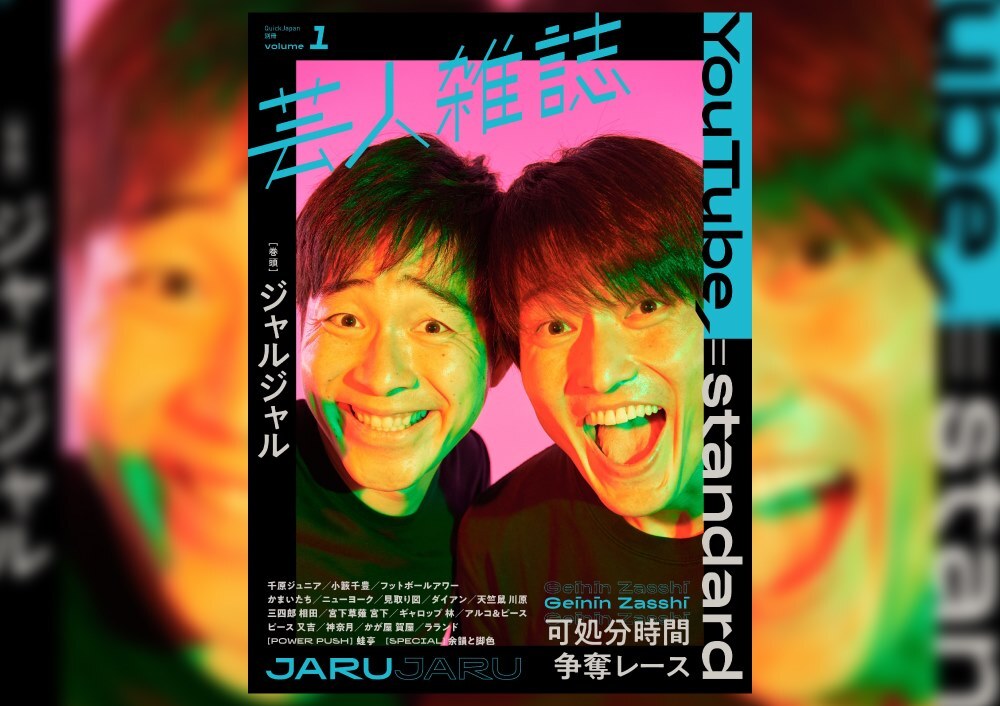美味しい「ヘーゼルナッツの味噌」の作り手、発酵マエストロ、カルロ・ネスラーにさらに聞く。そもそも、なぜ発酵食品に興味を持ったのか? イタリアで味噌やしょうゆに夢中になったカルロ少年に何があったのか。フードジャーナリスト・宮本さやかが、マエストロの「なぜなぜ人生」に迫る。
【関連】日本より美味しい味噌をイタリアで発見!花のような香りの「ヘーゼルナッツ味噌」の作り手を直撃
地産地消の本当の意味
「日本の味噌や醤油の作り方をいろいろ研究して、まあまあ納得できるモノができるようになった。麹菌だけは日本のものを取り寄せて、大豆は地元で作ってもらったものを使って。だけど、あるとき、気がついたんだ。味噌を作るのに必要な大豆は、もともとイタリアで食べているものではない。それはなぜかと言えばイタリアのこの地域で栽培するのには適していないからだってことに。大豆栽培には水がたくさん必要だけど、このへんは雨が少なくてとても乾燥している。そんな土地で無理に大豆を育てたら環境に大きな負荷をかけるし、食べ慣れていない僕らイタリア人の胃腸には、消化しにくいという問題もある」。

地産地消とよくいうけれど、それは地元で作物を作り、km0(農家から食卓まで0km)でさえあればいいということじゃない。その土地の土壌や気候に適したものを作り、その土地で生まれ育った人の身体に合うものを食べる、それが大事なんだ。発酵というプロセスを経て、人間の身体が消化・吸収しやすいように菌が食物を分解してくれるとはいえ、イタリア人の身体が消化しにくい大豆を使うというのも違うのではないか。
そう考えたカルロさんは、地元ヴィテルボ近隣の農家が作っていた豆類──レンズ豆やひよこ豆、そしてヘーゼルナッツで味噌、しょうゆソースを作ってみることにした。結果は上々。香り高く、美味しいだけでなく、環境にも食べる人間の身体にも優しい、そんな味噌やしょうゆたちができ上がった。さらに、地元の農家にも仕事が増えた。いい豆類をコツコツ作っている農家に注目が集まったから、じゃあ俺もいい豆作ろう! じゃあ俺も俺も、と地元の農業が活性化したのだ。
こんなふうにカルロさんは、発酵食品を武器にして、環境問題やSDGsにも取り組んでいる。今年の春からは、日本、イタリア、ドイツの企業をつなげ、地球規模の環境、生態系の回復に取り組む団体「JINOWA」でも、中心的な存在として活動している。
関連記事
-
-
マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】
『DAIENKAI 2025』:PR -
ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】
『DAIENKAI 2025』:PR