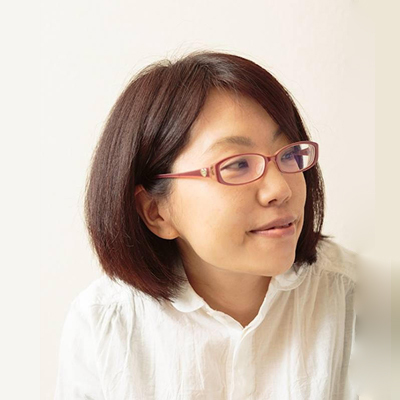脚本家・渡辺あやインタビュー(6) 「私にとって脚本は、ある程度の余白みたいなもの」

「東京にいたら書いていない」という「脚本を書く」行為について、渡辺あやさんが住む場所との関連を語る。自主映画『逆光』に企画と脚本で参加している渡辺さんに、地元・島根で行ったインタビュー最終回。
(1) 地元・島根を訪ね、『ここぼく』『逆光』の背景を聞く
(2)参加意識は「巨人軍のコーチみたいなもの」
(3)自分たちでお金を出し「企画会議を通る要素がひとつもない」映画を作る
(4)「成績優秀な人たちが、小学生が見てもおかしい事態を引き起こすのはなぜなのか?」
(5)煙草と人間のエネルギーについて「ちょっとくらい体に悪いこともやっていないと」
(6)「私にとって脚本は、ある程度の余白みたいなもの」
渡辺あや
映画『ジョゼと虎と魚たち』(2003年)で脚本家デビューし注目され『メゾン・ド・ヒミコ』(2005年)、『天然コケッコー』(2007年)など優れた脚本を次々書く。『火の魚』(2009年)、『その街のこども』(2010年)でテレビドラマの脚本を書き、2011年、朝ドラこと連続テレビ小説『カーネーション』でそれまで朝ドラを観ていない層にも朝ドラを注目させた。近年は『ワンダーウォール』(2019年)、『今ここにある危機とぼくの好感度について』(2020年)などが高い評価を得ている。寡作ながら優れた作品を生み出すことに定評がある。
映画『逆光』
コロナ禍、脚本:渡辺あや、監督、主演:須藤蓮が互いの持続化給付金を持ち寄って作った自主制作映画。舞台は70年代の尾道、三島由紀夫にかぶれている青年・晃(須藤蓮)が故郷・尾道に好きな先輩・吉岡(中崎敏)を連れて帰郷してくる。先輩に向けられた湿度を伴った晃の眼差しが物語を牽引する。尾道と島根で10日間のロケを行った。
心の中で冷えた凝り固まったものを解きほぐしたい
──以前、渡辺さんが好きなことをやれているのは、ご自分に作家のみならず、妻や母としての寄る辺があるからとおっしゃっていました。今回、生活圏に伺ってみて、東京とは違う空間と時間の流れがあると感じます。
渡辺 あると思いますねえ。私は外からの影響を受けやすいので、東京にいたら東京のサイズになると思うんですね。しゅっとすぐに。1週間くらいで(笑)。
──西宮育ちで、結婚後、ドイツで過ごし、帰国後島根。そこで出産したのち、その暮らしに飽き足らず脚本を書き始めたそうですが、今はどうですか。
渡辺 ところが、脚本の仕事を始めて思ったのは、東京にいたら書いていないであろうということでした。私にとって脚本は、ある程度の余白みたいなもので、「ああ、ひま! 脚本でも書くかー」みたいなことがないと絶対書けないと思うんですよ。
東京に行って打ち合わせしたらいろいろ楽しいから買い物して、いろんな人に会ったりして遊んで帰ってくるんです。バブル世代だから派手なことも嫌いじゃないんですよ(笑)。そうやって満喫して島根に戻ると、それが抜けるっていうか。たとえるなら、砂が水の中に混ざっている感じなんですけど、それがしゅーっと収まってきてからやっと書く作業を始められたりするんですね。
収まるまでに3日とかかかるんですが、そういう自分の状態を観察していると、やっぱり東京にいたらずっと脳みそや心が回っているだろうと想像するんです。東京だといろんな人に会うだろうし、普通に街を歩いているだけで情報量が回り過ぎて、たぶん、そこにいたら書けないと思います。

──確かにこちらは緑が濃くて落ち着きますよね。
渡辺 仕事の打ち合わせなどで誰かが来たとき、私はいつも緑を背景にして座るんです。そうするとみんな、私じゃなくて緑を見ながら話すようになって。仕事の話からプライベートの話になって、時には泣き出しちゃったりして。私というか、緑にはそういう効能があるのかもしれないです……。
──ははは。確かに渡辺さんの作品は、カウンセリングみたいな気がしますね。その人の混沌とした思いを腑分けしてくれるから、言いたいことが明確になってしまうのかなっていう。
渡辺 だったらうれしいですけどねえ。確かにそういうことをやろうとしているのかなあと思います。人の心の中で冷えた凝り固まったものを解きほぐしたいというような感覚があります。
──『ワンダーウォール』のとき、寡作とよく言われるが、書きたい企画がなかなか通らないとおっしゃっていました。昨今は、連ドラにラジオドラマ、自主映画……と企画が通るようになってきたのでしょうか。
渡辺 一時期、書いても書いても、お蔵入り?みたいなことがつづいて、それと安倍政権の絶好調期とが偶然なのかわからないけれど重なっているんです(笑)。それが最近、ちょっと空気がゆるんできたような感じがしていて……。それこそ『ここぼく』は安倍政権のときにはできなかったんじゃないかとか。紆余曲折を経ながら進めてきた企画も、会社の上の人が過剰な反応をしていましたが、ようやくできそうな空気になってきました。
──世の中的に、今の社会に物申したい気分になってきたのでしょうか。
渡辺 私としては、みんなが言えるようになったのならそれでよくて。あのころ、誰も言わないから、なんとか言うにはどうしたらいいのかと思って書いていたんです。
──渡辺さん、学生時代、生徒会長でもやっていましたか?
渡辺 いや、全然やってないです。でも『ワンダーウォール』のとき、80歳を過ぎた叔母が電話をしてきて「血を感じるわ」と言ったんです。叔母と母は60年安保のころに学生運動を経験しているんですよ。祖父も社会運動でマルクスにかぶれていたらしくて……(笑)。

渡辺あやさんの仕事場に伺いたいと提案したとき、仕事のたび、気分転換できる楽しみを奪ってしまうかなと恐縮もしたのだが、一回くらいは許していただけたのではと思う。幽閉された姫って感じではないので。
仕事場は6年くらい前に古民家をリノベーションしたそうで、あたりはジブリアニメの世界かと思うような、絵になる木があったり、家の中にはアンティークな家具があったり、情報量が多いと書けないと言うだけある空間がたっぷりとあった。文字を書く前のまっさらな半紙がいつも用意されているような場所だからこそ、間(あわい)のある作品が生まれるのかもしれない。無数の書物に埋め尽くされた知の宇宙から生み出される作品もいいし、こういうのもいいなと思う。
渡辺さんは自身の表情から発される情報によるバイアスを少しでもなくそうというかのように、逆光の中で少し影になった顔で語る。そこで思い出したのは須藤蓮さんが取材のときに言っていたことだった。
「これは僕の勝手なイメージなんですけど、渡辺さんって誰かと共有できるものから発信がスタートする脚本家さんなんですよ。『あなたと私の間にあるものしか物語になりませんよね』みたいな人で。そう。逆に言えば、通じ合うところがあれば誰とでも仕事ができるし、仕事する人によって書くものが違う。それでいて“渡辺あや”カラーがあるのがすごいと思うくらいです」
まさにここは渡辺あやと出会った人の数だけ物語の生まれる場所であった。
-

『逆光』
企画:渡辺あや、須藤蓮
脚本:渡辺あや
監督:須藤蓮
音楽:大友良英
出演:須藤蓮、中崎敏、富山えり子、木越明、SO-RI、三村和敬、衣緒菜、河本清順、松寺千恵美、吉田寮有志2021年7月17日(土)よりシネマ尾道、7月22日(木)から横川シネマにて公開。以後、順次公開予定。
関連リンク
関連記事
-
-
Furui Rihoが『Letters』で綴った“最後の希望”「どんなにつらい日々であっても、愛は忘れたくない」
Furui Riho『Letters』:PR -
4年目の今、重荷だった「王子様」を堂々と名乗れる。Last Princeが語る、プリンスを背負う勇気と楽しさ
Last Prince:PR