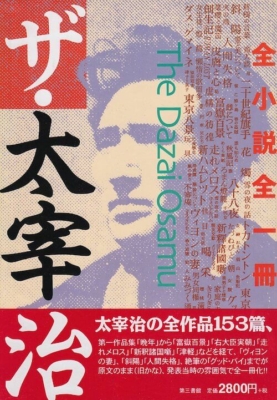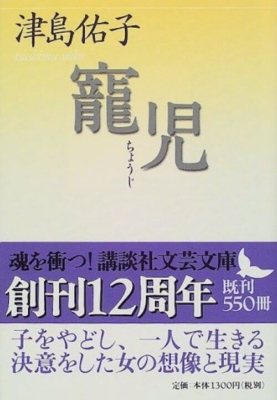「太宰治の孫」が芥川賞候補に! 6月16日に発表された「第163回芥川賞候補作」作家のひとり、石原燃がその日のツイッターのトレンドになっていた。太宰治の芥川賞への執念は孫の代で成就する? 書評家・杉江松恋が候補作「赤い砂を蹴る」を読む。
母系家族の小説である
第163回芥川・直木賞候補作が発表になった。芥川賞は5作のうち4作が初候補の作家で、「赤い砂を蹴る」(『文學界』6月号)の著者・石原燃が「太宰治の孫」であるということが一部で話題になっている。「津島佑子の子」であるほうがよほど大事なのだが、理由は後述する。石原燃は1972年生まれ、津島香以名義で演劇ユニット「燈座」を主宰する劇作家である。公式プロフィールに戯曲の作歴が書かれているが、小説は初めての著作のはずである。

「赤い砂を蹴る」はブラジル・サンパウロ州を訪れた〈私〉こと千夏が語り手を務める小説だ。〈私〉の母は2年前に末期癌と診断され、ほどなく亡くなってしまった。その母には、サンパウロの香月農場で生まれた芽衣子さんという親友がいて、彼女と共にブラジルを訪ねたいと願っていたのだ。日本への帰化申請のためいったん帰国する用事が芽衣子さんにでき、誘われて〈私〉も同行することになった。
母系家族の小説である。母の恭子は離婚しており、その後も交際した男性はいたものの、正式な〈私〉の父親にはならずじまいである。日本人と結婚した芽衣子さんも、その姑に冷遇されたり、夫がアルコール依存症になって体を壊すなど、男に苦しめられた人生を送ってきた。臨終間近に母娘が目と目で語り合ったときの、「私には父親がいなかったから、この国の男たちのことを知らなすぎた」という恭子の言葉がすべてを言い表しているように思う。
作中では、母子が暮らした部屋の記憶が幾度も語られる。それは母子にとっては安堵の空間だったのだ。また、作中では何人もの死が語られる。恭子や芽衣子の義理の母は女性だが、男性の死者のほうが多い。死んでいった成員の影を背負いながらもつづいていくのが家族ということなのだろう。女系のつながりに目が行きがちになるのは、〈私〉たちの住む社会が男の論理を優先しているからこそなのだということに読んでいてたびたび気づかされる場面があった。
太宰治より津島佑子が重要
「太宰治の孫らしさ」を期待される読者には、それはほとんどありません、と先にお答えしておくべきだろう。そもそも「太宰と芥川賞」という関係が強調されるのは、第1回の同賞で「逆行」が最終候補作になりながらも落選しているからだ(ほかに予選候補作として「道化の華」)。このときの川端康成の選評に激怒した太宰は「川端康成へ」という恨み節としか思えない文章を発表している。並行して佐藤春夫に「私に芥川賞をお与えください」と売り込んだが、当時は内規がごちゃごちゃしていたためか二度と候補になることはなかった。このへんの詳しいところは川口則弘『芥川賞物語』(文春文庫)をどうぞ。
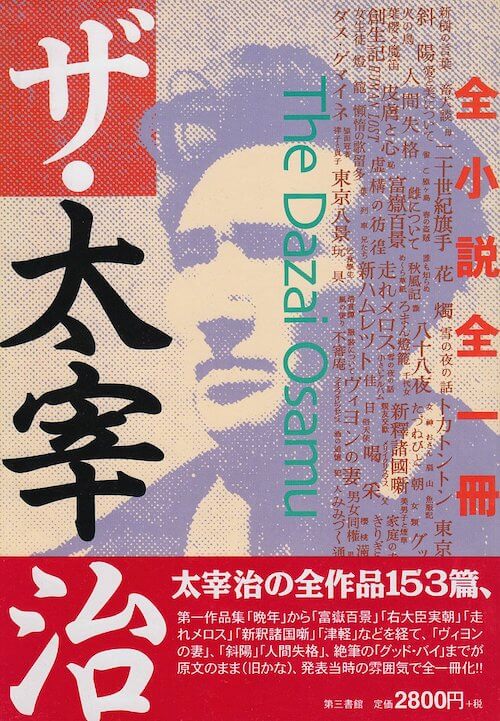
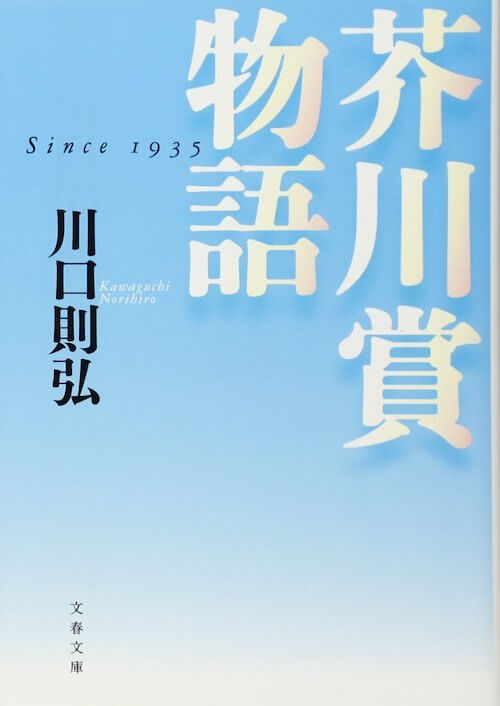
「赤い砂を蹴る」という作品との関連ではるかに重要なのは作者の母・津島佑子だ。ちなみに石原は、太宰の二度目の妻となった美知子の旧姓である。津島は1947年生まれ、1歳のときに父は亡くなっており、文学史上の人として太宰治を知ることになる。初めて津島佑子の筆名で発表した作品は短篇「レクイエム」(『謝肉祭』河出書房新社所収)だが、これは自身が12歳のときに病死した兄・正樹を登場させ、兄と妹が死んだ犬の「シロ」を葬るという内容だった。初期においてはこの兄の死が、のちには1985年に急死した長男が津島にとって重要な登場人物となる。「赤い砂を蹴る」の母親・恭子の職業は画家だが、風呂場で心臓発作のために死んだ息子をモチーフにした連作を発表したとあることからも津島佑子だと受け止めるべきだろう。
関連記事
-
-
Furui Rihoが『Letters』で綴った“最後の希望”「どんなにつらい日々であっても、愛は忘れたくない」
Furui Riho『Letters』:PR -
4年目の今、重荷だった「王子様」を堂々と名乗れる。Last Princeが語る、プリンスを背負う勇気と楽しさ
Last Prince:PR