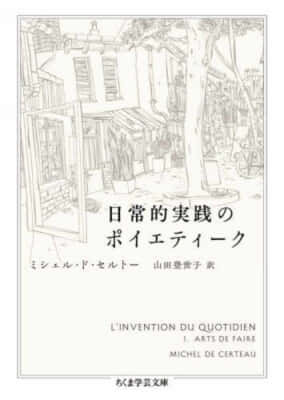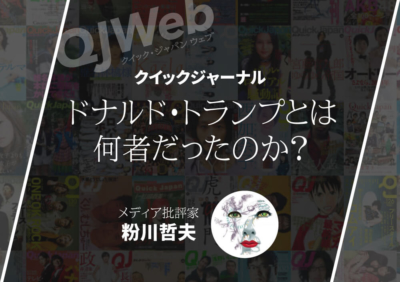ファンダム文化(ポップカルチャーのファン集団が能動的に作り出す文化)を論じた研究書、『コンヴァージェンス・カルチャー』(ヘンリー・ジェンキンズ 著/渡部宏樹、北村紗衣、阿部康人 訳/晶文社)が今年2月に邦訳された。
原著の刊行はSNSもまだ定着していない2006年だが、現在のファンダム文化はもちろん、「ポップカルチャーの政治利用」というテーマを考える上でも、重要な示唆に富む名著だ。
表立った政治的な目的を持たないポップカルチャーは、それゆえにどんなイデオロギーのもとにも利用され得る。実際にそうした政治利用は、SNS普及以前から行われてきた。
さらにSNSが普及した現在では、制作者もファンも意図しないかたちでコンテンツが政治性を帯びてしまうという事態が頻発している。その典型例として、本稿では昨年のタイの反政府デモにおける『とっとこハム太郎』のテーマソング利用を取り上げる。ポップカルチャーの持つ本質的な魅力とその危うさについて、『コンヴァージェンス・カルチャー』を手がかりに考えていきたい。
目次
カルチャーと政治の予見できない邂逅
本書のキー概念である「コンヴァージェンス」は、「収斂」を意味する英単語にジェンキンズが独自の用法を与えたものだ。まずはWEBでも公開されている訳者あとがきから、定義を確認してみたい。
本書での「コンヴァージェンス」は「1. 多数のメディア・プラットフォームにわたってコンテンツが流通すること、2. 多数のメディア業界が協力すること、3. オーディエンスが自分の求めるエンタメ体験を求めてほとんどどこにでも渡り歩くこと」といった三つの意味を持っている〔中略〕このコンヴァージェンスをキーワードとして、ポップカルチャーのファンたちが自発的にコミュニティを形成しその中で集合的に知識を生み出す参加型文化のダイナミズムを描き出している。
「訳者あとがき」たちよみ『コンヴァージェンス・カルチャー』より
「コンヴァージェンス」の概念は実に幅広いニュアンスを持ち、何を指し示しているのかをすぐに理解するのは難しい。特定の対象というよりも、2000年代に生じたなんらかの環境の「変化」や、それが引き起こしている「事態」を表す概念として、この語は用いられている。小説、アニメ、映画、バラエティ、動画、WEBサイトなど、さまざまなメディアの垣根を越えてコンテンツが流通するようになり、ファンはそれまで以上に自由に、意見交換や二次創作をはじめとしたファン活動を展開するようになった。そんな時代の変化を包括的に指し示す概念だ。
もちろん、2006年(「あとがき──YouTube時代の政治を振り返る」は2008年に追記)に原書が刊行された本書の描く「変化」は、2021年現在においてあまりにも当たり前の風景になってしまっている。加えてツイッターもインスタグラムもTikTokも本書には登場しない。むしろ、SNSが存在する以前のファンダムの生態が今とそこまで大きく変わらないことに驚いてしまうかもしれない。そうした意味でも、本書で展開される具体的なコンテンツやファンダム分析は、現代の読者にとってもじゅうぶんに楽しめるものになっている。

本書前半では、アメリカの人気リアリティ番組『サバイバー』、『アメリカン・アイドル』の視聴者たちの作品へのコミットメントが取り上げられる。視聴者はネタバレのリークや視聴者投票を通じて、本来一方的に提供されるだけの番組に、能動的に関わろうとする。中盤以降は、制作者にとっても無視できないほどの影響力を持つ『スター・ウォーズ』、『ハリー・ポッター』、『マトリックス』といった大作のファンダムの生態が、二次創作やさまざまな論争を通じて描き出される。分析を読み進めるうちに、抽象的だった「コンヴァージェンス」概念が少しずつ像を結んでいく。
さらに、そうした受け手の「能動性」は、本書後半で「政治とポップカルチャー」というテーマに接続される。大衆性があり裾野の広いポップカルチャーは、それ自体が目立ったイデオロギーを持たないがゆえに政治的に利用されることもままあり、とりわけSNS普及以降はそうした施策を当たり前に目にするようになった。しかし本書の2004年、2008年のアメリカ大統領選についての分析を読めば、直球の人気取りからシニカルなパロディまで、ポップカルチャーの「政治利用」はSNS普及以前においても行われていたことがわかる。
ポップカルチャーの「政治利用」と「コンヴァージェンス」
本稿が注目したいのは、このポップカルチャーと政治の接近というテーマだ。それは、わかりやすい黒幕がいて動員の目的もはっきりしているような「政治利用」に限らない。むしろ興味深いのは、思わぬアクシデントのような仕方で、特定のキャラクターに政治的な意図や文脈が付されてしまうような事態だ。「コンヴァージェンス」の概念は、まさにそうした制作者もファンも意図しないようなかたちでの政治性の発生を記述する際に役立つ。
たとえば本書冒頭で紹介される『セサミストリート』のバートのエピソードはその典型だ。アメリカの高校生が悪ふざけで作ったビンラディンとバートのコラージュ画像のせいで、バートは(『セサミストリート』のほとんど放映されていない)アラブ世界において反米のアイコンになってしまった。SNS普及以前に起きた事件とは思えないほどに現代的なアクシデントに思える。
直近では、作者のまったく予想していなかったかたちでネットミームとして流行し、アメリカの人種差別主義者のシンボルにまでなってしまった「カエルのぺぺ」の例が印象深い。「ぺぺ」はアメリカでオルタナ右翼のアイコンになると同時に、香港の民主化デモにおいてもアイコンとして掲げられていた。ネットミームとしてフラットに流通しており、どのような政治的文脈でも受け入れてしまえるために、別々に生じたふたつの運動においてアイコンとして用いられたのである(両者での「ぺぺ」の使用に参照関係があったかどうかについては不明)。

ジェンキンズによる下記のフレーズには、こうした事態を予見するかのような記述が含まれている。
コンヴァージェンス文化にようこそ。ここは古いメディアと新しいメディアが衝突するところ。ここは草の根メディアと企業メディアが交差するところ。ここはメディアの制作者とメディアの消費者の持つ力が前もって予見できない形で影響し合うところだ。
『コンヴァージェンス・カルチャー』P24
アマチュアとプロが入り交じり、ファンが作り手の予想もしないようなコンテンツの楽しみ方を発明してしまう「コンヴァージェンス」な環境においては、ポップカルチャーがどのような(政治的な)影響力を持つのかは前もって予見できない。その結果、背景に悪意や陰謀がないにもかかわらず、そこに政治的な「機能」が発生してしまうというアクシデントも起こり得る。こうした事態を分析し得ることは、「推し」やファンダムの分析への応用可能性と並んで本書の重要なアクチュアリティだといえるだろう。
関連記事
-
-
久保田未夢&指出毬亜が語る、果林とエマの“言わずに伝わる”関係性「自分にないものを持っているからこそ、惹かれ合う」【『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』特集】
虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会『約束になれ僕らの歌』:PR -
「明るさで元気をくれる人」と「一番近しい“あなた”」。矢野妃菜喜&村上奈津実が考える、侑と愛がお互いに差し向けるまなざし【『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』特集】
虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会『約束になれ僕らの歌』:PR