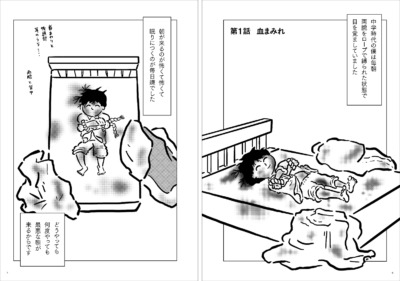『いだてん』に想を得て
しかし、それでもオリンピックは4年に一度しかない。ベストのタイミングで大会に臨むべく日々準備を重ねてきた選手たちには、とうてい簡単に諦め切れるものではないだろう。かたちはどうあれ、開催の可能性を模索するのは当然だし、社会に向けてもっと議論を喚起してもいいはずだ。
来年になっても国際的な移動が難しいようであれば、いっそ、参加を予定していた選手たちがそれぞれの国・地域に留まりつつも、オリンピックの名の下に競技大会を開いてはどうだろうか。いわば“リモートオリンピック”である。もちろん、多くの球技やレスリング、フェンシングなど選手が直接対戦する競技は遠隔では不可能だろうが、それでも競泳や陸上の競走種目に関してはタイムを競い合うことはできる。これらレースを同日、同じ時間に、各地を通信回線で結んでインターネットでライブ配信しながら実施したのなら、世界中が盛り上がるのではないか。出たタイムも公認はされないまでも、参考記録としてオリンピックの歴史に留めるのだ。希望をいえば、聖火を東京からどういうかたちで、全競技場が無理でも、世界の各地域を代表する都市にでも灯してほしいところである。
私がこのアイデアのヒントを得たのは、ある歴史上の事例だ。時は1948年、ロンドンで第二次世界大戦後初の夏季オリンピックが開催されたときのこと。昨年のNHK大河ドラマ『いだてん〜東京オリムピック噺〜』にも出てきたのでご存知の人もいるだろうが、この大会には、大戦中に枢軸国であったドイツと日本は招待されなかった。折しも日本では、競泳の古橋廣之進がめざましい活躍を見せていた。当時、日本は国際水泳連盟(FINA)からも除名されていたため公認はされなかったものの、古橋は世界記録を相次いで更新し、オリンピックに出れば金メダル間違いなしと思われた。しかし残念ながら参加が認められなかったので、日本水泳連盟では会長の田畑政治たちが一計を案じる。オリンピックと同日同刻に、明治神宮外苑プールで日本選手権を行おうというのだ。果たしてこのとき、自由形400メートルで古橋が、同1500メートルでは彼だけでなく橋爪四郎もロンドンオリンピックで優勝した選手のタイムを上回り、世界記録も更新した。

敗戦直後のまだ貧しかった日本でも、オリンピックに対抗してこうした大会を開き、非公認とはいえ世界記録が生まれたのである。古橋たちの快挙に多くの日本人が勇気づけられた。戦後の日本競泳界が本家オリンピックに対抗したのに対し、今度は新型ウイルスに対抗するため世界が足並みをそろえるのである。IOCに参加する国や地域には、紛争や経済状況などからまともな競技場すらないところも少なくないと思う。だが、かつての日本での先例を引き合いにリモートオリンピックへの参加を呼びかけたのなら、きっと賛同を得られるのではないだろうか。
このままでは立候補都市がなくなってしまう
さらにいえば、各地で分散して開催するリモートオリンピックは、コロナ以前から問題となっていたオリンピックの肥大化を解決するための糸口にもなるように思う。
今から20年前、2000年のシドニー大会の時点で199の国と地域から1万651選手が参加し、「もう、この規模が限界だ」との声がIOC内外で聞かれたという。しかし、データを見る限り、その後も大会の規模はますます大きくなるばかりだ。夏季オリンピックの参加国・地域は200、選手も1万1千人を超え、競技数も2008年の北京大会で28に達して限度いっぱいといわれていたのが、東京大会ではさらに33競技・339種目が予定されている。
東京大会は開催経費でもオリンピック史上最大になったといわれる。先ごろ報じられたところによれば、イギリスのオックスフォード大学の研究結果では、都市インフラ整備を含まない大会経費だけで158億4千万ドル(約1兆6800億円)に達し、これまで最大だった2012年のロンドン大会の149億5千万ドルをすでに上回ったという(『共同通信』2020年9月4日配信)。
開催にあまりにコストがかかるゆえ、最近ではいったんは立候補しながらも途中で辞退する都市も相次いでいる。2024年の夏季オリンピック招致でも、ボストンやハンブルクなどが撤退し、結局、パリとロサンゼルスしか残らなかった。そこでIOCは異例の措置ながら、2024年大会はパリ、次の2028年大会はロサンゼルスで開催すると同時に決めた(NHK『解説委員室』2017年9月14日配信)。これにあたってIOCのトーマス・バッハ会長が述べた「大きくて魅力的な鳥が2羽、目の前にいる。どちらかを手放す手はない」という言葉からも、このままでは立候補都市がなくなってしまうとの危機感が窺えよう。
IOCもまったく手を打ってこなかったわけではない。2014年12月の総会では、大会を開催する際の条件の緩和や、招致にかかる費用の削減などを盛り込んだ「アジェンダ2020」を採択していた。そこには、「主に地理的要因や持続可能性の理由から、複数の競技または種別を開催都市以外で、また例外的な場合は開催国以外で実施することを認める」といった提言も含まれる(小川勝『東京オリンピック「問題」の核心は何か』集英社新書)。今までIOCが、オリンピックはあくまで一都市での開催を原則としていたことを思えば、かなり踏み込んだものといえる。
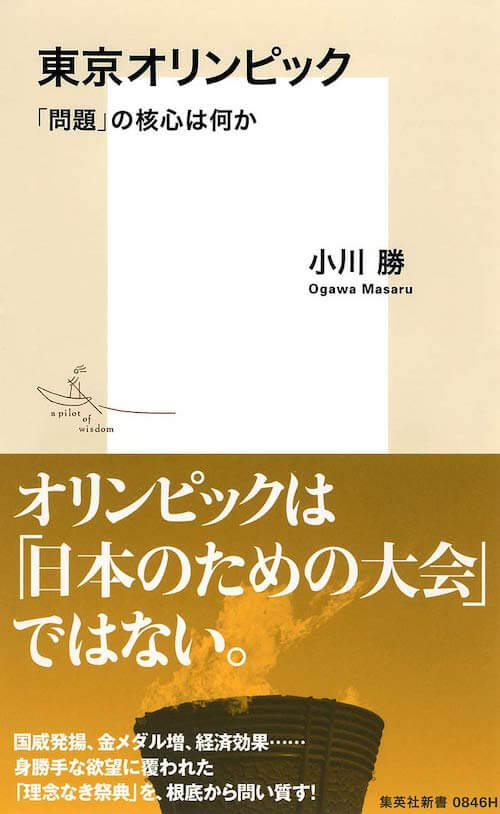
このIOCの提言は、将来的にオリンピックを複数の都市に分散して開催する方向へ道を開いたものとも取れる。もし分散開催が本格的に認められれば、すべての競技を受け入れるだけの余裕はない中小規模の都市にもオリンピック開催のチャンスが生まれる。それは、より多くの地域での開催を目指すべきオリンピック精神にも叶うはずだ。私の考えるリモートオリンピックも、こうした流れのなかで一種の予行演習の役割を果たせると思うのだが、どうだろうか。
実は、コストがかかり過ぎるがゆえに開催地に立候補する都市が激減したのは今回が最初ではない。1970年代にも同様の現象が起き、オリンピックは存続の危機に立たされた。そこから脱却する契機となったのが、1984年のロサンゼルスオリンピックである。同大会では、大会組織委員会が開催費用を抑えるため、既存の施設を活用すると共に、多くの企業から協賛を募って資金を集めた。この手法が大きな黒字をもたらしたため、以降の大会でも踏襲され、オリンピックは危機を乗り切ったわけである。同時にIOCは、より高い収益を求める方向へと舵を切った。そのために、高額な放映権料を支払うアメリカのテレビ局の意向が開催時期や競技日程にまで影響を及ぼすなどといった弊害も出ている(このあたりの経緯については小川勝『オリンピックと商業主義』〈集英社新書〉に詳しい)。しかし、今回のコロナ危機はそうした流れを変えるチャンスではないか。将来に向けてオリンピックが歩むべき道を示すという意味でも、東京オリンピックをどういう形で行うか、今一度議論を呼びかけたい。

-
関連リンク
- 東京五輪は「新型コロナに関係なく開催」 IOC副会長『AFPBB News』2020年9月7日配信
- 東京五輪1年前セレモニー開催、池江璃花子がメッセージ発信『AFPBB News』2020年7月24日配信
- コロナ禍東京五輪、もうちょっと頑張ってみませんか(『為末大学』)『日刊スポーツ』2020年8月6日配信
- NHK大河ドラマ・ガイド『いだてん 完結編 3』宮藤官九郎 作、NHKドラマ制作班 監修/NHK出版
- 東京五輪、開催経費は史上最大『共同通信』2020年9月4日配信
- 「2024パリ、2028ロス・同時決定の意味するもの」(時論公論)NHK『解説委員室』2017年9月14日配信
- 『東京オリンピック「問題」の核心は何か』小川勝/集英社新書
- 『オリンピックと商業主義』小川勝/集英社新書
関連記事
-
-
マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】
『DAIENKAI 2025』:PR -
ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】
『DAIENKAI 2025』:PR