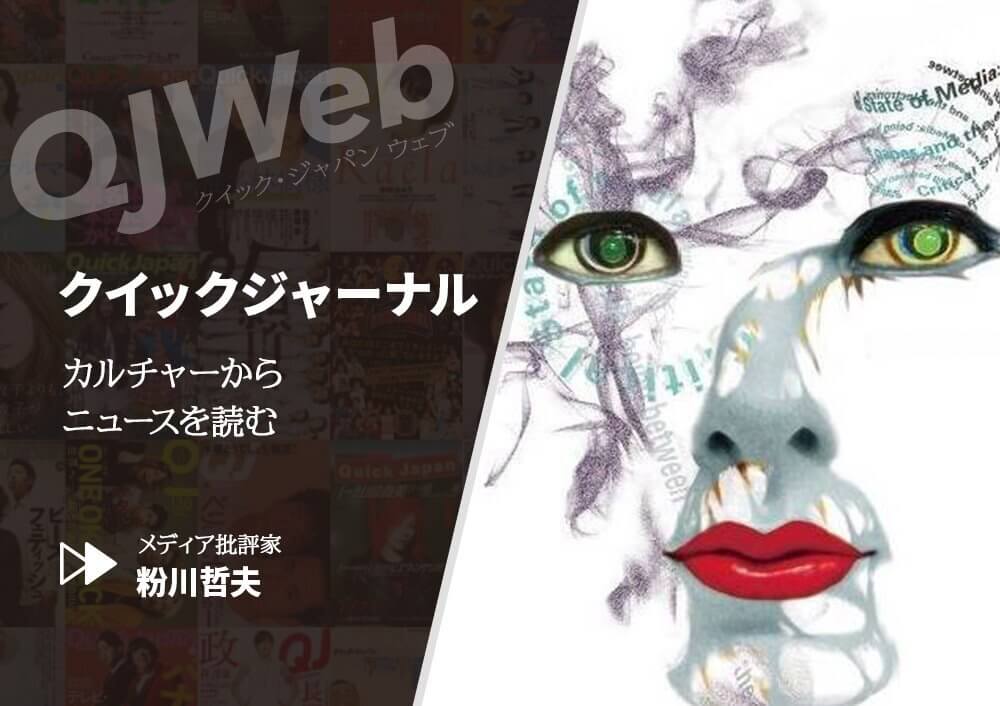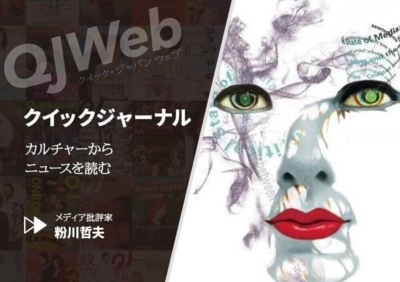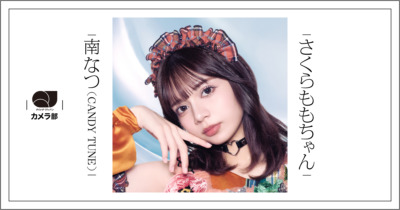『メディアの牢獄』(1982年)や『もしインターネットが世界を変えるとしたら』(1996年)などの著書を持つメディア論の先駆者として知られ、ラジオアートパフォーマーとして今も精力的に活動をつづけるメディア批評家の粉川哲夫。
かつてニューヨークに居を構えていた彼が、現在アメリカ中を揺るがしている「BLACK LIVES MATTER(黒人の生命は大事だ)」について――トランプ大統領と映画『ブレージングサドル』の関係などについて指摘しつつ――縦横無尽に論じます。
目次
ワシントンD.C.に“Black Lives Matter Plaza”という通りが正式に誕生
アメリカが燃えている。それも、かつてのように、ロスとかシカゴとか特定の場所だけでなく、6月5日現在、50州全部、450カ所以上に広がっている(NBC News, “Map: Protests and rallies for George Floyd spread across the country”)。
ベトナム反戦デモが起こった60年代でもこれほど同時多発的で広範なデモはなかった。発端は、警官によるジョージ・フロイドの殺害である。彼は、ミネアポリスの食料品店で偽札を使ったとして警察を呼ばれ、逮捕されたが、無防備で素直に警官の命令に従っているのに地面に這わせられ、窒息死するまで首を膝で絞めつけられたのだから、驚きだ。そのすべての過程が監視カメラやスマホの映像に残され、全米に流されたことで、抗議や暴動が広がった。
トランプ大統領は、このデモは、「極左アナキスト集団アンティファ(Antifa)」が背後で煽動している「陰謀」だと見なすが、1集団が組織できるような規模ではなく、そのスタイルも実に多様で、パフォーマンス性にあふれている。たとえば、政治感覚の敏感な都市オークランドでは、25歳の黒人女性ブリアンナ・ノーブルが、5月25日にミネアポリスでフロイドが警官に絞め殺されたニュースを知ると、数日後、愛馬に「BLACK LIVES MATTER」というプラカードを下げ、市中に繰り出した。オークランドでは、街頭の乗馬は合法である。このたったひとりのデモはただちに関心を呼び、馬のあとにつづく人々が増えていった。また、馬に乗った集団デモも登場する。ちなみに、都市の街頭の馬は警官とのイメージが密接だ。ニューヨークでも馬の警邏(けいら)はまだつづいている。
私は、80年代のパリで、白馬にまたがった女性を先頭にしたデモ隊を見て新鮮な印象を受けたが、今にして思えば、先導者に従って動くデモはもう古いのだ。ノーブルのデモは、そういうのとは根本的に違い、一緒に歩く人たちは、おもしろいからついて行くのであり、彼女のプロテストに賛同したから同行しているに過ぎない。
BLACK LIVES MATTERという言葉は今、このデモのスローガンになっている。6月5日、ワシントンD.C.の市長ミュリエル・バウザーは、ホワイトハウス近くの通り(16番街)の車道に、地区の壁画ペインティングのチームに依頼して、黄色のペイントで「BLACK LIVES MATTER」という文字を描かせ、この通りを正式に“Black Lives Matter Plaza”と名づけた。その着想のセンスと実行のすばやさが素晴らしい。