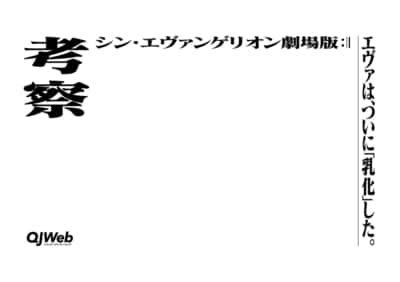新しくなれる邂逅の可能性
映画であることが強く意識されている。できるだけ、巨大なスクリーンで出逢ったほうがいい。シンクロ率が上がるから。
細密であると同時に、ダイナミック。とりわけ、戦闘シーンに顕著だが、円形の動きが視覚の残像を形作る。空中戦が多いことも要因だが、遠近感が消失する瞬間が多々あり、序盤ではこの初めての感覚に酔いしれることになる。
地に足がついていないが、決して夢幻的ではなく、闘いの臨場感は確固としてある。つまり、浮遊しているわけではなく、新しいリアリティとフォームが獲得されている。
映像的には紛れもなく新境地だが、考えてみれば、現代を生きるということは、こういうことなのではないか、と発見もさせられる。今を生きているということに、思い当たる。
私たちは、不確実な現実を、確実に生きている。不確実な世界に、確実に存在している。それを、戦闘描写を通して植えつけているのだ。
郷愁が、ない。馴れあいが、退けられている。が、排他的ではない。邂逅への誘いだけがある。お互いに、新しくなれる邂逅の可能性が、ここでは提示されている。
先鋭的な戦闘場面の一方、テレビシリーズを彷彿とさせる丁寧で豊かなドラマ部分がある。新劇場版では、かなり圧縮されていたキャラクターやエピソードが、じっくり腰を据えた立体性によって復興している。パラレルな物語なのに、よみがえるものがある。新しい懐かしさ。デジャヴのような心地のよさ。海外にいるからこそ、母国を想える、あの感触。ひとつの匂いが、無数の記憶を愛撫する、あの作用。距離と、親密さ。人間、人間、生きもの、生きもの。愛おしさが、募る。
エヴァは、ついに「乳化」した。
革新と伝統が、共にあること。
互いが、互いを補完し合っている。
だからこそ、何度もはっとされられる。
温故知新。最新の温故知新。太古の温故知新。
ある場面で、ひとりの人物が精子のように映った。ある場面で、ひとつの空間が卵子のように見えた。
女性性が、すべてにおいて先陣を切ってきた、このシリーズが示すジェンダーのありようについて、改めて考えたくなった。
コンプレックスと母性。神と人間。複製とオリジナル。父と子。過去と未来。死と生。機械と肉体。テレビと映画。大人と子供。アニメーションと実写。女と男。
対立するすべてのファクターの融和をまさぐってきたのが、エヴァだった。宗教学、哲学、倫理学、社会学が飛散し、入り乱れてきた理由が、ついに明確になったように思う。
水と油は本来、中和し得ない。分離するしかない運命を生きている。
だが、しかるべき温度と技術さえ用意できれば、両者は「乳化」という現象によって結びつく。
エヴァは、ついに「乳化」した。四半世紀かけて、ようやく「乳化」した。時間がかかった、とは思わない。それは必要な時間だった。
3.11以後であること。
コロナ以後であること。
この点も結果的に引き受けている。
頼もしい「乳化」である。
木のまわりで追いかけっこしていた虎たちが、いつの間にか溶け合い、バターになったおとぎ話を想い出す。
虎がバター化することの解釈は、人それぞれかもしれないが、私は讃えたい。
エヴァの「乳化」を、心から讃えたい。
-

映画『シン・エヴァンゲリオン劇場版』
企画・原作・脚本:庵野秀明
総作画監督:錦織敦史
作画監督:井関修一、金世俊、浅野直之、田中将賀、新井浩一
副監督:谷田部透湖、小松田大全
デザインワークス:山下いくと、渭原敏明、コヤマシゲト、安野モヨコ、高倉武史、渡部隆
テーマソング:「One Last Kiss」宇多田ヒカル(ソニー・ミュージックレーベルズ)
音楽:鷺巣詩郎
エグゼクティブ・プロデューサー:庵野秀明、緒方智幸
コンセプトアートディレクター:前田真宏
監督:鶴巻和哉、中山勝一、前田真宏
総監督:庵野秀明
制作:スタジオカラー
配給:東宝、東映、カラー
宣伝:カラー、東映
製作:カラー関連リンク
関連記事
-
-
マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】
『DAIENKAI 2025』:PR -
ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】
『DAIENKAI 2025』:PR