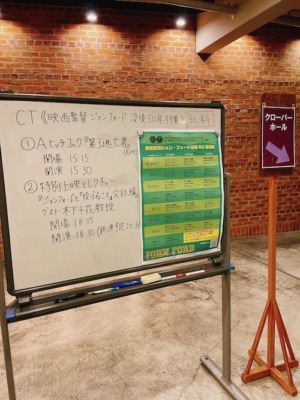“とにかく画面を凝視しろ”という一貫した主張
信じられないことだが、この映画「ジョン・フォードと『投げること』完結編」は、蓮實重彦の文章が読む者に与える感触によく似ているのだ。無数のジョン・フォード映画群から「投げること」だけを抜粋して編集しているだけにすぎないこのフィルムは、なぜか蓮實重彦を読むという体験にとてもよく似ている。
蓮實のライフワークと呼んでいい『ジョン・フォード論』から、いくつかの部分を抜粋してみよう。

1970年代の初頭に、フォード論を書きたいという意志というより夢を正式に口にしている
(『ジョン・フォード論』蓮實重彦/文藝春秋/2022年/p379「とりあえずのあとがき」より)
彼は80年代の東京で、そして90年代のパリで行われたジョン・フォードのレトロスペクティブを大きな契機とし、現実的な執筆は雑誌『文學界』で2005年から2021年まで16年かけて行われ、さらに大幅な書き直しを経て、一冊にまとめ上げた。発想・構想・実現までに半世紀を費やしている。この半世紀という歳月の長さは、ちょうどジョン・フォードの監督生涯(1917年監督デビュー、最後の監督作は1965年)のそれと一致する。
これからフォードの作品と向かいあおうとしているわたくしたちは、何よりもまず、画面に見えているもの同士の対立や思いもかけぬ響応関係に、じっと瞳を注ぐことだけは怠らぬつもりでいる
(前掲書、p26「序章 フォードを論じるために」より)
すなわち、すべてが同じ資格で見るものに委ねられているという視点から、わたくしが生まれるより遥か以前に撮られた作品であろうと、それを「過去」の作品としてとらえることなく、そのつどいまというかけがえのない「現在」としてそれらに向かいあうことにしたのである
(前掲書、p36同上)
こうしたステイトメントはいわば蓮實重彦の十八番(おはこ)であり、かつて「表象主義」と呼ばれた。物語やセリフや背景や作家のイデオロギーではなく、とにかく画面を凝視しろ。これが彼の一貫した主張である。「今」として見つめろ。
蓮實が監督した映画はまさに、フォードのサイレント時代からカラーの遺作まで縦横無尽に巡りながら、そのすべてが「投げること」という一点で現在化している。それは、ひたすら画面を「見る」ことで過去の映画も現在形にするレッスンにほかならない。
「未知の情動」と呼ぶしかない「ジョン・フォードと『投げること』完結編」
本書のクライマックスともいうべき第五章は「身振りの雄弁 あるいはフォードと「投げる」こと」と題されている。この章の「映画化」、あるいは「映画版」が「ジョン・フォードと『投げること』完結編」であることは間違いないだろう。
ここでは「投げること」をめぐる詳細な記述が、何本かの重要なフォード作品を軸に行われる。だが、蓮實の筆が冴え渡るのは次のようなときである。
多くの場合、個人がその振る舞いを孤独に演じることになるのだが、その瞬間に、個人的な「投げる」主体は、しばしば作品に未知の情動を導き入れる
(前掲書、p261「第五章 身振りの雄弁 あるいはフォードと「投げる」こと」より。以下同)
とりあえず、前後の文脈は考えなくてよい。蓮實重彦という書き手は、ふとした瞬間に「未知の情動」なる艶かしく悩ましい一語を挿入して、読む者を魅了する。ほとんど造語と呼んでいい「未知の情動」の一語は、なぜ「投げること」が繰り返されるのか、なんらその答えになっていないにもかかわらず、私たちを納得させる。
ジョン・フォードの映画の中で「投げること」が反復される理由も、そもそも映画というものを見つめる理由も、この「未知なる情動」と出逢うためなのではないか。そう幻惑されるのだ。そして、蓮實が三宅と監督した作品もまた「未知の情動」と呼ぶしかないと、意識が遠のいていく。
人は、この瞬間、「投げる」身振りが純粋状態の運動としてスクリーンに露呈されていることに思わず息をのみ、意味の論理を超え、稀有の身振りを顕在化させるものこそが映画に独特な瞬間を見るものにつきつけ、これを魅了するとも驚愕するともいいがたい未知の体験へと導くものこそが映画にほかならぬと、自分自身にいいきかせるしかない
(前掲書、p264)
蓮實は自身の言説を反復する。それは変奏ではなく、伝染だ。蓮實重彦の言葉が、来たるべき蓮實重彦の言葉に伝染していく。無論、読者もまた、このレトリックを超えた呪文のような何かに伝染する。「投げること」という主題もまた、あの映画の中で伝染していたのではないか?
人は、純粋状態の運動がスクリーンを不意に活気づけるさまに驚くしかない
(前掲書、p269)
そして、さらにこう言い募る。
映画を見るとは、この一瞬の変化をとらえる動体視力の体験にほかならず、ジョン・フォードは、「投げる」ことの主題体系を作品の細部まで行きわたらせることで、その驚きの体験へと何度もくり返して見る者を誘う。フォード的な「投げる」ことの主題とは、そのつど変化するまごうかたなき誘惑の記号にほかならない
(前掲書、p272)
これぞ蓮實節だ。「動体視力の体験」「誘惑の記号」といったキャッチーなフレーズを用いながら、ニュアンスの反復を活性化する。そこで語られていることはほぼ同じことなのに、読む者を捉えて離さない。フォードの「投げること」と同じように。
それが導き入れる身振りによって、悦び、悲しみ、諦め、苛立ち、憤りなど、ときには矛盾しあってさえいるさまざまな感情が視覚化されてゆくことは、いまや明らかになり始めているだろう
(前掲書、p317)
そう、私たちは「投げること」を通して、多種多様な感情が矛盾を乗り越えるように平然と混じり合う様を見届ける。映画を見つめるということは、手放された感情に、真新しい感覚で出逢い直すことなのだと知る。映画が手放した感情と、私たちが手放した感情とが、「投げること」という行為によって交錯しているようにも思える。
文章が映画に敗北する瞬間──「投げること」の陰影と祝福
ジョン・フォードの遺作『荒野の女たち』(1965年)は「投げること」で終幕を迎える。そうして、あまりにも潔く「THE END」の文字が銀幕に浮かび上がる。そして、この簡潔なフィルム「ジョン・フォードと『投げること』完結編」も、その「THE END」とともに幕を下ろす。カーテンコールは、ない。
断言するが、これほど大胆なイメージでみずからの映画から遠ざかってみせた映画作家は、ジョン・フォードをのぞいて、世界には一人としていまい
(前掲書、p325)
蓮實はそんな言葉で、この章を締めくくる。そこには、微かな自負もあるのではないか。徹頭徹尾、引用だけで構成したこの処女作の「遠ざかり方」も誰もやったことがないだろう。そんな無邪気な笑みさえ見え隠れする。
それは野心などとは到底呼べない代物である。かつて蓮實は『シネマの煽動装置』(話の特集/1985年)で一冊まるごとワンセンテンス(一文)を貫き通したことがある。快挙にして暴挙。だがそれは野心でも遊びでもなく、文体の不断の反復。ただそれだけであった。その有り様もまた、このマイクリレーばりの処女監督作に近い。
だが、こうもいえる。蓮實重彦の初監督作は、蓮實重彦の文章よりも遥かに簡潔であり、そして単純だ。それは、蓮實が自身の簡潔性と単純性(これまでの引用すべてがそれを物語っているだろう)を躊躇なく「投げ出すこと」でついに顕在化したのだと。
つまり、蓮實重彦は文体という己を差し出し、それを「投げた」。映画は、さらに簡潔で単純な連なりを「投げ返した」。
それはある意味、文章が映画に敗北する瞬間であり、しかし、これほどまでに初々しく、みずみずしく、さらに晴れがましい負けっぷりは、誰も見たことがない。
そこにこそ「投げること」の陰影と祝福がある。
2022年は、蓮實の信頼する教え子である青山真治が3月に、そして蓮實より6歳年長のゴダールが9月に亡くなっている。両者ともに蓮實重彦とは縁が深い。『ジョン・フォード論』はその間の7月に刊行され、「ジョン・フォードと『投げること』完結編」も同じ年に完成している。それは悲痛な偶然かもしれないが、やはり映画が導き入れた「未知の情動」による必然だったのではないだろうか。
関連記事
-
-
マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】
『DAIENKAI 2025』:PR -
ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】
『DAIENKAI 2025』:PR