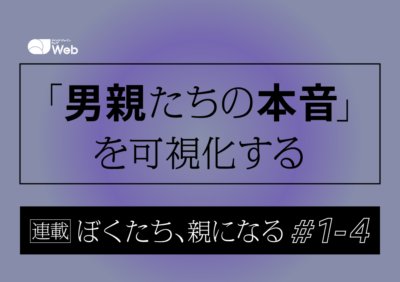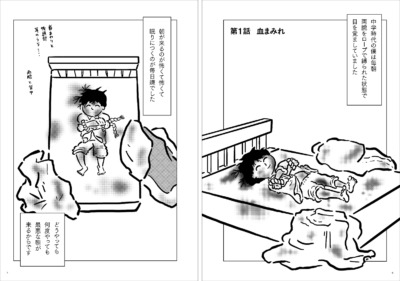子を持つ男親に、親になったことによる生活・自意識・人生観の変化を、匿名で赤裸々に独白してもらうルポルタージュ連載「ぼくたち、親になる」。聞き手は、離婚男性の匿名インタビュー集『ぼくたちの離婚』(角川新書)の著者であり、自身にも2歳の子供がいる稲田豊史氏。
第8回は、1歳半の子供がいるテレビディレクターの50代男性。夫婦ともに待望の子供だったが、彼は育児に対して大きな不満を抱えていた。
テレビ制作会社でディレクター職を務める徳岡譲さん(仮名/52歳)は、49歳のとき、同じ会社で当時31歳だった女性(現在34歳)と結婚。ふたりとも子供を望み、男の子を授かった。
20〜30代のころは激務が続き、結婚のことなどまるで頭になかった徳岡さん。しかし40代に入ると「飲み仲間がどんどん結婚して会えなくなり、プライベートがつまらなくなったから」という理由で「自分もそろそろか」と思い始め、結婚相談所に登録。婚活を開始した。そこでは良い相手に出会わなかったが、灯台下暗し。18歳下の同僚と交際、社内結婚に至る。
取材時点でお子さんは1歳半。すくすくと育っているが、徳岡さんには大きな不満がある。「育児で満たされなかった」のだ。
※以下、徳岡さんの語り
目次
育児でまったく満たされなかった
妻の出産にあたり僕も育休を取ったんですが、数週間のうちに「これが育休かよ!」って本当に嫌になりました。
コロナ制限ゆえに、分娩は途中10分程度立ち会っただけ。退院後も生まれたばかりの子供と直接的に触れ合えるのは妻だけで、僕はスーパーにひとりで食材を買いに行ったり、料理したり、掃除や洗濯をしたりと、出産前と同じような家事ばかり。
それをひとりでやるものですから、さらに孤独が募ります。子供の沐浴もお湯の用意だけ。妻が「自分が洗いたい」と言うので、初めはほとんど触らせてもらえませんでした。
自分が「親」ではなく、母子を遠くからサポートする「小間使い」のような気分。しかも妻の関心は常に子供に行ってしまうので、疎外感すら覚えました。

妻の希望で完全母乳だったことも大きいです。僕としては、妻が夜中に授乳で起きなくて済むようミルクも提案したんです。ミルクなら、夜中でも僕が準備してあげられるから子供に触れられますし、妻の負担が少しは軽減されるので一石二鳥。
でも、妻は母乳の分泌量を不安に思い、完全母乳を貫きたいと。彼女の意志は尊重しましたが、あとあとになって心に穴が空いた気がしました。当時の僕は明らかに暗いというか、うつ気味だったと思います。妻もそう言っていました。
もちろん、子供が起きているときに抱っこはできます。でも、そういうことじゃない。子供のお世話をしている感がない。この命に必要なことは何ひとつしていないような喪失感がありましたし、「関われない」ことから来るストレスがものすごく大きかった。
ひと言でいうと、全然満たされなかったんです。
直接的に子供と触れ合わなくても、夫による「サポート」が大事なんだという理屈もわかります。ただ、僕だってもっと関わりたかった。自分たちがこれから育てていかなきゃいけない生命体が、今この瞬間どういう状況なのかを、もっと把握したかった。じっと見つめていたかった。
男性である僕がそれを母性と呼んでいいのかどうかはわかりませんが、そういうものが僕の中に芽生えたのはたしかです。
「サポート」が嫌だと言ってるわけじゃありません。でも、「サポート」に徹していると、瞬間瞬間の子供の反応、表情の変化みたいなものを全然見られないじゃないですか。
今はもう息子も1歳半で卒乳もしたので、あのころとは手のかかり方も変わりました。僕が息子のご飯も作ってあげられるし、不思議とパパっ子なのでたっぷり触れ合えてはいます。
だけど……あのときの、あの瞬間に求めていたものは、もう戻ってこない。
社会がパパの不満を「無視」している
ただ、この不満を妻にぶつけたいわけじゃないんです。生まれたばかりの子供にパパが何かしてあげたいと思っても満たされない状況があるってことを、この社会が認識してない。というより「無視」してるってことが問題かなと。
国も自治体も、イクメンを推奨するわりには、基本スタンスが「パパはママを支えましょう」じゃないですか。いやいや、もっとパパも子供に触れさせてくれよ!と思いました。

出産直後から「母になる」女性と違って、男性が「父になる」のはもっとあと、みたいな言い方をされるじゃないですか。
だけど男性が育休を取れば、より長く、生まれた子の近くにいることになります。従来とは違う関わり方になるし、そのことによって「父性」の感じ方も変わっていくんじゃないか?と疑問を抱きました。
僕の中に芽生えた母性らしきものとか、「もっと見つめていたい」みたいな感覚が、男にはないものだと社会が決めつけてる。男が育児を実感する、そこに義務感ではなく充実感があるってことが、この社会の中では必要ないものにされてるなって。
社会を規定してる側、仕組みを作ってる側が、その程度の解像度でしか把握してないってことです。これは僕の体感ですが、育児相談スタッフや助産師さんでさえ、「男性に宿る母性」の存在を認識しようともしない。出産後のメンタルヘルスに関するアンケートに答えるのは母親だけ。出産後の心療相談も母親だけ。
結局、育児は母頼み。男にも母性があるなんて、誰も想像すらしない。だからいつまで経っても「パパのサポート意識喚起」でしか発想をスタートできない。
いや、そうじゃない。気づいてくれよ。男にだって育児の実感が欲しいんです!
出産が「閉じられている」
結婚して、子供ができて、本当にいろいろなことが予想外でした。ひとつ、すごく感じたのは、子育ての前段階である出産が「閉じられている」ってことです。
よく言うじゃないですか、「現代社会では死が遠くなった」って。大昔は日常生活の中でわりに遺体を目撃していたけど、今はそれが見えなくなっていると。それと同じで、現代社会では出産が遠くなりました。
要は、出産が「個人の体験」になってしまった。ノウハウが受け継がれてない。親に自分を産んだときのことを聞いても、30年とか前のことだから忘れちゃってるし、30年前の常識は今の常識と違う。なんなら間違っていて参考にならない。
ネットには山のように情報が落ちてますけど、むしろ振り回されます。「ああしたほうがいい、こうしたほうがいい」という個人のノウハウが大量にクラウド化されてはいますが、その「説」のどれを採用するかはこっちで取捨選択しなきゃいけない。別のタスクが増える。初めての子供で、そんなことをしてる余裕なんて本当にない。

もうひとつ思ったことがあります。よく、第二子は第一子に比べてざっくり育てる、第一子ほど手間をかけない、でも、のびのび育つっていうじゃないですか。
じゃあ、なんで親がその適当さを第一子からいきなり持てないかっていうと、これも社会的に子育てのノウハウや経験が共有されていないからですよね。
昔みたいに、ご近所なり所属コミュニティなり近隣に住む親族なりといった身近に赤ちゃんがいれば、自分の第一子は「第一子」ではありません。子育てのなんたるかのいろんなパターンを事前に観察してますから。
せめて親が同居していれば、出産はともかく育児フェイズではもう少し安心感が出てくると思います。親は「第一子」経験者ですし。
でも、今はそうなってない。
核家族は人工的な単位
ふたつとも、諸悪の根源はたぶん、日本の核家族化です。うちもそうですが、特に都市部の、近くに血縁者がいない核家族。
僕は子供ができて、核家族って本当に孤立してるんだなと痛感しました。人類にとって実にアンリアルというか、作られた、人工的な単位ですよ、核家族って。その単位がいかに苦しいかって。
女性は昔から育児を一手に押しつけられていましたが、しっかりした共同社会があり、各々が大家族だったころは、おじいさんやおばあさんといった手の空いている人に子供を預けることもできました。
子供はその両親だけの子ではなく「みんなの子」みたいな意識があった。それが人間社会の自然な状態だった気がします。

でも1960年代から70年代にかけて急激に核家族化が進んだ結果、子育てが孤立しました。祖父母が同居しておらず、都市部では近所のつながりも希薄化した結果、家庭内で妻ひとりに育児を押しつけることになったんです。
「育児を押しつけられてつらそう」な女性を母親に持った子供たちは、「ああ、育児ってつらいものなんだ」と当然思いますよね。僕もそうでした。
母の人生は、子供の成長に無頓着な父に振り回されっぱなしだったので。
父と別居した母は、それでも父についていった
僕の育った家庭は、ちょっと特殊です。
僕はひとりっ子で生まれは東京なんですが、僕が1歳のときに、それまで機械工だった父が一念発起して受験勉強を始め、関西の国立大学に入学しました。それで一家そろって関西に引っ越したんです。
母は大手銀行勤務の一般職でしたが、出産後に退職。その後、家計を支えるため、保育士や事務などのアルバイトを転々としていました。

僕が5歳になると、父は「パリの大学に留学したい」と言い出し、一家でフランスに引っ越しました。僕は5歳から12歳までパリ暮らしの帰国子女なんです。
僕は僕で環境の変化に慣れるのが大変でしたけど、母は輪をかけてつらかったでしょう。フランス語だって、僕のほうは子供ゆえの適応能力ですぐに覚えましたが、母はさぞ日常生活で困ったはず。
未だに聞けてないんですが、父が関西やパリで学生をやっていたときの一家の収入が謎なんです。父はほぼ無収入、母はアルバイト。家計はいったいどうなっていたのか……。その点においても、母の心労は相当のものだったと思います。

実は、パリ時代から両親は別居していました。渡仏後しばらくして父が家を出ていってしまったんです。そうなると母がフランスに残る理由はないはずですが、僕を連れて帰国したりはしませんでした。
そこはいろいろと事情があったんでしょう。最終的には離婚しましたが、別居とはいえ、当時はまだ家族でしたから。子供が父親と完全に離れた生活を送るのはかわいそうだ、とか。
フランスから帰国後、父は関西の大学に助教授として就任。その数年後には東京の私大に転勤しましたが、母は僕を連れて父の転勤先を追いかけ、一貫して父の職場の近くに住み続けました。
父のようになりたくなかった
この家族の、一番の被害者は母です。いい人がいれば再婚して新しい人生を歩んでほしかったけど、彼女はその選択をしませんでした。
そういう母を幼いころから近くで見ていて思ったんです。「家庭って、そんなにいいもんじゃないな」って。僕の晩婚の原因のひとつは、確実にそれです。自由に生きた父親に振り回された母親の人生が、どこか僕の心に影を落としていました。

婚活当初、僕の子供願望はさして強くなかったんです。相手の年齢にもよりますし、いてもいなくてもいいか、くらいのスタンスでした。ただ、あるとき母に言われたんですよ。「子供を作っておかないと、表現の幅が狭まるわよ」って。
実は、母は帰国後に文筆家を目指し、何冊か著作も出版しました。表現活動をしている人の言葉だけに、まがりなりにも映像制作をしている僕にはすごく響きました。
それになにより、母の想いに「応えたい」という気持ちが僕の中にありました。母子家庭で当然ママっ子でしたし、ひとり息子を抱え、異国の孤独に生き抜いた母の人生をずっと見ていましたから。
僕は、我が子に無頓着だった自分の父親と違って、育児と向き合いたかった。そして、その「育児と向き合う」は「妻と同じくらい子供に触れる」ことだったんだと、自分に子供が生まれて気がつきました。
ただ、そんな気持ちが男性にもあるということに、この社会では誰も見向きもしない。問題にしない。心底、がっかりでした。
新しい家族のかたち
※以下、聞き手・稲田氏の取材後所感
国や自治体が「パパはママを支えましょう」というスタンスであるという主張、社会がパパの不満を「無視」しているという感覚は、あくまで徳岡さんのものであって、「そんなふうに感じたことはない」と思う方もいるだろう。また、国や自治体の担当者からすれば、「昔に比べればずいぶんと変わったはず」と反論したくなるかもしれない。
しかし、都市部に住み、仕事柄社会事情によく通じ、育休を取るほど“意識の高い”50代の男性が実際に大きな不満を感じたという事実は、無視できない。こういう人はきっとほかにもいる。
徳岡家では、育児に関する夫婦喧嘩が未だに絶えないという。それもまた、徳岡さんが育児をパートナーに丸投げせず「積極的に関わりたい」という思いが強いゆえの衝突なのだろう。
取材の終わりがけ、徳岡さんは「これは、のろけですけど」と前置きして言った。「妻は“子供”が欲しかったんじゃなくて、“小さい僕”に会いたかったそうなんですよ」
満たされない「母性」に不満を抱く夫。子供の庇護者としての母親になりたいのではなく、夫のような存在をもうひとり求める妻。
徳岡さんの言う「人類にとって実にアンリアルな、人工的な単位」である核家族化がもたらしたもののひとつが、このような「新しい家族のかたち」なのかもしれない。もちろん、ポジティブな意味で。
【連載「ぼくたち、親になる」】
子を持つ男親に、親になったことによる生活・自意識・人生観の変化を匿名で赤裸々に語ってもらう、独白形式のルポルタージュ。どんな語りも遮らず、価値判断を排し、傾聴に徹し、男親たちの言葉にとことん向き合うことでそのメンタリティを掘り下げ、分断の本質を探る。ここで明かされる「ものすごい本音」の数々は、けっして特別で極端な声ではない(かもしれない)。
本連載を通して描きたいこと:この匿名取材の果てには、何が待っているのか?
関連記事
-
-
マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】
『DAIENKAI 2025』:PR -
ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】
『DAIENKAI 2025』:PR