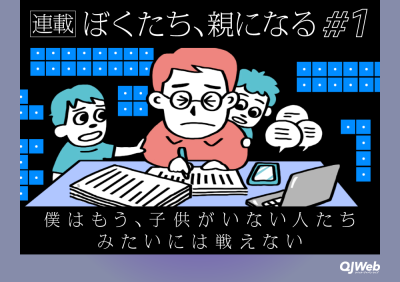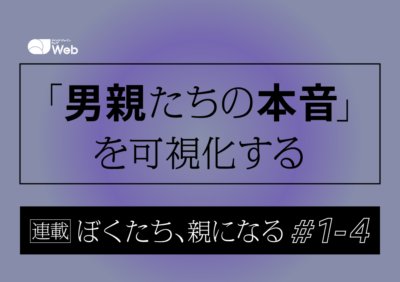「子供にも一家団らんにも興味がない」50代記者。再婚後に子供を作ったワケとは【#13後編/ぼくたち、親になる】

子を持つ男親に、親になったことによる生活・自意識・人生観の変化を、匿名で赤裸々に独白してもらうルポルタージュ連載「ぼくたち、親になる」。聞き手は、離婚男性の匿名インタビュー集『ぼくたちの離婚』(角川新書)の著者であり、自身にも2歳の子供がいる稲田豊史氏。
全13回続いた本連載も今回で終了。最終回は、新聞記者の50代男性。長年「子供はいらない」と強く思っていたが、再婚後に子供を作った理由とは。
新聞社の文化部記者である加古川学さん(仮名、51歳)は、35歳の時に同い年の久美さん(仮名)と「子供は作らない」という前提で結婚する。しかし5年後、久美さんは心変わりして「子供が欲しい」と言い出し、かつ加古川さんに仕事の休業を迫ったことで夫婦関係が悪化。その後5年間にわたり夫婦関係外来に通うも、離婚した。
一方、加古川さんは久美さんと別居中に、17歳年下の茜さんと交際をスタート。結婚する気はなかったが、茜さんからは「子供が欲しいから結婚したい」と迫られる。
※以下、加古川さんの語り
「生活」に興味がない
当時の茜は30歳。聞けば、今まで子供にはまったく興味がなかったけど、周囲の友人たちがぽつぽつ子供を作りはじめたことで感化され、欲しくなってきたとのことでした。
今までの僕であれば、要求をリジェクトして終わりです。もともと子供は欲しくないし、それはずっと変わっていない。自分の中に「父親」のロールモデルもビジョンもない。仕事は今のまま、今の物量のままやり続けたい。やりたいことを時間的にも精神的にも諦めたくはない。そもそも前妻の久美とは、子供のことが引き金になって関係が悪化し、離婚したわけで。
すごく雑に言うなら、僕はピーターパン・シンドロームです。青年のメンタリティのまま好きなことだけをして、仕事に全振りして生きていきたいと願い続けている。それがOKの相手として、久美はおあつらえ向きだった。
久美のほうも同じく、好きなことだけをして仕事に全振りしたい人間だったので、その関係のままであれば、なんの問題もなかった。久美が「子供が欲しい」と言い出さなければ。

茜は、その経緯を全部了解しているはずでした。なのに、それでも僕と結婚して子供が欲しいと言う。そこで、茜に言いました。
「僕は家事能力がない。なぜなら『生活』に興味がないから。生活をきれいに整えておこうという気持ちがない。だから、家事は言われればやるけど、言われなきゃできない。やるべきことを自発的には気づけない。家というのは僕にとっては『倉庫』であり『巣』でしかないから。だから、世間で言うところの『一家団らん』にも一切興味がない。育児についても、指示されればできる範囲で手伝うけど、父親としての正しい振る舞いはわからない。そもそも、僕は子供がいなくて困ることはひとつもないから、もし妊活してできなくても凹まないでほしい。それでもいいなら、結婚して子供を作ろう」
茜は承諾しました。
人生に負荷をかける
こうして僕は茜と結婚しました。3年前のことで、僕は48歳で再婚、茜は31歳で初婚。そして一昨年、息子が生まれました。もうすぐ2歳になります。
ただ、今でも言いきれます。僕は、積極的に子供が欲しいと思ったことは、今までの人生で一度たりともなかったと。なのに、なぜ茜の要求を承諾したのか。
我慢を重ねていた子供時代を除けば、僕は今までかなり好き勝手な、思いどおりの人生を送ってきました。経験したいことだけを経験し、経験したくないことは徹底的に避けることで、心から楽しく生きてきたという自負があります。変な言い方ですが、人生においてだいたいのことは予想どおりに動いていました。
でも、50に手が届く歳で、この先の人生にもし何かおもしろいことが起こるとしたら、おもしろいことを呼び込めるとしたら、たぶん、僕が「予定外」の行動を取るしかない。自分の人生に対して意識的に「負荷」をかけなければ、本当におもしろいことになんて絶対に起こらない。
「予定外」の「負荷」。僕にとってそれは、今までずっと避けてきた「父親になること」でした。

僕、フラワーカンパニーズってバンドが好きなんですけど、彼らの『地下室』という曲の「斬新な事は いつだって 自分の中にはない」ってフレーズに、すごく共感するんです。
伊集院光の話も心に残っています。彼は40代のとき、これから新しい刺激を受けるには、今まで自分に興味のなかったものをやるしかないと気づき、大嫌いだった自転車に乗り始めたそうです。なるほどな、と。
20代のころの僕は、むしろ負荷をすごく警戒する人間でした。でも、歳を重ねるごとに、気づけば「昔はストレスだったことが、意外とこなせる」ようになってきました。それこそ、アスペルガーの気質があっても技術と知識をもってすれば普通の社会生活を送れるのと同じで。
これを「年の功」だというなら、そうなのでしょう。「人間的成熟」と呼ぶのなら、そうなのでしょう。
このことを、うちの親戚まわりではよく「人間が練れている」という言い方をします。「ばあちゃんくらいの歳になると、人間が練れてるから、いちいち細かいことで腹を立てたりしないんだ」って。
今持ってるものは全部持って階段を上がりたい
過去に稲田さん(注:インタビュアー)が取材した方の中に、40歳を過ぎて今まで熱中できていた趣味に興味がなくなったから、次の取り組み対象として「子供」がちょうど良かったというライターさん(#06)がいましたよね。
彼が加齢によってスキゾ(物事に執着しない)っぽくなったというのはわかります。ただ、僕は明確にそうじゃない。というより、意識的にそうならないように心掛けているんです。
僕、子供ができる前に持っていたものは、全部持ったままで階段を上がりたいんですよ。もともと飽きるのが嫌な性格なので、あらゆることは飽きないようにしたい。常にパラノ(特定の価値観や考え方に固執する)でありたい。そう心掛けているから、いまだに「やりたいこと」が「やりたくなくなって」はいないんです。

だから、今までやってきたこと──取り組んできた趣味とか、仕事に直結するインプットなど──は、子供ができてからもほとんどオミットしていません。
周囲には「お前、ほんとに子供いるのか?」なんて不思議がられますけど、そこは睡眠時間を削ることで帳尻を合わせています。朝は6時起きで子供の支度、寝るのは毎日深夜2時ですから。
文化系男子というか、僕みたいな記者とか編集者なんかに多いと思うんですけど、読書量など「自分に使った時間」が仕事のクオリティに直結するという意識の方って多いじゃないですか。彼らいわく「子供ができて育児に時間が取られると、仕事の質が落ちてつらい」と(#01)。
その考え方はとても理解できます。できますが、僕はそういう発想で考えてはいないんです。子供も興味の範囲内なので、強がりでも痩せ我慢でもなく、子供が仕事の邪魔をしていないんですよ。
もちろん、実際に育児に時間は取られるし、睡眠時間は現実に削られています。ただ僕は、やりたくないことをやらなきゃとか、誰かのためにこの時間を犠牲にしなければ、っていう発想では生きてないし、生きたくない。
そういう意味では、子供という「負荷」が、僕の元々の思想に後づけで都合よく組み込まれただけなのかもしれない。いずれにしろ、結果オーライですが。
妻の幸せのために子供を作った
実は、「父性」がどんなものかということが、いまだにわかってないんですよ。
尊敬できなかった僕の父にあったのは、旧弊な父権でしかなかったので、もしそれが父性なるものなら、父性なんてなくていいやとも思います。僕はそれを嫌悪していたし、自分の中にも少しは残っているという自覚はあるので。
息子の教育に関しては100%、茜に主導権を渡していて、茜の考えにはできるだけ反対しないようにしています。僕が息子の教育に関して何か主張することは一切ありません。
息子がどう育ってほしいかについても、僕自身にはなんの希望もありませんし、就いてほしい職業や行ってほしい学校、習い事などはもちろん、こういうライフイベントが楽しみだ、みたいなことも全然ないです。
興味がないんですよ。息子にとってどの学校がいいとか、どんな習い事をしたらいいとか、どんな塾に行ったらいいかなんて。特に習い事なんて、子供に複数の「逃げ込む場所」を確保する以外のもの以上の存在ではないでしょう。
ある所属コミュニティで居づらくなったときに、身を置ける場所。それはたしかに複数あったほうがいいけど、子供に何かを習得させようなんて、一切考えていません。
誤解してほしくないんですが、息子のことは──自分でも驚くほどに──かわいいと思っています。関心も思い入れもあります。それは揺るぎません。

では、なぜ茜に全権を委任するのか。そもそも、僕は子供がいなくて困ることは当初からひとつもありませんでした。欲しかったのは茜です。だったら、何より彼女が子供を最大限に愛せて、特別だと思い続けられる状況を作ることが一番大事でしょう。
なにより、茜に対する最大級の感謝があります。こんなにも年上のバツイチ男と結婚し、しかも子供を持たせてくれて、僕の人生に予定外におもしろいことを運んできてくれた。こんなにありがたいことはありません。
それに、僕より17歳下の茜のほうが、自分よりはるかに長く息子の人生に寄り添える可能性が高い。であればこそ、僕ではなく、彼女にとって後悔のないような子育てが重要なんです。
乱暴な言い方をするなら、僕は茜の人生が幸せになるために子供を作りました。日々、茜の意見を「どう肯定するか」だけを考えていますよ。

ちなみに、息子の名前も茜がつけました。形式上、僕も案は出しましたが、すごく神経を使って茜の案に誘導したんです。僕の案を通そうなんて、最初から1mmも思ってませんでした。
成熟年齢の遅れ
※以下、聞き手・稲田氏の取材後所感
稀有なケースである。子供を欲しいと思っていない、生活にも一家団らんに興味がない男性が、その信条に一切反することなく、子供を持っているからだ。
なぜ矛盾する対立概念が破綻なく成立しているのか。ひとつは茜さんという、加古川さんにとってこれ以上なく“都合のいい”パートナーの存在だ。加古川さんの提示した、人によっては「不平等条約」とも言える条件を、茜さんは飲んでいる。
もうひとつは、加古川さん持ち前の「思考の跳躍力」だ。子を持ち親になるという、彼の信条からすれば真っ向対立するはずの人生の選択を、ポジティブな意味での「予想外の負荷」と捉えることで、むしろ元々の信条になじませてしまっている。剛腕と言うほかない。
加古川さんはこれを、「年の功」「成熟」「人間が練れた」という言葉で表現した。人として成熟したからこそ、このように思考し、このような決断を下し、このような行動を取れたのだと。
現代人が人間として成熟する速度がどんどん遅くなっている、とはよく言われる。かつては20歳で「大人」だったところ、今や30歳、下手すれば40歳を過ぎてもいまだに「心は少年」「好きなことだけやっていたい」と言う男性は多い。
ピーターパン・シンドロームを自認していた加古川さんもそのひとりだ。彼の成熟は1度目の結婚破綻後、40代後半になってようやく訪れた──という見方もできる。
「昔と比べて寿命が延びたのだから、成熟年齢が遅れたところでなんの問題もない」という意見の妥当性は、実は条件つきだ。現代人がたっぷり時間をかけて精神的成熟を達成し、「結婚」や「親になること」を受け入れられるようになったときには、生殖能力のピークが──特に女性は──とっくに過ぎているからだ。
加古川さんの前妻・久美さんは結婚5年目、40歳のとき、加古川さんに「私の出産可能年齢を考えたことはないの?」と詰め寄った。
なお加古川さんは、茜さんとのお子さんを体外受精で授かっている。
連載「ぼくたち、親になる」書籍化決定!
約1年続いた本連載の書籍化が決定しました。書籍版では、QJWebで掲載した全13回に加え、書き下ろしのボーナストラックも収録予定。詳細は後日発表します。
【連載「ぼくたち、親になる」】
子を持つ男親に、親になったことによる生活・自意識・人生観の変化を匿名で赤裸々に語ってもらう、独白形式のルポルタージュ。どんな語りも遮らず、価値判断を排し、傾聴に徹し、男親たちの言葉にとことん向き合うことでそのメンタリティを掘り下げ、分断の本質を探る。ここで明かされる「ものすごい本音」の数々は、けっして特別で極端な声ではない(かもしれない)。
本連載を通して描きたいこと:この匿名取材の果てには、何が待っているのか?
関連記事
-
-
マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】
『DAIENKAI 2025』:PR -
ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】
『DAIENKAI 2025』:PR