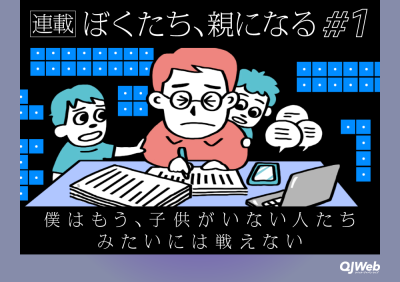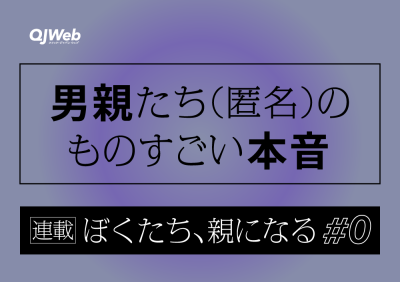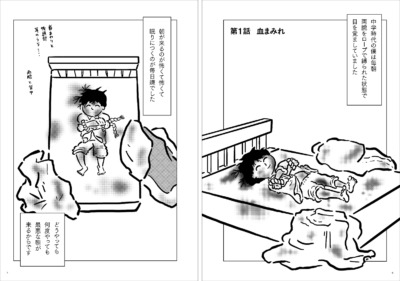妻子と別居した40代男性「ぼくにとって、子育てはハンデだ」仕事で“戦えなくなった”日々のこと【#01前編/ぼくたち、親になる】
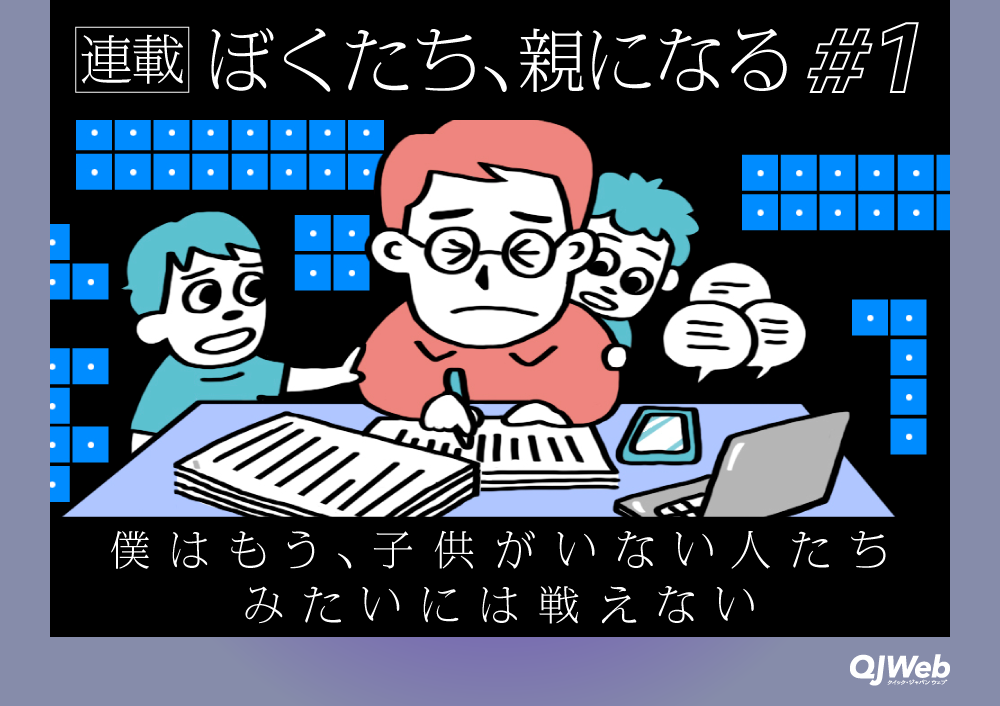
子を持つ男親に、親になったことによる生活・自意識・人生観の変化を、匿名で赤裸々に独白してもらうルポルタージュ連載「ぼくたち、親になる」。聞き手は、離婚男性の匿名インタビュー集『ぼくたちの離婚』(角川新書)の著者であり、自身にも一昨年子供が誕生したという稲田豊史氏。
第1回は、ふたりの子供がいる40代男性の独白。彼が親になったことで感じた、想定外の葛藤とは。
栗田将さん(仮名、43歳)は大手出版社の書籍編集者である。手がけるジャンルはビジネス書から社会学、実用書、エッセイなど幅広い。
普段から世の中にアンテナを張り、社会の関心が高いテーマを見定めると、その執筆に適した著者を探し、依頼して書いてもらう。出版不況と言われて久しいが、今までに10万部を超えるヒット本を何冊も企画してきた。要は、“できる編集者”である。
結婚は2010年、30歳のとき。ふたりの子供を授かった。現在12歳と7歳で、いずれも男の子だ。取材中、栗田さんはパートナーである妻のことを終始「嫁」と呼んでいた。
※以下、栗田さんの語り
目次
編集者になるのが夢だった
高校時代から編集者になるのが夢でした。でも、新卒で出版社に入れたはいいけど、20代のうちはずっと販売営業、つまり書店と取り次ぎ回り。30歳目前で、念願叶って書籍の編集部に異動できました。
ただ、僕は出向社員でした。というのも、僕がその出版社に入社したあとで、僕の所属する営業部門が別会社として分離独立したからです。要するに、早いとこ編集部のある本社に「転籍」しなければ、いずれは販売営業に戻されてしまう。
出向期間は一般的に3年。その3年の間に、僕がやらなければならないことは何か?

考えた結果、自分にふたつのノルマを課しました。ベストセラーを出すこと、そして社内で表彰されることです。このふたつのゴールを達成できれば、誰も「栗田を営業部門に戻そう」なんて言わないはず。
とはいえ、30歳で編集者1年目ということは、新卒ですぐ編集部に配属された奴に比べて7年ものビハインドがあります。スタート地点がずっとうしろ。にもかかわらず、ゴールはほかの人よりずっと先。しかもタイムリミットは3年。やることは山積みです。焦ってはいましたが、燃えてもいました。
嫁は、僕が長らく編集者になりたいことを知っていましたから、異動辞令が出たときには我が事のように喜び、祝福してくれました。ほら、この革の鞄、見てください。嫁がそのときにお祝いとして買ってくれたものです。今でも会社にはこれで出勤しています。
第二子の出産、コロナ禍で状況が変化
実は、編集部に異動直後のタイミングで第一子の男の子が誕生しました。
産前も産後もバタバタでしたが、3歳で幼稚園に入るまでは、嫁が専業主婦として大半の育児をやってくれたので、僕は仕事に打ち込めました。
編集の仕事を見様見真似で覚えながら、書店の棚を観察し、売れている本を買い漁っては読み込み、昼も夜もなく企画を考え、たくさんの著者候補と会い、熱弁し、執筆を依頼しました。
SNSでの発信、メディアへの仕掛け、トークイベントなど、売るための方法は片っ端から試しましたね。そのいくつかでは明らかな手応えを得られました。
その甲斐あって、10万部以上のベストセラーを比較的早い時期に何冊か手がけることができ、会社から表彰もされました。ゴールを達成できたんです。編集者になって3年目、晴れて本社に転籍が叶いました。
その2年後、僕が36歳のとき、第二子が誕生しました。ふたり目の男の子です。上の息子とは違い、嫁の希望で1歳から保育園に預け、彼女は栄養士の仕事に復帰しました。
下の息子が4歳になるころ、つまり今から3年前、状況が変わってきました。新型コロナ感染拡大で、僕が自宅でのテレワーク中心になったとたん、編集者にとって最も大切である「没入する時間」が取れなくなったんです。
仕事の質を担保する「没入」が、できなくなった
嫁は毎日、電車に乗って勤務先に出勤します。一方の僕は、会社の方針で週に4日は自宅でテレワーク。なので、僕が下の息子の保育園への送り迎えを担当することになりました。
それはいいとして、困ったのは嫁が勤務先からLINEで僕に、頻繁に家事の指示を飛ばしてくることでした。お昼にスーパーに行ってこれとこれとを買っといてほしい、15時になったから洗濯物を取り込んでたたんでおいてくれ、といったような。
でも、こっちは一日にいくつものオンライン会議があるし、その合間にゲラを読んだり、企画書を書いたりもしています。それがぶつ切りになることによって、まとまって何かに没入できる時間がほぼなくなりました。これが、ものすごくつらいんです。

こういう話をすると、洗濯物を取り込んでたたむなんて15分もかからないんだから、大して仕事を侵食してないだろう、会議や作業はその前後にスケジュールしとけばいいじゃないか、っていう人がいるじゃないですか。全然、わかってませんよね。嫁もわかっていませんでした。
インプットにしろ思考にしろ、没入状態というのは一度途切れると、すぐには元の「場所」に戻れません。この仕事は没入が本当に大事なんです。本の企画や売り方を考えるにしろ、原稿を精読するにしろ、没入が仕事の質を担保します。
没入というのは、ひとつづきのまとまった時間が確保できなければできません。細切れの15分、30分が一日のうちに何回あったところで、意味がないんです。
2時間なり3時間なり、途切れなく思考しつづける、没入することによって、初めて到達できるものがある。得られるひらめきがある。実際、僕はそうやっていい企画を立ててきました。
編集者にとって子育ては「ハンデ」
嫁はそういうタイプの仕事をしたことがないから、いくら説明しても理解してくれませんでした。「家にいるから、それくらいできるでしょ」を繰り返すだけ。
でも、洗濯物を取り込む時間自体は15分でも、元の没入度を取り戻すには、それこそ30分も1時間もかかる。
たとえば、15時に洗濯物を取り込んで、手早くたたんで15時15分。16時40分には保育園のお迎えに出なければいけない。こんな細切れの時間で没入することなんてできません。
子供を連れて帰宅したら、もちろんほっとくわけにいかないので、ずっと相手をしています。大量に届くSlackへの簡単なレス程度はできますが、嫁が18時半に帰ってきて一緒に夕食を取って風呂に入るまでは、仕事は完全に中断します。
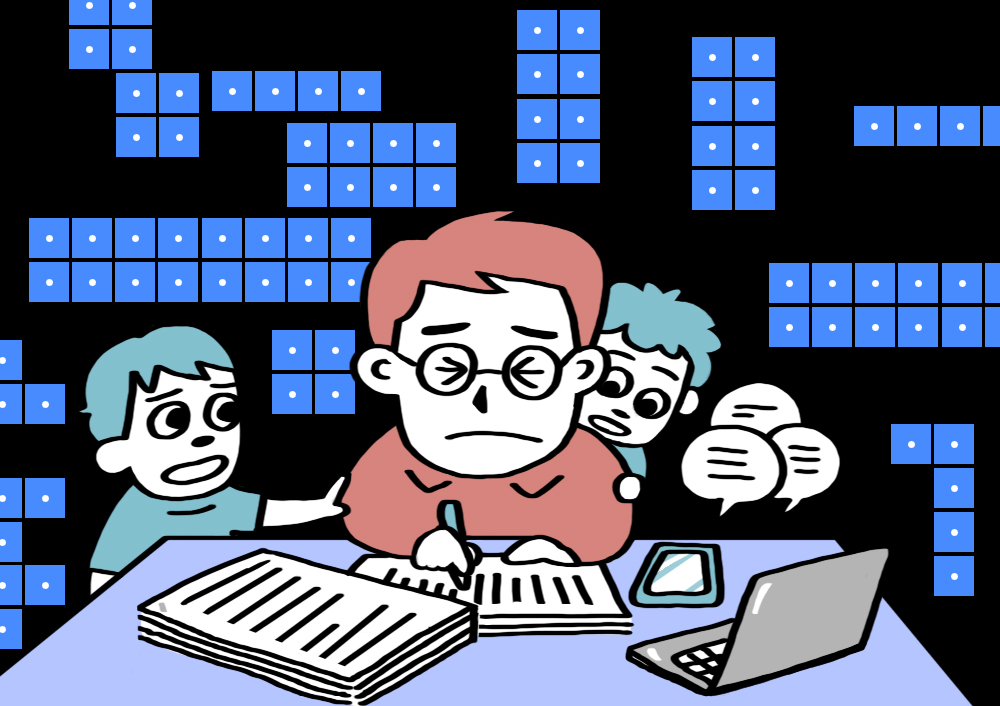
嫁に育児のほとんどを任せていたときと違い、嫁が働きに出て育児を半々でシェアするようになって、僕は没入する時間をほぼ完全に奪われました。
共働き夫婦が子供を育てるとはこういうことだ、というのは百も承知です。どんな夫婦だってそうしているでしょう。
だけど、気づいたんですよ。共働きで子供を持つというのは、編集者にとってはすごいハンデなんだ、と。
準備ができないから、戦えない
書籍編集者の仕事の中でも特に大事なのは、インプットです。仕事と直接関係がなくても、これはと思う本やマンガや映画は、常日頃から浴びるように読んだり観たりしておかなければなりません。
情報源としてのネットニュースやツイッターなどのSNSは隙間時間にスマホでもチェックできますが、ちゃんとした「作品」に没頭することを怠れば編集者としては“終わる”んです。
日々良質な作品に触れ、感性を刺激し、脳を回しつづけなければ、編集者としての感覚は鈍り、腕も落ちる。発想力も企画力も編集力も、すべて錆びついてきます。同業者の方なら、わかっていただけるんじゃないでしょうか。
ところが、子供ができて育児にコミットすると、没入する時間が取れないから、2時間集中して映画を観るとか、マンガを一気読みするとか、難しい本を集中して読むみたいなことが一切できなくなります。
まず、連続ドラマは観ないし、観られない。長い小説や、巻数ものの本は無理。本来、いい書き手を探すための読書は編集者の生命線ともいえるものですが、そこに思ったように時間が取れない。
書き手さんにアプローチする際には、せめて主要作は全部読んでおきたいけど、それができなくなる。これが本当につらいんです。土日は平日以上にそれができません。週末、家に小さな子がふたりいる状態で、自室にこもってじっくり本を読むとか映画を観るなんて、できるわけがない。

僕は没頭に人一倍時間をかけることで、7年分のハンデを埋めました。人よりうんとたくさんの本を読み、作品に触れ、人と会い、思考し、思考し、思考し……それで勝ち取ったベストセラーです。運もあったでしょうが、やはり積み重ねた膨大な「準備」がものを言いました。
でも、下の息子が生まれて嫁が仕事に復帰し、相応の家事を僕も分担することになると、そんなことはもう絶対にできないと悟りました。ああ、こりゃ駄目だ。満足に準備ができない。だから戦えないなって。
文化系は個人戦。「インプットの時間」が減ると不利になる
部下とか会社の若い奴なんかを見ていて、つくづく思ったんですよ。もう自分は、彼らほど何かに没入する時間を確保することができないんだと。つまり僕はもう、子供がいない人たちみたいには戦えない。
この点は、フリーランスで文筆業をやられている稲田さん(注:インタビュアー)にも聞きたいんですよ。編集者がクリエイターだとはいいませんが、それに近い職業、作品を生み出すタイプの職業って、仕事に生き方が直接反映されるじゃないですか。
プライベートと仕事に本質的なオン・オフがない。日々の生活の中で誰かと話すこと、観ること、読むこと、すべてが作品づくりに直結していますよね。
それが子育てで途切れてしまう。この恐怖感。むしろ稲田さんのほうが、その切迫感は強いんじゃないですか? インプットの時間が思うように取れないのは、文筆業という商売上、すごく不利になりませんか?

僕は自分のことを、いわゆる“文化系男子”だと自認していますが、結局のところ文化系って、ずっと「個人戦」をやってきたんですよ。チーム戦じゃなくて。
文化系という人種は今までの人生、基本的にひとりでコンテンツをこつこつと摂取してきたじゃないですか。極論すれば、自分の人生の時間をどれだけコンテンツに捧げてきたかによって、今の自分の地位がある。
僕は会社員なので組織の一員ですが、書籍編集者の業務は完全に個人戦です。戦いそのものが個人なのはもちろん、戦うための準備も個人でやる。孤独に粛々と、本を読み、人と会い、考え、動く。ずっとひとり。
チームの仕事なら、不足分をほかの人にカバーしてもらえますが、個人戦だとそうはいきません。
出版社社員の離婚率が高いことに納得
だから、文化系と呼ばれる人たちから「子育てとは」と問われれば、インプットやアウトプットの質や量が下がるという意味においてはやっぱりハンデだし、「リスクだ」と答えるしかありません。仕事上のメリットはあまりない、と言わざるを得ない。
子供がいて、育児にもちゃんとコミットしていて、でも文化系としてインプットもちゃんとできていて、個人戦をガンガンやってる人なんているでしょうか? 僕は20年以上の会社人生の中で、そんな人は見たことがありません。
有り体にいえば、仕事か家庭のどちらかを犠牲にするしかないんです。出版社社員の離婚率が高いのも納得がいきます。まじめに仕事をすればするほど離婚に近づくんですから。
実は僕も、2年前から妻子と別居しています。
記事後編:別居した妻が夫に求めていたものは?
【連載「ぼくたち、親になる」】
子を持つ男親に、親になったことによる生活・自意識・人生観の変化を匿名で赤裸々に語ってもらう、独白形式のルポルタージュ。どんな語りも遮らず、価値判断を排し、傾聴に徹し、男親たちの言葉にとことん向き合うことでそのメンタリティを掘り下げ、分断の本質を探る。ここで明かされる「ものすごい本音」の数々は、けっして特別で極端な声ではない(かもしれない)。
▼本連載を通して描きたいこと:この匿名取材の果てには、何が待っているのか?
関連記事
-
-
マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】
『DAIENKAI 2025』:PR -
ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】
『DAIENKAI 2025』:PR