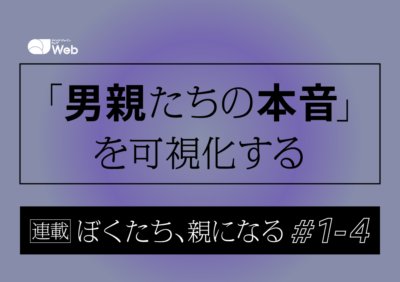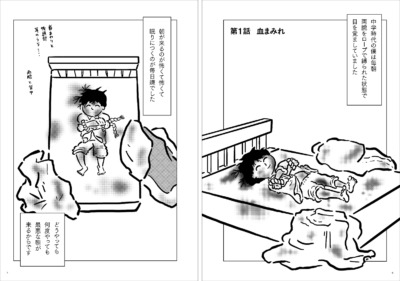子を持つ男親に、親になったことによる生活・自意識・人生観の変化を、匿名で赤裸々に独白してもらうルポルタージュ連載「ぼくたち、親になる」。聞き手は、離婚男性の匿名インタビュー集『ぼくたちの離婚』(角川新書)の著者であり、自身にも2歳の子供がいる稲田豊史氏。
第13回は、新聞記者の50代男性。再婚した現妻との間に子供を授かったが、長年「子供はいらない」と強く思っていたという。
加古川学さん(仮名、51歳)は新聞社の文化部記者。3年前に再婚した妻・茜さん(仮名、34歳)との間に、間もなく2歳になる男の子がいる。
ただ、加古川さんは長い間、かなり強く「子供はいらない」という考えだった。実際、10年以上も夫婦生活を共にした前妻とは、「子供は作らない」という前提で籍を入れた経緯がある。加古川さんの人生はいつ、どのようにして大きく方向転換したのか。
※以下、加古川さんの語り
目次
「父親」のロールモデルがない
もともと、かなり自覚的に「子供はいらない」と思っている人間でした。自分の中に「父親」のロールモデルがなかったからです。もっと言うと、「大人の男」がどういうものであるかという認識ができないまま、大人になりました。
それは、明らかに父のせいです。
僕は母の背中を見て育ちました。母は結婚しても仕事を辞めず、今でも小さな会社を経営しています。面倒見が良く、親分肌で、仕事もできる。尊敬できる人です。
一方の父は、昔からまったく尊敬できませんでした。団塊世代の地方公務員。いつも自分が正しいと思っていて、よく母に議論をふっかける。人の話を聞かない。子供は一切褒めない。僕と弟の出来を比べる。
何よりたちが悪かったのは、「自分は同世代と比べて、考え方が進歩的である」という優越的な意識が露骨だったことです。
父はその世代には珍しく、結婚したら仕事を辞めろと母には言わなかったし、子供たちには「自立的であれ」と繰り返していました。でも僕に言わせれば、同時代なりの古い考え方の人よりも、「自分は進歩的である」という意識の人のほうが、その頑迷さが見るに堪えない。哀れですらある。その典型が父でした。
だから、全然好きじゃなかったんですよ。父のこと。

ただ悲しいことに、僕は小さいころから、父に嫌なくらい似ているとも感じていました。要は同族嫌悪です。
だから僕、10代のころには「自分は絶対に子供を持ちたくないし、できれば結婚もしたくない」と思っていました。子供なんて持ってしまえば、自分もきっと父みたいになる。あんな父親になるのは絶対に嫌だと心に誓っていました。
世の中には、「自分の親みたいにはならないぞ」と決意して、果敢に家庭を作られる方もいますが、僕にその自信はなかったです。血には抗えないと諦めていたので。
「子供時代」を追体験したくない
子供はいらないと思っていた理由は、もうひとつあります。僕自身、子供時代がそれほど楽しくなかったんです。
微笑ましいエピソードや、良い思い出と呼べるものはたしかにありますよ。ただ、総じて感情としては愉快ではなかった。不自由で、しんどかった。
学校がとにかく嫌でした。いじめられていたわけではないけど、団体行動を要求されるのがとにかく不快で、なんて理不尽なんだろうという気持ちがずっと頭から離れなかったんです。

自分が親になれば当然、自分の子供がたどる「子供時代」について、もう一度ひと通り考え直すことになりますよね。幼稚園のこと、小学校の行事のこと、受験のこと。そんなの、二度と考えたくない。思考に上らせたくない。ヘドが出ます。
社会における子供という存在が嫌いだとか、憎んでいるとか、そういうことではありません。子供時代や子供社会のことに「思いを巡らせる」のが嫌なんです。だから、学校の先生になりたい人の気持ちが、今でもまったく理解できません。
それほどまでに、僕の子供時代は嫌な記憶で覆われています。それを我慢して大人になったので、二度と触れたくない。子供を持つことで、再び「子供時代」を追体験するのは絶対に御免だと思っていました。
妻が変心する
だから、僕が35歳のときに結婚した最初の妻・久美(仮名、当時35歳)とは、子供を作らないのはもちろん、当初は結婚すらしない予定でした。お互い30歳くらいのころから籍を入れずに同棲していたんです。
久美は“とある文化人”で、交際当初から収入は僕より上でした。彼女も僕と同じく子供はいらない派で、しかも経済的には完全に自立していましたから、僕以上になおさら結婚する理由がありませんでした。

ところが、同棲を始めて5年ほど経ったころ、結婚するきっかけが訪れました。家の購入です。
共同名義でローンを組むとなると、籍を入れていたほうがややこしくない。彼女のほうは依然として結婚にはうしろ向きでしたが、僕としては結婚していたほうが親にも会社にも説明がしやすいし、年齢的にもいいころだし……ということで納得してもらい、結婚しました。
とはいえ「子供は持たない」という意見は一致していました。ふたりとも変わらず、積極的に子供がいらなかった。
ところが結婚5年目、僕と久美が40歳を迎えるころ、久美が突然言い出しました。
「私の出産可能年齢を考えたことはないの?」
「欲しい」のは自分ではないのに…
驚きました。子供を作らないことをお互い納得して結婚したはずなのに、話が違う。でも、それを永遠の「取り決め」だと思っていたのは僕だけで、久美の中では単に「そのときの気分」だったのでしょう。
のちに周囲の話を聞いたり本を読んだりして学びましたが、ある約束事を「男はルールだと思うけど、女はルールだとは思わない」の典型です。
ルールじゃないなら何か。久美と話してわかったのは、僕が子供を欲しいと言い出さないことが、僕が久美に対して興味を失っているように見えるらしいということでした。実際に興味は失っていなかったのですが、問題は「事実、久美にはそう見えている」ことなので、これは難しいぞと。
打開するには僕が折れて、子供を作るしかない。ところが、じゃあ子供を作ろうかと持ちかけてみると、今度は抵抗するんです。「どうせあなたは子育てに協力しない」「あなたが信用できない」
極め付きは、「私は仕事を休業する気はない。もし子供ができたら、あなたが仕事を休業して全面的に育児をして」という久美の言葉です。

久美は“とある文化人”なので、会社勤めではありません。しかも“売れっ子”でした。休業すればその分収入は減るし、活動も滞る。休業によるキャリアダメージは、サラリーマンの僕よりもずっと大きい。その点はもちろん理解していました。
だけど、僕はそもそも子供が欲しいと思っていません。いらないけど、久美が心変わりして「欲しい」と言い出したから歩み寄っている。なのに「私は休業しない、あなたが休業しろ」という主張は、どうしても受け入れられませんでした。
妻に「アスペルガー症候群」を疑われる
その一件があってから、夫婦関係は急速に悪化しました。結婚生活はトータル10年以上続きましたが、後半の5年は大学病院の夫婦関係外来に通い詰め。少なくとも僕は離婚する気がなかったので、なんとか関係を修復できないかと望みを託していたんです。
あるときから、久美は僕に対して「アスペルガー(症候群)なんじゃないの?」と口にするようになりました。アスペルガー症候群は、読みかじった僕の理解(※)では「発達障がいのひとつで、自閉症スペクトラムに含まれる。対人関係が苦手、興味や行動に偏りがあり、コミュニケーション能力や社会性に問題がある」ですが、彼女いわく「あなたは人の気持ちがわからない」と。
僕にそういう気質がないとは言いきれません。昔から興味の対象はものすごく偏っていたし、集団行動は苦手。あることに熱中したら、納得いくまでやり尽くさないと気が済まない。興味のないことは絶対にやりたくない。
ただ、自閉症にしろアスペルガーにしろ、あくまでスペクトラム(連続体)です。「障がいか、そうでないか」ではなく、どれくらいその傾向があるかの程度によって測られる症状の度合いでしかない。
結局、久美の求めに応じて有給休暇を取り、自閉症スペクトラムの検査を受けました。結果は、記憶力が異常に良く、それ以外の能力との有意差があるものの、医師の所見は「病名をつけるほどの程度ではない」。基本的には「異常なし」だと、僕は理解しました(※)。
ところが、久美は「有意差がある」の部分に反応してしまい、「やっぱりあなたが異常だった」の一点張り。結局、それが引き金になって関係は悪化の一途をたどり、別居期間を挟んで離婚しました。

離婚が最終確定した直後、夫婦関係外来の予約がまだ残っていました。行かなくてもよかったのですが、せっかくなので先生に「今日で最後にします」と告げるべく病院に赴きましたが、久美はドタキャン。
仕方がないのでひとりで診察室に入り、良い機会だと思ったので、自分たち夫婦がどう見えていたかを先生に聞いてみたところ、こう言われました。
「ご主人は一貫してなんの問題もありません。ただ、奥様は人一倍、いろいろと察してほしい方ですね」
久美の望む水準で察せなかった、という意味では、たしかに久美にとって僕は、紛れもない「アスペルガー症候群の人」だったのでしょう。
※※アスペルガー症候群や自閉症スペクトラムに関する記述は、あくまで加古川氏の理解によるものです
憧れは椎名誠や筑紫哲也
ただ、仮に久美と折り合いがついて子供を作っていたとしても、うまくはいかなかったでしょう。僕の中に父親のロールモデルがない、「どういう父親になりたいか」のビジョンが一切ないんですから。
僕が若いころから憧れていた年上の男性って、椎名誠とか筑紫哲也とか目黒考二といった、いわゆる家庭を顧みない人たちでした。家庭には週末にしか帰らない。家庭の匂いなんてもちろんしない。そんな人たちです。
今となっては、それが旧時代的に過ぎること、社会的にNGであることは、もちろんわかっています。ただ、若いころからの憧れは拭い去りようがありません。僕は彼らをかっこいいと思って作家やジャーナリストや文芸評論家に憧れ、そういった文章を読み漁っていましたから。

だから、久美と離婚に至らなかったとしても、ずっと憧れていた「年上の男性」を僕がどこかで目指し続ける以上、いずれ久美は──つまり女性は──必ず「ないがしろ」にされる。子供がいるにしろいないにしろ、すなわち僕が父親であるにしろ夫であるにしろ、久美と夫婦関係を保ち続けるのは難しかったでしょうね。
結局、八方塞がってたんです。離婚は必然でした。
「子供が欲しいから結婚したい」
今の妻である茜は17歳年下で、彼女が大学生のときに知り合いました。彼女が新聞研究系のサークルに所属していて、その勉強会に現役記者の僕が呼ばれたんです。ただ、長らくは交流会で時々話す程度の仲でした。
久美と別居を始めたころから、茜と交際を始めましたが、僕に結婚する気はまったくなかったし、はっきりそう伝えていました。
もはや自分が、一般的な意味における結婚に向いていないことは痛いほどわかっていましたし、「家庭を顧みない男」への憧れが続いている以上、茜も「ないがしろ」にされることは目に見えている。だいたい、年の差がありすぎます。
僕のそういう考え方や久美と破綻した経緯は茜にすべて話し、その上で「交際はいいけど結婚は期待しないでほしい」と伝えていました。相当に薄情な男です。僕は。

ところが、久美との離婚が成立しそうだという話をしたら、茜は「じゃあ結婚してくれるの?」と言ってきました。驚きです。「今までの僕の話、聞いてた? なんで?」。そう問うと、さらに驚きの言葉が返ってきました。
「子供が欲しいの。でも、あなたは興味ないかな?」
後編は8月25日(日)夜、公開予定
【連載「ぼくたち、親になる」】
子を持つ男親に、親になったことによる生活・自意識・人生観の変化を匿名で赤裸々に語ってもらう、独白形式のルポルタージュ。どんな語りも遮らず、価値判断を排し、傾聴に徹し、男親たちの言葉にとことん向き合うことでそのメンタリティを掘り下げ、分断の本質を探る。ここで明かされる「ものすごい本音」の数々は、けっして特別で極端な声ではない(かもしれない)。
本連載を通して描きたいこと:この匿名取材の果てには、何が待っているのか?
関連記事
-
-
マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】
『DAIENKAI 2025』:PR -
ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】
『DAIENKAI 2025』:PR