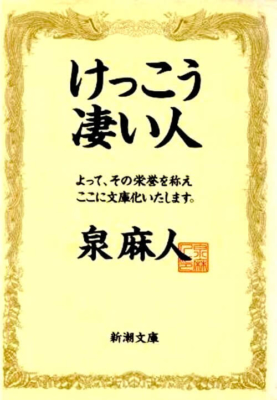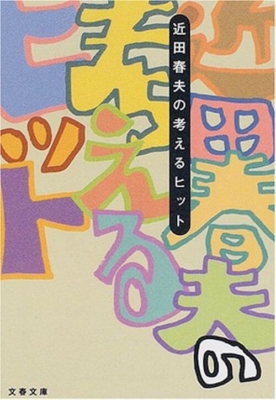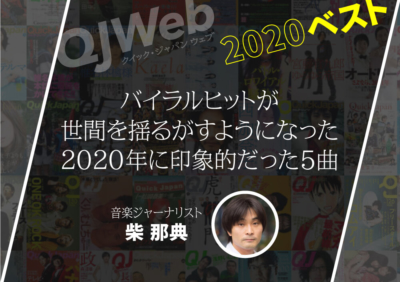アイドルとは歌うヒトではなく歌わされるヒト
近田の批評はまた、極めて公正でもある。AKB48の選抜総選挙が話題になっていた2011年には、《“子供キャバクラの政局ごっこ”に日本国中いい大人までがうつつを抜かしている》と現象に対しては眉をひそめつつも、いざ楽曲(「フライングゲット」)に向き合えば、《ラテンディスコっぽい曲調はとても聴きやすい作りで王道的、といいつつコードにしろ仕掛けにしろ決して安易な予定調和には陥っていない。なんともスムーズな流れの中にもきらびやかな飾りを刺激的にちりばめた、仕事の密度を感じさせるサウンドプロダクションに、思わず聴き入ってしまった》と評価してみせた(『考えるヒットe-1 J-POPもガラパゴス』)。
アイドルについて、近田は連載初期にTOKIOとV6を取り上げた回で、《どんなに時代が変わろうが、アイドルとは歌うヒトではなく歌わされるヒトなのだ。歌い手、といわず歌わされ手、と彼らのことは呼ぶべきだ》と書いていたことがある(『近田春夫の考えるヒット』文春文庫)。まあ、これぐらいはわりと誰でも書きそうだが、これにつづけて、次のようにはなかなか書けまい。
だから、アイドル当人には楽曲に関する責任は一切ない。じゃ彼等の責任範囲はどこまでなのか、というと性的魅力の発揮、そこのみだと私は思う。ムロン、そのなかに「歌いっぷり」は入る。アイドル歌謡を完結させる一番の要素といってもいい。雑ないいかたをすれば、アイドルとオペラ歌手は同じことを競っているわけである。(中略)とにかく、アイドルを評価する場合、楽曲に言及するのは的はずれだと私はいいたい。三大テノールだのマリア・カラスだのの歌について語る時、作曲家の能力に触れるヒトはいないのと同じ話である。
『近田春夫の考えるヒット』文春文庫
ポピュラーミュージックは、楽曲、アレンジ、歌詞だけでなく、歌唱や演奏の技術、歌い手の個性、さらには作品を世に送り出すためのシステムや背景となる時代状況など、さまざまな要素で成り立っている。すべてが作詞・作曲家やプロデューサーの思いどおりにいくわけではなく、誰が歌うかによって作品の聴こえ方が変わってしまうということも往々にしてある。
だからこそ論じるには、ひとつの曲も総合的に捉えながら、各要素を整理する必要があるはずだが、それができている書き手は少ない。アイドルについて評価するときも、プロデューサーの能力や責任もごっちゃにしてしまう人のなんと多いことか。それだけに近田の仕事はよけいに際立つ(それにしても、アイドルとオペラ歌手を同列に置いてしまったのはすごい)。
先入観に捉われず、作品と向き合った上で公正に判断を下す。アイドルをアーティストの下に見たりしないし、大御所にだって容赦はしない。それができたのは、近田が常に非主流派、アウトサイダー的ともいうべき立場にいたからでもあるのだろう。
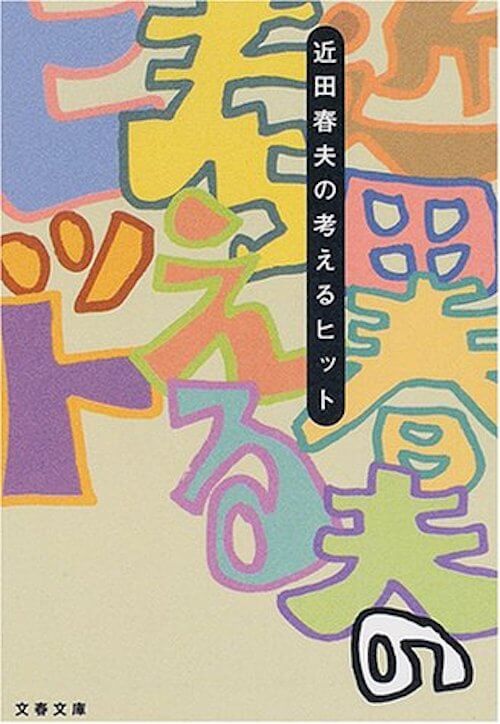
まさかこれほどの長寿企画に成長するとは
70年代後半には、テレビドラマ『ムー』『ムー一族』に出演するなど、芸能界でも活躍したが、やがて一線から退いている。同時期には雑誌やラジオで歌謡曲論を展開し、のちに物書きとなるような青少年に影響を与えた。しかし、これも80年代に入ってしばらくするといったん休止してしまう。
1985年にコラムニストの泉麻人の取材を受けた際には、《本筋、っていうのが嫌いみたいねオレは。(中略)最近の傾向としては、こういった世界の人みんながマルチ人間化しちゃったでしょ、文章書いたり、唄うたったり……。そうなってくるともう嫌なわけ、だからいまオレ、異常に音楽一本にのめり込んでる。常に本筋とはずれたことしたい、ってのはあるね》と語っていた(泉麻人『けっこう凄い人』新潮文庫)。
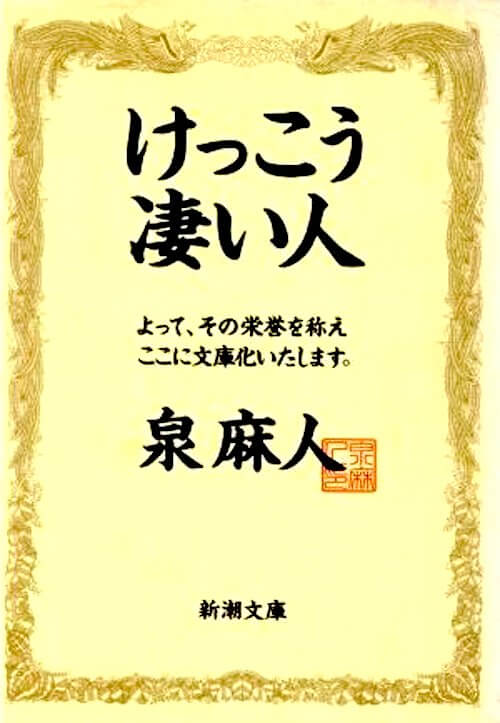
ミュージシャンとしても彼はパイオニアであった。70年代末には、郷ひろみや森進一などの曲をカバーした歌謡曲論の実践盤ともいうべきアルバム『電撃的東京』を近田春夫&ハルヲフォン名義でリリースして、一部で注目された。その後も80年代から90年代にかけては、プレジデントBPMやビブラストーンといったユニットを組んで、いち早く日本語によるラップミュージックに挑戦し、玄人筋からの評価を得た。
だが、根っからの飽き性である彼は、数年も経つと、さっさとやめてしまう。《その理由は、ひとたびそのジャンルの音楽の構造が分析できてしまうと、その時点ですっかり興味が失せてしまうからだ》と、「考えるヒット」を企画した同連載の初代担当編集者・井上孝之は説明する(『考えるヒット テーマはジャニーズ』「解説」)。
そんな近田に、当時まだ20代だった井上が「考えるヒット」の企画を持ち込んだのは1996年。ちょうど小室哲哉プロデュースの楽曲が相次いでメガヒットになるなど、日本の音楽市場が絶頂にあったころだ。CDの売り上げは連載が始まって2年目の1998年をピークとして、以後、凋落の一途を辿ることになる。「考えるヒット」はそうした状況のなか、四半世紀近くにわたって書きつづけられた。この仕事を依頼した井上からして、まさかこれほどの長寿企画に成長するとは予想外であったという(前掲)。
ちなみに、「考えるヒット」の始まった当初、近田は原稿を手書きしていたという。それがのちにはiPhoneの音声入力で執筆するまでになったとか。前出の泉麻人は、テレビ雑誌の編集者だった80年代初めに近田に原稿を依頼したとき、彼から《しゃべるのと同じスピードで書けないとキモチ悪いんだよね》と言われたのが印象に残ったと記している(『けっこう凄い人』)。そんな近田にとって音声入力はまさに福音であっただろう。この点で時代はようやく彼に追いついたといえる。
最近になって、関ジャニ∞のメンバーがミュージシャンや評論家を招いてヒット曲を分析する『関ジャム 完全燃SHOW』(テレビ朝日)のような番組が注目されるなど、近田の仕事はここへ来て継承され、一般にも受け入れられつつある印象を受ける。しかし、だからといって彼の役割が終わったとは言いたくない。むしろ、サブスクリプションサービスによって、古今東西の音楽がより自由に聴けるようになった今だからこそ、近田の仕事は価値判断の指標となるものとしてますます重要になってくるはずである。連載は終わるが、今後も別のかたちであれ、批評家・近田春夫の活躍に期待したい。
関連記事
-
-
ケビンス×そいつどいつが考える「チョキピース」の最適ツッコミ? 東京はお笑いの全部の要素が混ざる
よしもと漫才劇場:PR -
「VTuberのママになりたい」現代美術家兼イラストレーターの廣瀬祥子が目指すアートの外に開かれた表現
廣瀬祥子(現代美術家)/ひろせ(イラストレーター):PR -
パンプキンポテトフライが初の冠ロケ番組で警察からの逃避行!?谷「AVみたいな設定やん」【『容疑者☆パンプキンポテトフライ』収録密着レポート】
『容疑者☆パンプキンポテトフライ』:PR -
『FNS歌謡祭』で示した“ライブアイドル”としての証明。実力の限界へ挑み続けた先にある、Devil ANTHEM.の現在地
Devil ANTHEM.:PR