いかに戦争を位置づけるか
そして実は、この一連のシーンで一番重要なのは、すずの“見えないところ”で太極旗が立つ様子が描かれている点にある。
原作では、すずのいる畑と太極旗が立つバラックの位置関係はさほど明確ではないが、紙面のすずの顔の向きとは逆方向に、太極旗が描かれる。アニメ映画ではより具体的に、すずが毎日見下ろしてきた灰ヶ峰の斜面の一画に太極旗が掲げられる。しかしこちらも、すずは山側を向いており、海側を見ることはない。
原作もアニメ映画も、すずはこの太極旗を目にしていない。彼女の加害の自覚は、太極旗を見たからではなく、彼女自身の内面の変化として描かれているのだ。つまり、この太極旗とすずの振る舞いを、同時に見ることができるのは、現代の読者・観客しかいないのである。このとき読者・観客は、すずの中に生まれた漠然とした加害の自覚が、アジア・太平洋戦争における日本のアジア侵略と結びついていることを具体的に意識することになる。
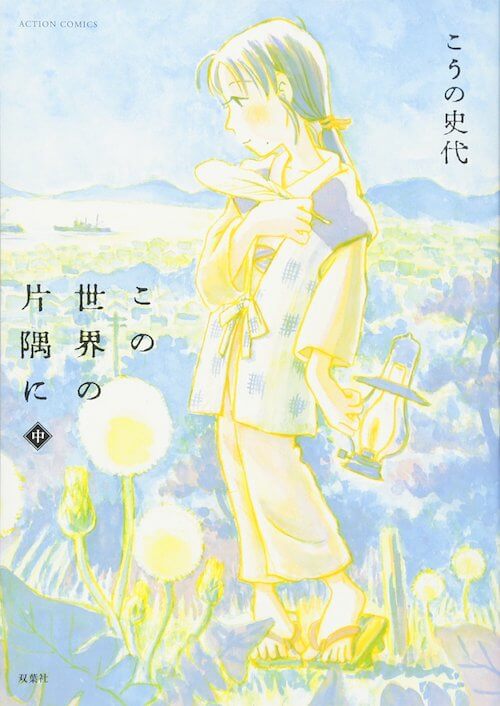
アジア・太平洋戦争になぜ敗けたのか。そこにどのような加害の側面があったか。当時の日本人はそれをすぐ認識できたわけではない。それはGHQにおける占領期を経て1955年に55年体制が定まるまでのおよそ10年間の間に、(ある種の偏りを内包しつつ)徐々に形成されていったのである。
だからすずの「自覚」は、その変化を象徴的に描いた極めてフィクショナルなものということができる。だがこの「自覚」が作中に示されないと、すずの人生における戦争の意味を描いたことにはならない。「当時を生きる人の生の声」を尊重しつつ、当時の価値観から距離を取っていかに戦争を位置づけるか、という難問に対する本作の回答が、8月15日の描写に集約されているのである。
もちろんこれは『この世界の片隅に』の戦略であり、すべてにあてはまる正解ではない。たとえば、もっとキャラクターを突き放して描くタイプの作家なら、また別のアプローチもあるだろう。
だがいずれにせよ『ひろしまタイムライン』にはこうした発想は(今までのところ)まったくない。
歴史研究者の成田龍一は、『「戦争経験」の戦後史』(岩波書店)の中で、戦争体験の語られ方をその時期に合わせて、次のように分類している。
戦時下である「状況の時代」(1931年〜1945年)、戦争体験を持つもの同士が語り合う「体験の時代」(1945年〜1965年)、戦争体験があるものがないものに語る「証言の時代」(1965年〜1990年)、複数の多角的な証言が集団としての記憶を構成する「記憶の時代」(1990年〜)という4つである。
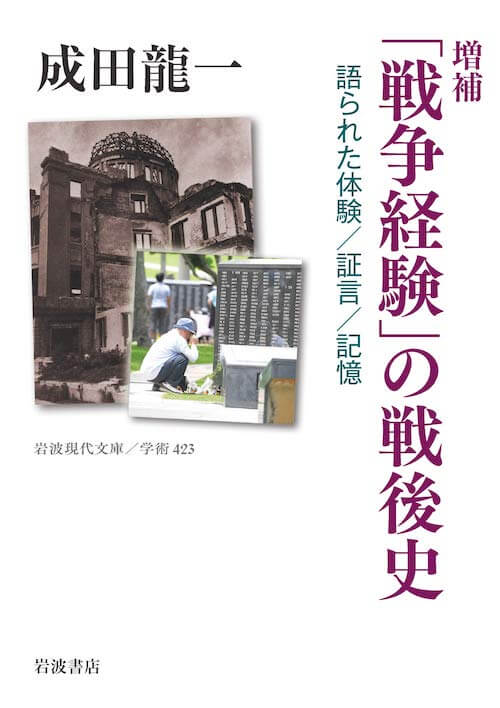
これにならうと『ひろしまタイムライン』のやり方は「証言の時代」のものであり、その結果として個人体験に基づく「証言」の特権化の傾向が強いことがわかる。現在求められているのは、その先にある、複数の「証言」を検討して大きな「記憶」の一部に位置づけていく「記憶の時代」の振る舞いではないか。『ひろしまタイムライン』には、そうした「記憶の時代」の視点が欠けている。それが具体的には「現代の読者・観客の視点」の欠如という形で現れたのだ。
逆に言うと『この世界の片隅に』は、「現代の読者・観客の視点」を意識したことで「証言の時代」とは一線を画した、「記憶の時代」の「戦争もの」として成立したのである。その点で『この世界の片隅に』のアプローチは今後、アジア・太平洋戦争をフィクションで取り扱うときにとても示唆に富んだものといえる。

関連記事
-
-
4年目の今、重荷だった「王子様」を堂々と名乗れる。Last Princeが語る、プリンスを背負う勇気と楽しさ
Last Prince:PR







































