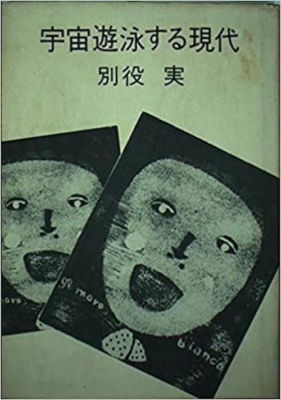言葉を剥ぎ取る、別役の「ドラマツルギー」
関係性というのは、別役実のあらゆる仕事を考える上でのキーワードかもしれない。たとえば、1960年代以降の演劇で常套手段として用いられてきたドラマツルギー(作劇術)を、彼は「リンゴのドラマツルギー」と名づけてこんなふうに説明していた。
……舞台中央にテーブルがあり、その上にリンゴがひとつ置かれている。そこへ男がひとり現れ、リンゴを指して「これはリンゴです」と言う。以後、男は繰り返し舞台に現れ、そのたびにリンゴに向かって「これはリンゴかな?」「もしかしたらこれはリンゴかもしれない」「まさか、これはリンゴじゃないだろうな」とセリフを言い換えていく。そして最後には「なるほど、これがリンゴか」と言って舞台を降りる……。
演じ手たる男は、最初に「これはリンゴです」と言ったあと、舞台に登場するたび徐々にリンゴというものに対し疑いを深めていく。それに合わせて観客も不安を覚えると同時に、リンゴを自分自身の目で改めて確認しようと見つめ直すだろう。ここで初めてリンゴは演劇的な「物」となるのだ。そうなればあとは、男がもう一度現れて「なるほど、これがリンゴか」と言いさえすれば、《観客は、ほとんど宇宙人がはじめてリンゴを見るように、それがそこに「在る」ことに感動することが出来るのである。つまり、リンゴがリンゴであることに感動することが出来るのである》と、別役は書く(『宇宙遊泳する現代』)。
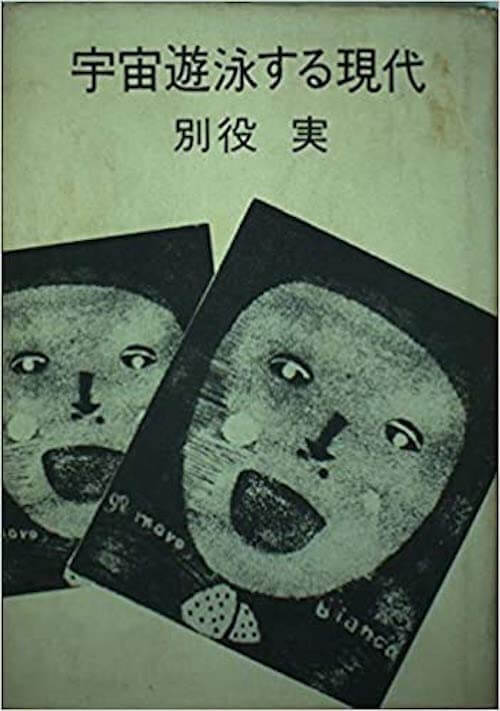
別役曰く、この男の作業は、リンゴから「リンゴ」という言葉を剥ぎ取るものだと言っていい。最初の「これはリンゴです」から、「これはリンゴかな?」「もしかしたらこれがリンゴかもしれない」「まさか、これはリンゴじゃないだろうな」と進むにつれ、そのものを「リンゴである」とする指示性が次第に弱められていく。
《つまり、この指示性が弱められていく分だけ、男は彼の体内の疑問を増大させ、それによってリンゴとの関係を安定させなければならない。/観客もまた、同様である。リンゴがリンゴであることの指示性が弱まり、そこに「在る」実質としてのリンゴと、「リンゴ」という言葉が乖離してゆくに従って、日常的な安定感がゆらぎはじめ、不安を覚えることになる。そして、「リンゴ」という言葉ではなく、そこに「在る」実質としてのリンゴとの関係において安定したいと傾向づけられ、「これがリンゴか」という、再発見にまで及ぶというわけだ》(前掲書)
生きる上での示唆、物事の本質
もともとリンゴには、古来よりさまざまなエピソードと、それにまつわるイメージが付与されてきた。旧約聖書のアダムとイブに始まり、ウィリアム・テルが息子の頭の上に乗せたリンゴ、白雪姫が継母から食べさせられたリンゴ、ニュートンが万有引力の法則を発見したリンゴ、さらには敗戦直後の流行歌「リンゴの唄」や「リンゴをかじると歯ぐきから血が出ませんか?」という歯みがきのCMに至るまで、リンゴは実に多様なイメージで彩られている。「リンゴのドラマツルギー」とは、そうした言葉やイメージを剥ぎ取って、今一度リンゴそのものに向き合いながらその実質を見出し、関係を再構築しようというものであった。
《言ってみれば、リンゴは今「言葉だらけ」の存在となっているのであり、今後更にそれにまつわる言葉を、増殖させつつあるのである。こうした傾向がこのまま続いたら、間もなく我々は、「リンゴを食べる」のではなく、「リンゴというイメージを構成する言葉を食べる」ということになりかねない。/《リンゴのドラマツルギー》は、こうした言葉の洪水の中で沈没しかけているリンゴの実質を——沈黙した「物」としてのそれを、救い出そうとするものである。そしてこれは、リンゴだけにとどまらない。現在我々の周囲にある、我々の知っているあらゆる存在が、そのような状況のもとに置かれているのである。それらひとつひとつについて、我々は今、それぞれのドラマツルギーを見出していかなければいけなくなりつつある》(前掲書)
情報社会とは、まさにあらゆる存在が「言葉だらけ」になった状況である。いまや地球全体に拡大された電子網を膨大なイメージと言葉が飛び交っている。その中には本当ともウソともつかないものも、また膨大に含まれる。そんな時代を生きる上で、別役の作品は私たちにさまざまな示唆を与えてくれるのではないか。たとえば、先に取り上げた『日々の暮し方』以外にも、『けものづくし』を始めとする「づくしもの」と呼ばれるシリーズなど、別役のエッセイには、もっともらしく書かれてはいるが実はまったくのでたらめという内容も少なくない。それでいて、物事の本質をずばり喝破していたりする。
「べつやく」か「べっちゃく」か
「言葉だらけ」といえば、ウィキペディアの別役実の項でもまた、彼について多くの言葉により説明がなされている。そこでずっと気になっていたのは、彼の姓について「べっちゃく」と「べつやく」とふたつの読みが併記されていることだ。私の知る限り、彼の著書のプロフィールのほか、事典の類いでも「べつやく」読みが採用され、「べっちゃく」というのはウィキペディア以外に見たことがない。果たして「べっちゃく」読みも正しいとするソースはどこにあるのか、残念ながらウィキペディアにはそこまで示されてはおらず、ずっともやもやしていた。
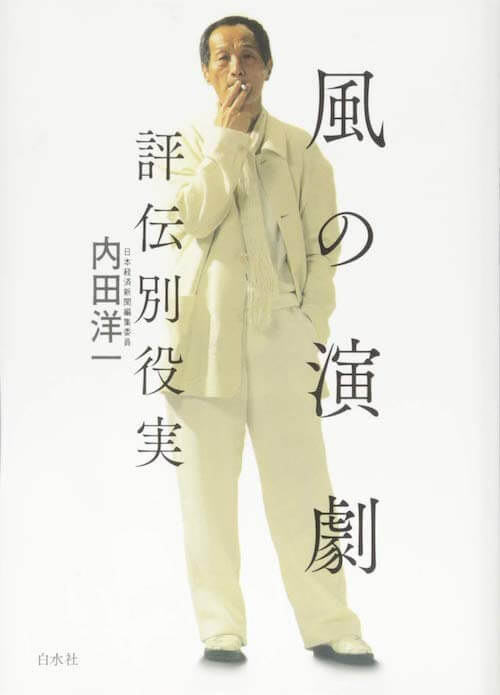
ようやく氷解したのは、日本経済新聞編集委員の内田洋一が一昨年に上梓した『風の演劇 評伝別役実』を読んでからである。同書によれば、別役家のルーツは高知で、土佐人にすれば「べっちゃく」と読むのが本当だという。それが本人曰く《べっちゃくと言っても東京では理解してもらえないから、それで、べつやく、べつやくと自分でも言っていた》(『風の演劇』)。彼が演劇活動を始めたのは東京に出てからである。とすれば、本来は「べっちゃく」であれ、公にはやはり「べつやく」の読みが正しいような気もする。ちなみに内田洋一は本人との間でこの話題が出たとき、うっかり戸籍ではどちらなのか聞いてしまったところ、「ま、カナふってないからね」という答えが返ってきたという。冗談好きだった彼らしい物言いではないか。
最後にお断り
ついでなので言っておくと、この原稿の冒頭で、別役の脚本で連合赤軍事件の映画の計画があったと、さももっともらしく書いたが、そんな映画は実現しなかったどころか、計画すら存在しない。件の映画についての記述は、監督とドリフの関係などを除けばすべて、別役のエッセイを不遜にも真似てみようと思って、私がでっちあげたものである。本来なら、ウソだとバラさないところまで真似るべきなのだろうが、ウィキペディアによけいな情報を追加されても困るので、最後に一応、お断りしておく。
参考文献
別役実『犯罪症候群』(ちくま学芸文庫/1992年)、『東京放浪記』(平凡社/2013年)、『日々の暮し方』(白水Uブックス/1994年)、『宇宙遊泳する時代』(彌生書房/1991年)
扇田昭彦『日本の現代演劇』(岩波新書/1995年)
大田俊寛『オウム真理教の精神史―ロマン主義・全体主義・原理主義』(春秋社/2011年)
筑紫哲也『若者たちの大神 筑紫哲也対論集』(朝日新聞社/1987年)
内田洋一『風の演劇 評伝別役実』(白水社/2018年)