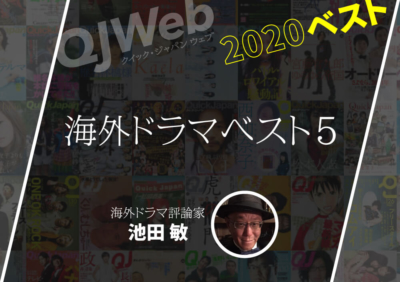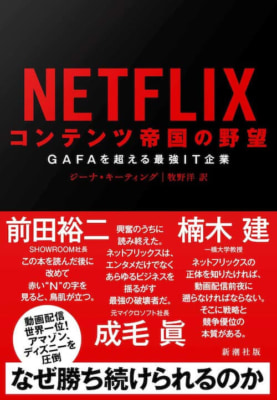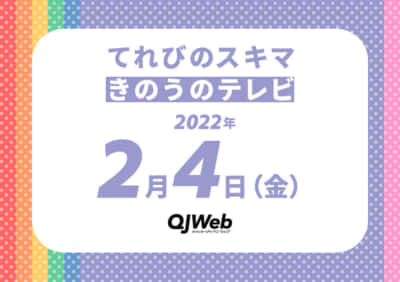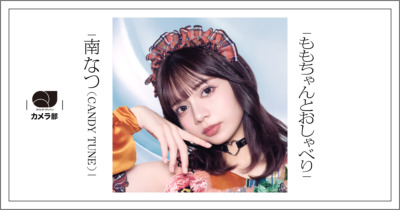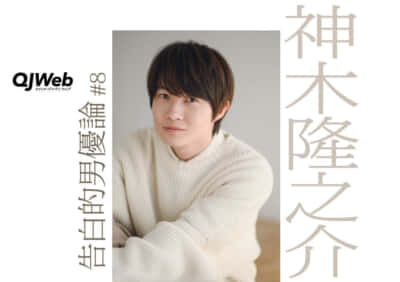全米の学校で教材にも採用
ディズニープラスには大人も要注目というコンテンツが多い。『ハミルトン』は演劇界の権威、第70回トニー賞で史上最多ノミネーションを獲得し、11部門で受賞した傑作演劇を収録。アメリカ合衆国建国の父のひとり、アレクサンダー・ハミルトンを主人公にした物語とあってなんと全米中の学校で教材となり、ここにもディズニープラス独自の路線を感じる。
ちなみにディズニープラスは「ナショナル ジオグラフィック」のドキュメンタリーも充実しており、これらもコロナ禍で学校に行けない子供たちにとって格好の教材になり得る。
オリジナルのドキュメンタリーシリーズもあり、『マーベル616』はマーベル・コミックと社会の関係に迫るが、これの第6話(以前は第1話だったはずだが)「日本版スパイダーマン」は、これだけでも多くの日本人に観てほしい感動的なドキュメンタリーだ。
アニメーションとシリーズ作品というディズニーの強み
これは偶然が重なっただけだろうが、映画会社としてのディズニー自体、コロナ禍のような非常事態に強いという一面がある。まずアニメーション自体、リモートワークで作品作りがしやすい。さらに実写映画においても、2016年の『ジャングル・ブック』のように俳優以外はほとんどCGという作品にも挑んでおり、実写パートにおいてスタッフを減らすことが可能だ(ただしVFXのスタッフは通常の実写映画以上に多そうだが)。何より、シリーズ化が可能なヒット作が多いのがディズニーの強みである。
改善されるべき点がないわけではない。ディズニーが脱アニメーションを目論んで1980~90年代に力を入れた実写映画の数々や、20世紀フォックスの過去のライブラリーをもっと配信ラインナップに加えてほしいと願う。確かに、中にはファミリー向けと呼びがたい作品もあるが、もう少し料金が上がってもそれらを観たい大人のユーザーは多いはず。
いや、もうひょっとしたら、そうした“ディズニープラスプラス”の構想があるかもしれない。何はともあれ、表面からは見て取れない伸びしろが実は多いディズニープラス。サービス名についた1文字、“+(プラス)”は、ディズニーの未来を象徴しているのかもしれない。

関連記事
-
-
4年目の今、重荷だった「王子様」を堂々と名乗れる。Last Princeが語る、プリンスを背負う勇気と楽しさ
Last Prince:PR