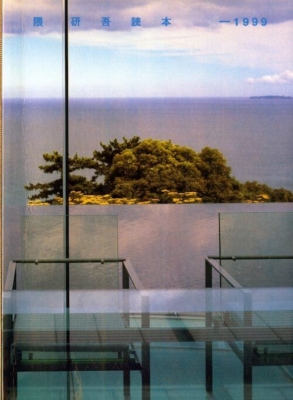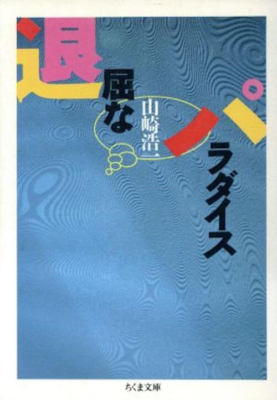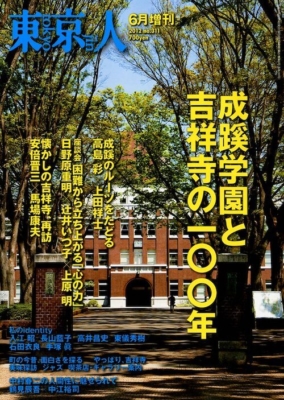削除された?「みんなちがってみんないい」
対談でちぐはぐなのは会話だけではない。記事中、先の馬場と安倍のやりとりの直前に掲げられた小見出しにも、不自然なところがある。その小見出しでは「鈴と小鳥とそれから私 みんなちがってみんないい」という、金子みすゞの詩の一節が引用されているのだが、肝心の対談にはなぜかこれに該当する発言が出てこないのだ。これはいったいどういうわけか? 真相はおそらく、成蹊学園の個性重視の教育を語る上で、馬場か安倍いずれかの発言に出てきたものの、ゲラの段階で削られてしまったのだろう。だとすれば小見出しも変えないといけないが、うっかり見落とされてそこだけ残ってしまったものと思われる。邪推するに、対談からみすゞの詩を削ったのは安倍のほうで、替わって引用されたのが、先の吉田松陰の言葉だったのではないか。
成蹊学園における個性重視の教育は、明らかに安倍が政治家として推し進める教育政策とは相容れない。そう考えれば、対談の不自然な点も説明できる。同時に安倍の中でも、自分が実際に受けた教育と、政治家としての教育観の間にはかなりのギャップがあるともいえる。
教育観に限らず、安倍の政治信念には、どうも自ら体得したものではないような印象がつきまとう。前出の野上忠興も、《安倍が「正しい」と信じる憲法や安保政策に対する考え方そのものが、彼の人生において、学生時代の議論や政治史、思想史、法学などを学ぶ中で身に付いたものでもなければ、政治家として国政に携わる中で検証し磨かれたものでもない》とずばり指摘していた(『安倍晋三 沈黙の仮面』)。
では、彼の政治的モチベーションの源泉はどこにあるのか。それは祖父・岸信介の「教え」を守るということに尽きるのではないか。安倍が第1次政権から今回の首相辞任に至るまで政権の最重要課題として掲げてきた憲法改正も、祖父が首相時代に果たせなかった悲願であった。安倍は幼少期よりかわいがってもらったこの祖父に多大な影響を受けているとは、よく指摘される。事実、政治とは無縁に思われた大学時代にも、こと憲法絡みの話になると、人が変わったように激し、能弁になったとの学友の証言もある。学友はその場面に遭遇して、安倍の岸への思い入れを強く感じたという(前掲書)。
結局、憲法改正は、強い政権基盤を得た安倍をもってしても実現できなかった。当初は憲法全文に手を入れるはずだったのが、いつのまにか9条に自衛隊の存在を明記するだけの「加憲」へと後退していた。この原因としては、2015年に安保関連法案を可決させる際、憲法解釈を変更して集団的自衛権の行使を容認するという手段を取ったため、本来的な「改憲の必要性」という大義が薄弱になってしまったとする国際政治学者の中西輝政の指摘もある(「「安倍政権はあの瞬間に一変した」歴代最長“一強”政権が暗転した“2015年夏の分岐点”とは」『文春オンライン』2020年9月13日配信)。それでもなお安倍が憲法改正に固執したのは、やはり祖父の悲願を達成せねばならないという個人的な心情ゆえとしか考えられない。
大学がレジャーランドな時代
祖父の思いを受け継ぐことが、安倍にとっての政治的なモチベーションになったのには、世代的なものもあるように思われる。1954年生まれのこの世代にとって、もはや政治は多くの若者が志すほど魅力的なものではなくなっていた。そこには60年代末~70年代初めの高度経済成長が大きく影響している。明治以来、日本の最大の国家目標は、欧米へのキャッチアップ(追いつき追い越せ)であったが、高度成長によってほぼ達成されてしまった。また、高度成長を経て社会は複雑化し、政治家の役割も国民を主導するというよりは、さまざまな階層からの要求を調整することこそ重要になってきた。こうなると若者が自発的に政治を志す動機づけは乏しくならざるを得ない。政界から叩き上げが減り、2世や3世の政治家が幅を利かせるようになったのには、そんな背景もあるのだろう。いわば政治家志望者のモチベーションが、国家目標という「大きな物語」を共有することから、肉親の意志を継ぐという「小さな物語」へと移行したわけである。
「大きな物語」といえば、かつては多くの若者を惹きつけた共産主義イデオロギーも、新左翼運動が1960年代の大学紛争を経て袋小路に入り、内ゲバが多発するようになると、急速に色あせていった。安倍たち1954年生まれは、すぐ上の世代(終戦直後に生まれたベビーブーム世代=団塊の世代)の政治運動が敗北を喫するのを見ながら、大学に入学する。
1954年生まれが大学に入ったちょうどその年、1973年には第1次石油危機が起き、日本の高度成長が公害などさまざまな問題を残しながら終焉を迎えた。右肩上がりの時代が終わり、バラ色の未来を描きにくくなる中で、若者たちはせめて学生時代だけは楽しもうと、ひとときのモラトリアムを享受するようになる。大学がレジャーランドと呼ばれ出したのもこのころだ。ホイチョイ・プロダクションズの馬場康夫は就職後も、社会に染まってしまうのが嫌で、大学卒業後5年くらいは、年に1回ほど車を飛ばして学校に行っていたという。馬場に限らず、この世代にとって学園生活は、卒業してからもそんな行動に駆り立てるほど楽しい思い出に満ちたものなのだろう。
ホイチョイの一連の作品も、こうした学生気分の延長にあることは間違いない。ただ、彼ら1954年生まれはなまじ学生運動の敗北を近くで見ており、石油危機で就職難も経験しているだけに、そのあとのバブルを謳歌した新人類世代のように遊びに徹するということもできない。この世代には、そんな中途半端さを自認する人も少なくない。やはり同年生まれのコラムニストの山崎浩一は次のように書いている。
昭和29年なんて年に生まれた世代ってのは、なんかこうハンパなんですね。みそっかすなんですね。ぼく自身そうだからよくわかるんですけど。シラけきるには早すぎて燃え上がるには遅すぎる、というか、発射してしまうのはまだ早いけど抜くのはもう遅い、というか、まあつまり「前門の団塊、後門の新人類」の煮えきらない世代なんですな。というより、ほとんど「世代」として認知されていないといっていい。
『退屈なパラダイス』ちくま文庫
山崎はさらに、同じ本に収められた別のコラムでこのように自分たちの世代を分析する。
60年代と70年代、全共闘と無共闘の、ふたつの時代/世代の谷間のミッシングリンクみたいなぼくの世代は、特にその世代的アイデンティティを取り沙汰されたり背負わされることもない。(中略)そう、この世代は「世代」なんぞという不粋で乱暴な枠組みではひとくくりにできないことを最大のアイデンティティとする、トワイライトなハイブリッド種なのだ。
『退屈なパラダイス』ちくま文庫
たとえば、ぼくと同世代である松任谷由実、矢野顕子、大友克洋、ホイチョイ・プロダクション、林真理子、所ジョージ……(とんでもない顔ぶれだ)。彼らのそれぞれの仕事の間には、なんの世代的共通項も見出せない。彼らを「同世代人」として眺めたことも、一度もない。たまたま同い年であるという、ただそれだけのことだ。
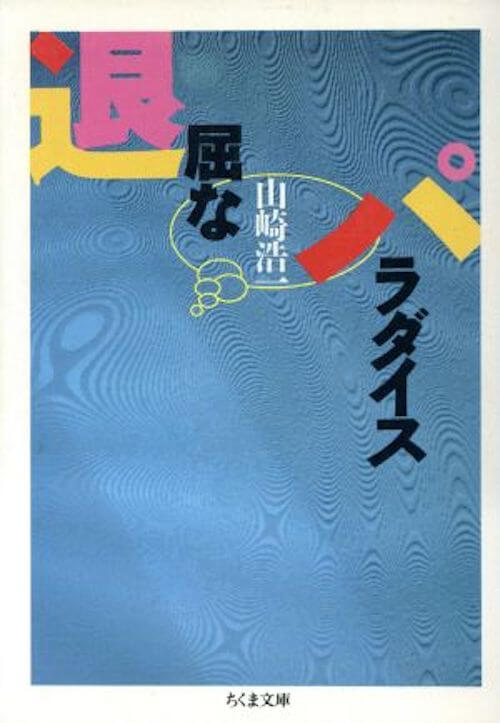
ちなみに引用文に挙がった人物のうち、矢野顕子と所ジョージは1955年の早生まれにあたる。1954年~1955年の早生まれの著名人にはこのほかにも、ミュージシャンではTHE ALFEEや竹内まりや、アナウンサー・タレントの古舘伊知郎、タレント・俳優の片岡鶴太郎、歌手の南沙織、太田裕美、元キャンディーズで現在は俳優の伊藤蘭、俳優の三浦洋一、小日向文世、根岸季衣、檀ふみ、高橋惠子、秋吉久美子、タレント・テレビプロデューサーのデーブ・スペクター、声優の千葉繁、小山茉美、落語家の春風亭小朝、立川志の輔、建築家の隈研吾、ゲームシナリオライターの堀井雄二、CMクリエイターの佐藤雅彦、漫画家の星野之宣、寺沢武一、青色LEDの開発者のひとりでノーベル物理学賞受賞者の中村修二、元ラグビー選手の松尾雄治、元プロ野球選手ではランディ・バースとブーマーというふたりの三冠王経験者のほか中畑清や田尾安志といった名前が挙げられる。政界では共産党委員長の志位和夫が、安倍前首相と同い年にして共に1993年の総選挙で初当選した同期にあたる。
これらの顔ぶれを見ていると、どうも時代ごとに変貌を繰り返した人が目立つ。中でも顕著なのは片岡鶴太郎だろう。80年代には『オレたちひょうきん族』などのバラエティ番組で被虐的キャラとして笑いを取っていたのが、ドラマ『男女7人夏物語』で演技に開眼、並行してプロボクサーを目指したのを機に小太りだった体も絞って個性派俳優へと転じた。その後は、画家としても活躍、さらにヨガによってまた大きく変身を遂げた。
作家の林真理子もまた、常に変わりつづけながら、のし上がっていった感がある。80年代にコピーライターを振り出しに、結婚願望をあけすけに綴ったエッセイで売り出すと、テレビにも出演してやや色物的に見られていたのが、小説を書き始めるや直木賞を受賞。90年代には結婚して子供も儲け、今や直木賞の選考委員や日本文藝家協会理事長などの要職にあり、昨年の新元号の選定にあたっては懇談会のメンバーにも選ばれた。
関連記事
-
-
4年目の今、重荷だった「王子様」を堂々と名乗れる。Last Princeが語る、プリンスを背負う勇気と楽しさ
Last Prince:PR