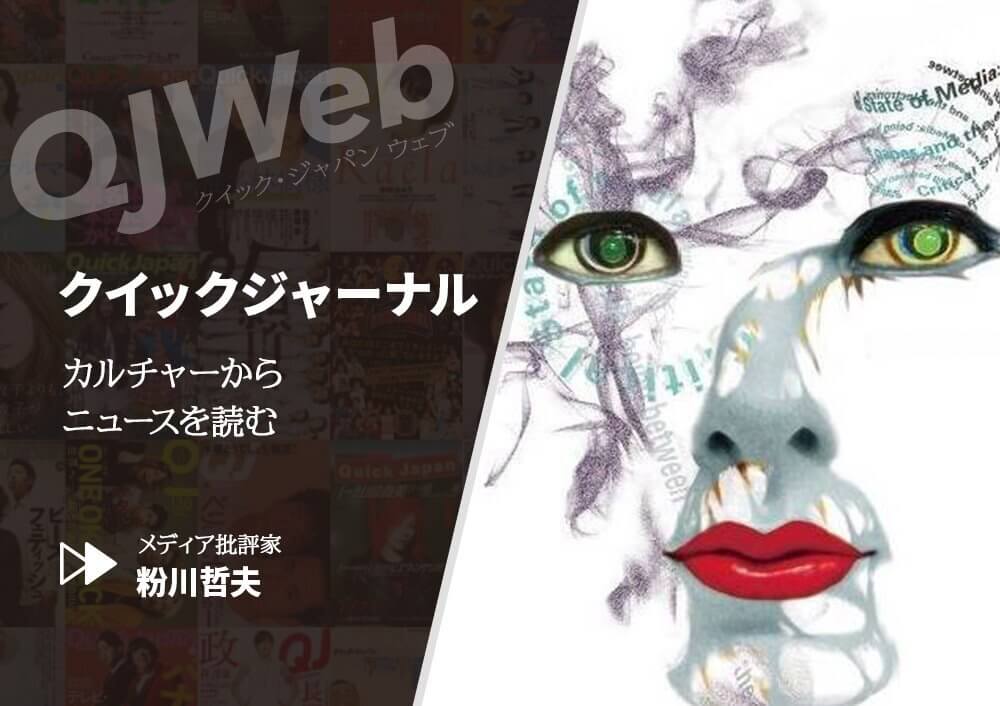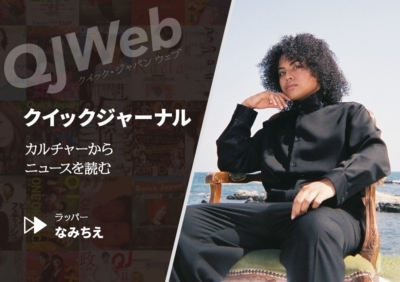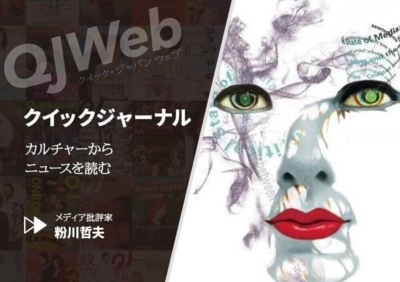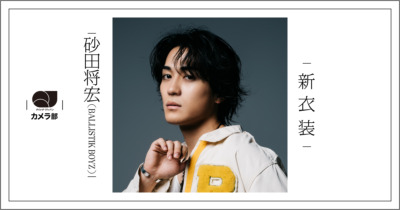「電脳化することで『デジタル上で人間は生き続けられる』と主張するマインドエミュレーション財団が登場」(『GIGAZINE』2020年9月3日)という記事が、“不老不死”的なテーマとの関連もあり、一部で注目を集めている。
記事では、「人間の肉体は死んでしまうが、心をデジタルでエミュレートすれば人は生き続けられる」と主張し、寄付を募る「マインドエミュレーション財団」のウェブサイトが発見されたとある。
『メディアの牢獄』(1982年)や『もしインターネットが世界を変えるとしたら』(1996年)などの著書を持つメディア論の先駆者として知られるメディア批評家の粉川哲夫は、このニュースをどう見たのか。
そんなQJWeb編集部からの問いかけに対して、彼は「TK」と「MX」との対談というかたちで回答を寄せた。
クラウド上で「生きつづける」
「マインド・エミュレーション」への関心が高まっているというので、AIやブレイン・インターフェースの研究家、その方面の起業家の知り合いに意見を聞いてみた。以下は、その複数の意見と回答を「MX」の発言としてまとめたものである。
TK 最近、「マインドエミュレーション財団」というのが立ち上がったと聞きましたが、その公式サイトをのぞいても、はっきりした方向が見えませんね。
MX ああ、ダン・シロカーが立ち上げたやつね。ひとりの人間の「マインド」を生きながらえさせることを、アンチエイジング(抗老化)やインモラリティ(不老不死)に引っかけたところが商売としては新しいかな。
TK あまり評価してない口ぶりですね。
MX ダンは、思想家というよりも起業家だからね。オバマの2008年の選挙対策チームで働いたり、グーグルの「Chrome」の立ち上げにも参加し、そのあと「オプティマイズリー」というスタートアップを立ち上げて、成功したんだ。ビジネスデータの有効活用実験のモデルやソリューションを提供する会社だね。スタートアップはテリトリーを多重化していくのが常識だ。彼は、「スクライブAI」というスタートアップのCEOもやっている。
TK “スクライブ(scribe)”というのは、羊皮紙に律法の文字を記す写字生の意味ですが、これからはAIが世の中の重要事項を律法化していくという含み?
MX 知らないなあ。そうかもしれないけど、マインドエミュレーション財団と同じで、とりあえずヴィジョンを提示したんだろう。
TK マインド・エミュレーションの可能性自体はどうなんですか?
MX これは、今に始まったことではない。ロボット、AI、人工生命といった古い概念の中にも同じ考えがあったし、「全脳エミュレーション(Whole Brain Emulation)」、「マインド・アップロード」、「ブレイン・アップロード」、「マインド・コピーイング」というような言い方で、脳の機能をシミュレートし尽くそうというアイデアやプロジェクトは限りない。
2005年にスイス連邦工科大学(EPFL)が始めた「ブルー・ブレイン(Blue Brain)」プロジェクトでは、脳神経細胞を分子レベルでシミュレートし、デジタル情報にするんだが、そのモデルは大学のスーパーコンピューターの中にしかないわけで、1個の人間の代わりにはなりにくいのだ。
TK しかし、モデリングが可能なら、その情報をネットで共有したり、トランスファーしたりできるわけですね。それは、ある種の「デジタル・ヒューマン」じゃないんですか?
MX 確かに、SFや映画の中のようにデジタル・ヒューマンが「人間サイズ」、つまりボディサイズである必要はないわけで、クラウドの中に偏在していてもいいわけだ。おそらく「マインドエミュレーション財団」が狙っているのも、個々人が、クラウド上で「生きつづける」ようなフレキシブルなデータブロックを提供しようということなのかもしれない。
関連記事
-
-
4年目の今、重荷だった「王子様」を堂々と名乗れる。Last Princeが語る、プリンスを背負う勇気と楽しさ
Last Prince:PR