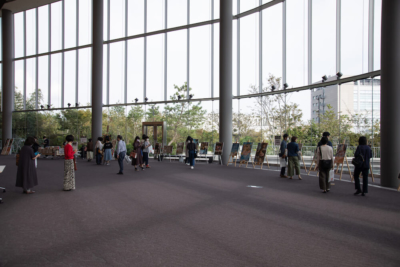観客を育てるための「集中講義」
観客を育てること。それが映画祭の目的ではないかと行定監督は言う。
「お前らに育てられたくないよ、と反発の声が挙がるかもしれませんが(笑)。僕自身、1980年代、ホウ・シャオシェン、エドワード・ヤン、ウォン・カーウァイといった監督たちの登場で、未知のアジア映画について学んでいった過去があります。観客に、多様性と自由、精神性、そして映画の見方というものを知らしめることも映画祭の役割なのではないか。映画の観客が育つことは、僕ら映画人にとって絶対いいことですし」
とはいえ、映画学校のように順番に「教える」わけではない。『くまもと復興映画祭』は、「飛び級」だと微笑む。
「いきなり、知らない世界に連れていく。たとえば、2日間で8本観たら、映画を1年分観たような満足感が得られる、濃い『集中講義』になればいいなと。映画祭を6年やっていると、確実に映画ファンが育っていることを実感します。最初は高良健吾のファンでしかなかった人たちが、今年は何が観られるのかなと、楽しみにしてくれているんですよ。かなりマニアックな期待を抱いている。映画を観て、自分の頭で考えて、その上で来場したゲストの話をティーチインで聴くから、さらに深められるんです」

今年の映画祭でも、ティーチインにおける観客からの質問はとても細やかで、作品の核心を突くものが多かった。確かに「育って」いた。
「映画祭にはボランティアがつきものですが、この映画祭は、イベント会社に任せています。ホスピタリティの面からもそのほうがいいと思うから。たとえば、音楽のフェスを開く場合、もしボランティアを雇ったら大混乱ですよ。韓国の『釜山映画祭』などには、まるでプロのようなボランティアスタッフがいます。そのための『教育』がきちんとなされているから。
でも日本だと、人手が足りないから『ここにいてね』というレベルのことが多いと思う。それだと、せっかく参加してくれた人も帰るときには疲弊してるんじゃないかと。映画祭に気持ちがある人を、そんなふうに失いたくないし、むしろ観客として来てほしいんですよ」
とりわけ、コロナ状況下での開催となった今年は、プロフェッショナルなスタッフの存在が不可欠だった。三密を避け、安心して映画を楽しめる環境作りが、行定監督のもとホスピタリティ重視の姿勢に見事に重なった。
各回の上映後は、来場ゲストによるチャリティーTシャツへのサイン会も行われたが、そこでも混乱は一切見られなかった。ゲストと観客にはしかるべきディスタンスが保たれたが、そのことによって、むしろハート・トゥ・ハートな温もりある通い合いが生まれた。場をコーディネートする優秀なスタッフの存在は大きい。

「映画祭は、自分にとっては、ひとつの映画を作っているようなものですね。彼ら優秀なスタッフは、優秀な助監督のようなもの。今年は客席を減らしたこともあり、結果的に、『無理をしない、背伸びをしない映画祭』になったと思います。
そのぶん、一つひとつの映画をきちんと届けることができた。ティーチインをオンラインで配信したり、深夜の恒例企画をオンラインイベントとして展開したりもしました。フィジカルがあるからこそ、それらのリモートも併用できると実感しました」