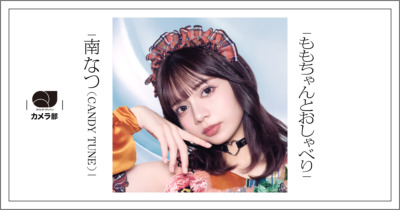『チィファの手紙』『窮鼠はチーズの夢を見る』──それぞれの映画に見る作家性
行定監督は『チィファの手紙』を観て、中国映画でありながら、圧倒的に「岩井俊二」という映画作家の作品になっていると感じたようだ。さらにそこには、岩井監督の“作り方の独自性”があるのだという。本作のプロデューサーに名を連ねているのは、『ラヴソング』(1996年)などの監督であり、『孫文の義士団』(2009年)などをプロデュースしてきた巨匠ピーター・チャンだ。
行定 僕は非常にアジア映画に影響を受けてきましたし、インディペンデント的に作られている中国映画って、今すごいレベルまできていますよね。そこに岩井さんが参入していくのはおもしろいと思いました。しかも、ピーター・チャンがプロデュースするという。ジョウ・シュンやチン・ハオといった中国映画界を支えてきた俳優たちが作品の中心に立っているのもよかった。
それに何より、作家性が物語にも画にも現れていると感じましたね。苦労やプレッシャー、ストレスなどはあったかと思いますが、それを凌駕するような作品に仕立て上げているのがすごい。僕も経験がありますが、中国で映画を作るのは難しいんです。そのなかできっちりと“岩井俊二の映画”を作り上げている。『チィファの手紙』は中国映画でありながら、圧倒的に岩井俊二という作家の作品でした。

岩井 ピーター・チャンたちのチームの援護あってこそのものだったので、彼には感謝しかないです。現場での苦労は記憶にないと言えるくらいなので、本当に助けられました。
行定 岩井さんのすごいのはひとつの作品のモチーフを何通りにも広げていくところ、“作り方の独自性”だと思います。『ラストレター』と『チィファの手紙』の関係性もそうですが、劇場上映や配信などのメディアの形式にも囚われず、“自分で自分の作品をリメイクする”という。そう考えると、市川崑監督に近いものを感じます。

一方の岩井監督は『窮鼠はチーズの夢を見る』を観て、“性別”など関係のない普遍的な恋愛映画になっていると感じたのだという。
岩井 『窮鼠はチーズの夢を見る』は全体的に群青色がかっていて、まるで水の中にいるような作品でした。最後のほうの海辺のシーンで、今ヶ瀬(成田凌)が恭一(大倉忠義)に対して「例外だった」と言うセリフがあって、彼は恭一みたいな人のことは本当は好きではなかった。でも「自分の中で例外だった」というのが、すごく腑に落ちたんです。
これは男女間においても言えますが、ふたつとない相手を選ぶときというのは、自分の人生における一番の人を選ぶイメージをみんな持つと思います。「一番好きだから、一緒にいるんだ」というような。でも今ヶ瀬の場合、“一番の例外”を選んでいる。これって真理を突いているな、と思いました。あの海辺のシーンで、この映画は普遍化したと感じましたね。恋愛映画として普遍的なものになり得た。男性同士だからというものではなく、想いを向け合う者同士、そこに性別は関係ないと証明したんです。

行定 あの海辺の会話というのは、やっぱりすごく核になっています。「あの場面に向けて作りたい」というのは最初から言っていました。岩井さんの言うように、「例外だった」というのは腑に落ちるものです。それがちゃんと感じられるように過程を構築していくことがすごく重要でした。
それにこういった作品って、「BL」や「LGBTQ」といった言葉で括られがちなんです。でも、まさに岩井さんの言うとおり性別に関係なく、“替えがたい何か”があるかどうかが重要。現代は“個人”というものがすごく問われている時代で、いろんな考え方が共存しています。それをどれだけ正当化できるか。映画においても“選択肢“を与えないといけません。これが僕の裏テーマで、宣伝でも「BL」や「LGBTQ」という言葉は使わないでくれと言いました。この作品は、“人が人を好きになる”という事実を描いたものなんです。
関連記事
-
-
4年目の今、重荷だった「王子様」を堂々と名乗れる。Last Princeが語る、プリンスを背負う勇気と楽しさ
Last Prince:PR