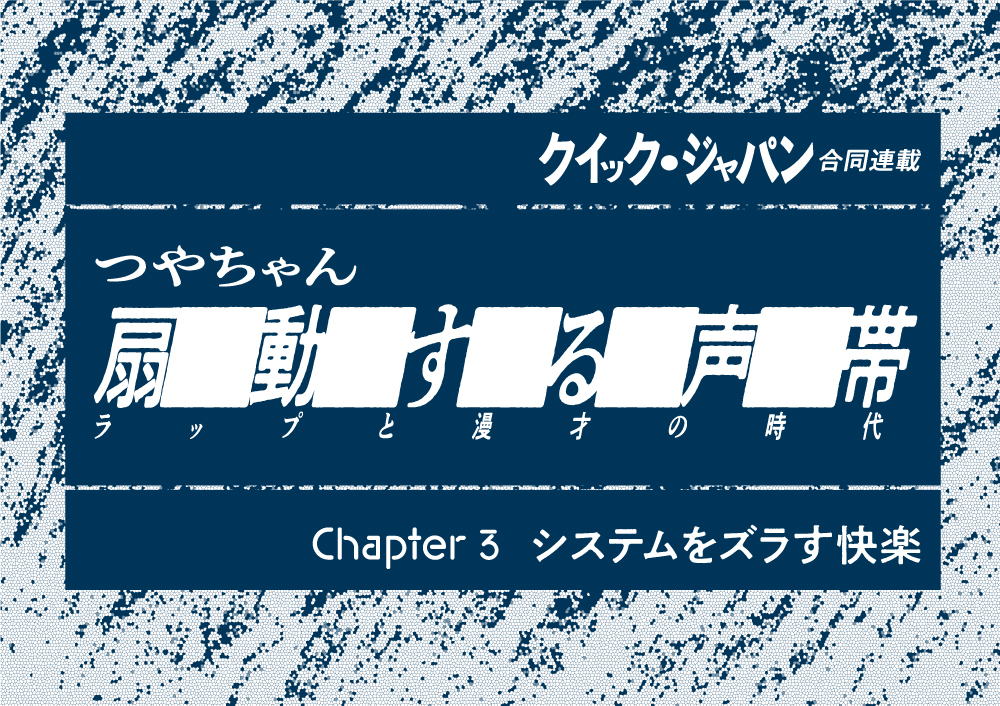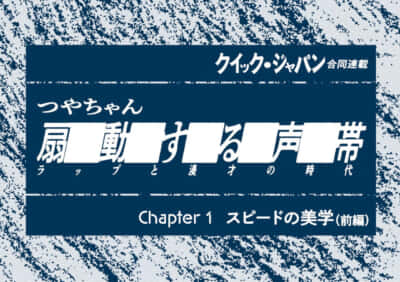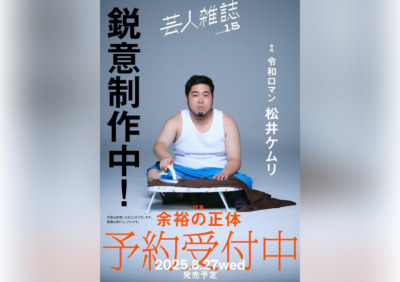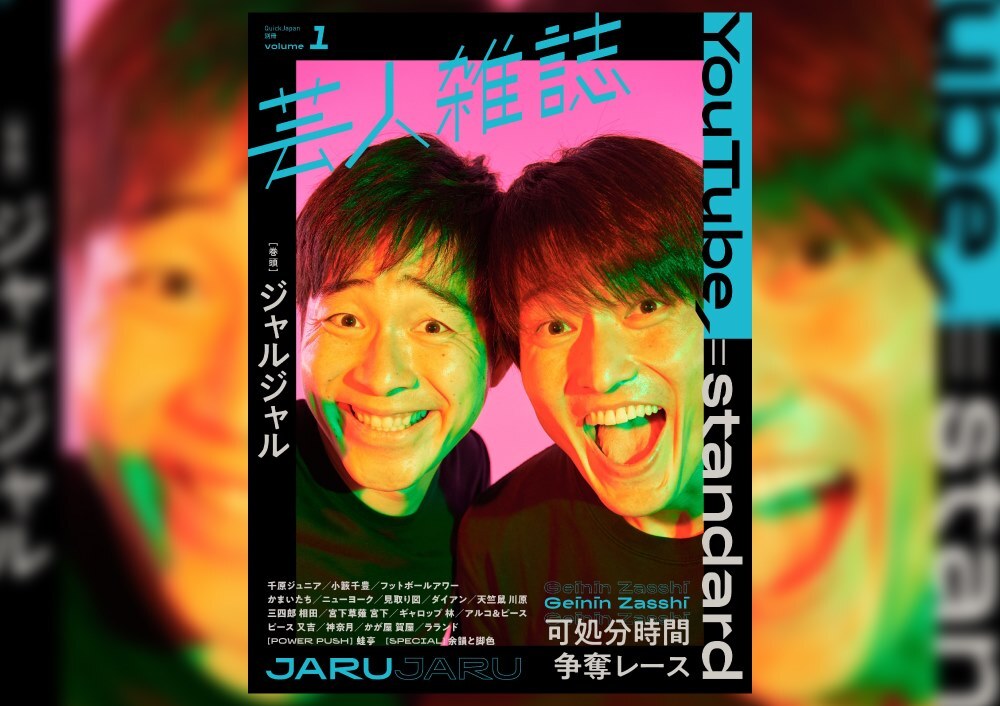新たな角度と言葉からラップミュージックに迫る文筆家・つやちゃんによる、ラップと漫才というふたつの口語芸能のクロスポイントの探求。『クイック・ジャパン』と『QJWeb』による合同連載「扇動する声帯──ラップと漫才の時代」Chapter3。
Chapter3「システムをズラす快楽」
漫才のラップミュージック化が止まらない。
笑いの喚起を目指す口語芸能──音楽とはまったく関係ないものと認識されているその試みが、驚くべき展開を見せているのである。MCバトルへ参入するお笑い芸人が増えていること、界隈においてヒップホップへの愛がそこかしこで宣言されていること、ラッパーと芸人のコラボレーションが多発していること、それら目に見える事象がまずは挙げられるだろう。しかし、実は私たちの意図せぬ深層でもそれら漸近は大胆に進んでいる。いま、漫才はその定義を膨らませ、目を見張るような運動神経でラップ側への侵入を果たしているのだ。
2021年は、漫才がラップミュージックへ大きなラブコールを送った年として記憶されるべきだろう。この年の『M-1グランプリ』では、いくつかの出演者がループ音楽に接近するかのような“型”を志向し、作品に新鮮なリズムを導入することに成功した。準々決勝での怪奇!YesどんぐりRPG、準決勝でのヨネダ2000、そして決勝での「もも」が挙げられる。
三組とも近年徐々に『M-1グランプリ』での順位を上げ、過去最高となる成績でじわじわと賞レースでの存在感を高めている。
ラップに最接近した『M-1グランプリ2021』
それぞれが“せめる。”と“まもる。”という名で「もも」を称するコンビは、決勝で敗れ去った。彼らが興味深いのは、お互いが相手に対し「〇〇顔やん」というボケをぶつけ、それに対し「なんでやねん」とツッコミを入れていくという、その決まりきった型の反復にある。
いや、ループ性を目指す芸であれば、これまでもいわゆる“行ったり来たり漫才”のような形で行われていたはずだ。けれどもその徹底加減たるや、ネタの本題に入ったひと言目──「まぁみんなもそうやと思うけど」という「みんな」の強調された音程から早速“型”を遂行するスイッチが押されるほどである。「みんな」の音程は本作における主軸として幾度となく繰り返される「なんでやねん」と近しい響きで発声され、次第にフックと化していくのだ。
“せめる。―攻める”と“まもる。―守る”が怒涛の応酬をループさせ、それらを軸に「なんでやねん」というアイデアをフックとして一本の作品で貫き通す、極めてヒップホップ的ゲーム性が憑依した作品であろう。
一方で、誠と愛のふたりが組むヨネダ2000は、突如現れた新風として鮮烈な才能を印象づけた。漫才史を参照するならば、たとえばジャルジャルがこれまで試みてきた純粋なるラップ的アプローチとは異なる方法での、2MCの役割を解体する実験である。
敗者復活戦で披露された『YMCA寿司』を見てみよう。「自分、寿司屋の大将やるからずっとYMCAやってて。そうすりゃ大金持ちさ!」というひと言から本題のネタに入る本作は、誠の「ずっとYMCAやってて」という指示により冒頭から2MCの役割が放棄される。しかし「そうすりゃ大金持ちさ!」と宣言し資本主義ゲームに没入した次の瞬間から、驚くべきループ音楽が演じられるのだ。
誠はひとりで二役を演じつつ──霜降り明星・せいやのドタバタ劇とは異なる、極めて冷静沈着でメカニカルな動きが特徴的だ──、相方の愛は「YMCA」を延々と反復させることで、リズムを紡ぎ誠の一人二役話芸を支えていく。言うなれば、愛の「YMCA」は下部構造を支えるトラックの役割を果たし、その上部で誠が二役の“ポエトリーラップのごとき”応酬を展開するのである。
怪奇!YesどんぐりRPGも注視すべき才能だろう。『M-1グランプリ』で披露された「ムール貝•改」は、舞台上を広く使ったフォーメーションや『ドラえもん』のボケなどに見られる身体芸が印象的で、一見すると“しゃべり”の外部の力に頼ったパフォーマンスとも映る。しかし、延々と繰り返される「ムール貝酒蒸しにして~/酒蒸しにしたら酔っぱらっちゃうヨ~ン様ンサタバサ」のループはフックとして次第に中毒性を生んでいき、しまいには快楽へと繋がる不思議な魅力を発している。
漫才におけるループの力
漫才、ひいては笑いにおける「反復」とは、実際のところどのような作用を果たしているのだろうか? 興味深いことに、それらは“反復されることで”ようやく笑いに昇華されるのである。ボケとして、あるいはツッコミとしてひと言で放り出されただけでは笑いにつながりにくい“弱い”台詞が、何度も繰り返されることで“強さ”につながっていく。
弱さのべき乗が強さに化けること、それが反復の面白さである。たとえば、笑いのメカニズムを解き明かした名著『笑いのセンス』著者である中村明は、二葉亭四迷の『平凡』を引きながら、笑いの技法としての反復について次のように述べる。
読者が、なにも「平凡」という語をそこまで繰り返さなくてもいいのに、という気分になれば、作者のしつこい反復操作に頬がゆるむかもしれない。
『笑いのセンス 日本語レトリックの発想と表現』(中村明/岩波書店/2002年)
かたや、漫才やコントのテクニック形態を分類した井山弘幸著『笑いの方程式』はタカアンドトシの「欧米かっ!」というお決まりのツッコミを例に挙げ、タカが演じようとしたのは実はアメリカ風であり欧州ヨーロッパとは無関係であった事実を指摘しつつ、
そうなると「欧米かっ!」というツッコミ自体もどこか変で滑稽でもある。
『笑いの方程式 あのネタはなぜ受けるのか』(井山弘幸/DOJIN選書/2007年)
と指摘する。つまりは、一聴すると変で意味が通っていない語も過剰に重ねていくことで笑いに転化される、その謎めいたループ効果こそが漫才における「反復」の力なのだ。
ループを意図的に崩し生まれる笑い
ところが、驚くべきことに、前述した3組はただただ反復を繰り返すだけで漫才を成立させているわけではないのである。
ループするだけがラップミュージックではない。速度を変えBPMを行き来するビート、ラップを通過し旋律を奏でる歌、合いの手を抜き差しすることでつまずくリズム……優れたラップ作品は随所でなんらかのズレを生み、反復構造を意図的に崩す。あるいは再び崩れたループを回復させ、破壊と創造を身をもって体現することでドラマ性を生む。
キミドリ「オ・ワ・ラ・ナ・イ〜OH, WHAT A NIGHT!〜」(『OH, WHAT A NIGHT!』収録)の、断片的なサンプリングの継ぎ接ぎによって甦るめくるめくパーティの記憶。甲高く張り上げる声、粘っこく発音される渋い声、随所で顔を出す黄色い声……それらがキラキラのシンセ音と起伏あるトラックの上で鳴り続けることによって、激しい揺れが起こる。ループに一瞬亀裂が入ること、そのズレを再び、みたび、ループで埋め合わせること。度重なる分裂の発生/回復がなにごともなかったかのように狂騒に回収されるという、強靭な運動神経こそヒップホップの醍醐味なのだ。
同様に、たとえば怪奇!YesどんぐりRPGのズレを観察してみよう。その表現は、かつて身体を大きく駆使しリズム芸を打ち立てたオリエンタルラジオや、短言ツッコミの反復を生んだタカアンドトシらとの違いが明らかである。それぞれがピン芸人らしい独自の笑いで四方八方に拡散しつつ、幾度となく「ムール貝酒蒸しにして~」で収斂されていく、ともに完結と逸脱を繰り返す奇妙な自己再生力──まるで笑い飯のような──こそが光っている。
あるいは、ヨネダ2000のズレは、ズレながらも美的調和を指向する。ネタ中で「彼女の声は美しい」と称されたその“YMCA”のリズムは、寿司の作り方を説明するために一時BPMを極限まで落とし、その後Def Tech「My Way」をサンプリングすることで澄んだユニゾンを聴かせる。物語の展開に引きずられ“YMCA”のビートは回転し、徐々にテンポを速め、まさにラップミュージックに接近するような起伏を構成していくのだ。
もものネタで表現されるズレは、自己言及を孕んだ、さらなる複雑な構造を生んでいる。お互い「せめる。」「まもる。」という名前を宣言した後に、ツッコミで「この人ズレてますよね?」と言い合うふたりは、相方を「〇〇顔」と形容しながら──これもまたヒップホップ的キャラクター性へのアプローチを匂わせる行為だ──スピーディーに攻守を切り替えていく。攻撃する側の担当は、作品のリズムを規定するために冒頭こそ<せめる。せめる。→まもる。まもる。>を×2回繰り返すが、その後は<せめる。→まもる。→まもる。→まもる。>というように攻守のズレが作られ、「この人ズレている」という指摘が漫才そのものによって表現されていく。
2021年に同時多発的に実を結んだ漫才のラップミュージック化──その漸近は、反復によるリズムの生成にとどまることなく、“ズレ”をも捉えながらヒップホップ的律動を育んでいるのだ。背景には、近年勃興している漫才の枠組みを崩すような潮流、コントとのクロスオーバーがあるのは間違いないだろう。と同時に、2019年に『M-1グランプリ』で優勝に輝いたミルクボーイのインパクトも影響源のひとつに挙げられるかもしれない。彼らの作品にこそ、執拗に反復する“型”をベースにしたラップミュージック的構造を指摘できるからだ。
しかし、ミルクボーイが与えた影響はその地点にとどまらない。次回は、ラップミュージックへと接近しつつもラップから離れていくようなミルクボーイの芸当、それらと歩調を同じくする同時代のラッパーについて論じていく。
Chapter4は6月25日発売の『クイック・ジャパン』vol.161に掲載。
(※本連載は偶数回は『クイック・ジャパン』、奇数回は『QJWeb』での掲載となります)