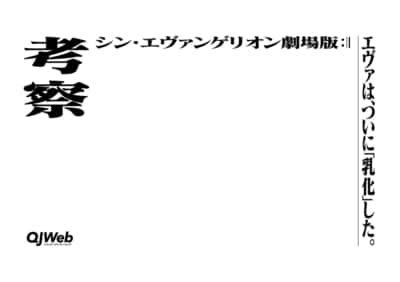加害性との向き合い方
イブキたちシシ組との対比として、ほかの肉食獣たちの“強さ”や加害性との向き合い方を引き合いに出して考えていく。
中でもベンガルトラのビルは、物語にとって非常に重要な役割を果たす。ルイとはまた違った意味でレゴシと対をなすキャラクターといえる。
イヌ科同等にポピュラーな肉食獣であり、身体能力とそれに付随する権威を持つネコ科の大型種、ベンガルトラ。そのオスであるビルは、属性だけで見ればレゴシとよく似ているものの、レゴシと違って特権性を謳歌するスタンスを取る肉食獣らしい肉食獣、本人曰く“陽キャラ”だ。一部の肉食獣の生徒同様、裏市に出入りし、草食獣の肉や血を口にしている。
ただ、彼は社交性の高さゆえ、そうした自身の加害性に完全に無自覚ではいられない。だから彼にとってレゴシは厄介な存在だ。レゴシといると、レゴシのようにある意味でストイックに、高潔にいられない自分の弱さに目を向けさせられ、苛立ちを覚える。レゴシもビルのスタンスを快く思っておらず、演劇部の公演中の一件がいよいよ逆鱗に触れ、大きな衝突が起こる。かくして2匹は、イヌとネコなのでややこしいが犬猿の仲となる。
ただ、ビルはビルなりに自身の加害性との向き合い方についてポリシーを持っている。自身が草食獣の肉を食うからこそ、演劇部の仲間などの身近な草食獣は大事にすると決め、率先して危険から守る。そうした場面を経験するたびに、ビルの中に次第に特権性を持つ者としての責任感が芽生えていく。特に大きな成長の転機となる「ショック卵」の回は、作中でも屈指の名エピソードといえる。

レゴシも次第に彼のスタンスに一定の評価を下すようになり、物語終盤にかけて「お前はよくやってる」と労いの言葉をかけていることからも、物語側がビルのスタンスもまたひとつの選択肢たり得ると認めていると取れる。
もう1匹、ヒグマのリズについても触れておきたい。
彼の加害性との向き合い方は特にひどく歪んで、不条理なものとして描かれる。彼はレゴシ同様に無害であろうと努めてきたが、レゴシと違って踏み留まれず、食殺を犯してしまう。
一部のクマ科はあり余る腕力を抑制するために、薬の服用を義務づけられている。リズもその1匹で、本来備わっている力も、薬の副作用による強烈な不快感もひた隠しにして、無害で気のいい「穏やかなクマさん」を演じなくてはならないことにやり切れなさを抱えていた。
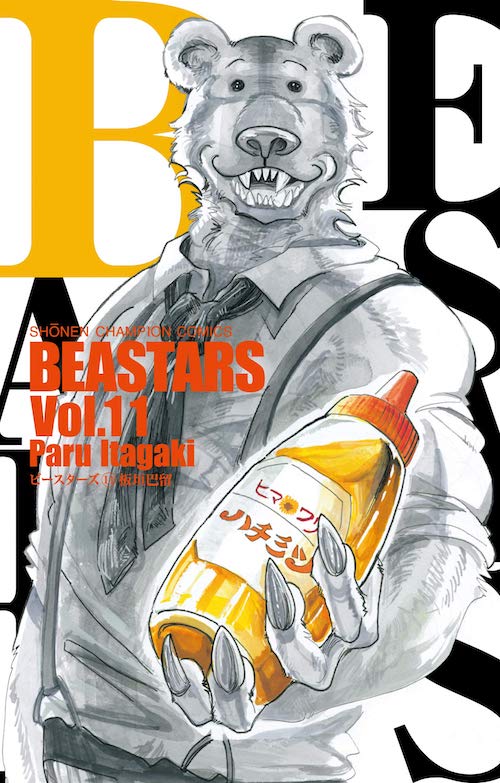
そんななか、ふとした瞬間にテムからかけられた「リズってなんか怖いよね」という言葉が彼の本質を見抜き、気持ちを楽にさせる。そして、部員たちと一線引いて付き合っているスタンスをも「高い目線はやっぱり心細い?」「いつもどんなこと考えてるの?」と指摘し、歩み寄り、自己開示を求められる。リズはそれを「言葉の抱擁」と表現した。
それを受けてリズは、薬で力を抑制していることを打ち明け、唯一自分を偽らずにコミュニケーションできる相手としてテムと深い仲になっていく。このテムからの受容はリズにとって許しや救いであり得たのだが、受容は蜜の味、正しい認知がなければ曲解からの暴走を生む。
リズはテムとの問答によって自身の加害性を正しく認められるようになっただけで、加害性を行使する許しを得たわけではない。その思い違いを発端として、リズとテムの関係性が悲しい結末を迎えてしまうことは、リズのしたような認知が正しいものではないと作品側が示唆しているように感じられる。
テムの食殺は、リズが自身の弱さをさらけ出す機会を得られてこなかったがゆえに起こったといえる。それは人間社会でも同じことで、シシ組に表象されるような「有毒な男らしさ」に類するものに苛まれても、それを吐き出す場がないことでさまざまな機能不全が社会に生じている。社会の側に男たちが弱さを吐き出す場がじゅうぶん用意されておらず、それが常態化してきたことで、自分の中にある社会的に弱さや汚点とされる部分について自己開示する習慣がつきにくくなっている。
たとえば海外ではアルコール依存症の患者や犯罪被害者、DV加害者といったさまざまな属性の人々が自身の内面を語り合い聞き合うピアカウンセリングという手法が根づいている。映画やドラマで、椅子で輪を作るように座って自身の体験を順に語っていくシーンを目にしたことのある人もいるだろう。こういった組織だった会を設けることは難しくとも、個々人が日常的に弱さを打ち明ける場を設けるよう努め、リズと同じような悲劇を生まないように暮らしていくことが、この作品への読者からの真摯な返答といえるのかもしれない。