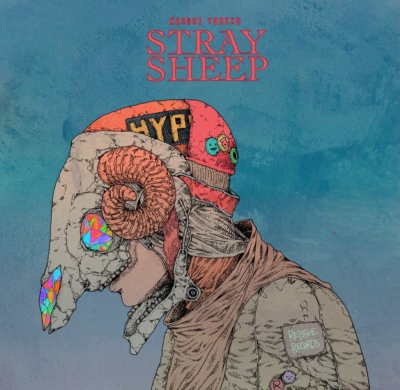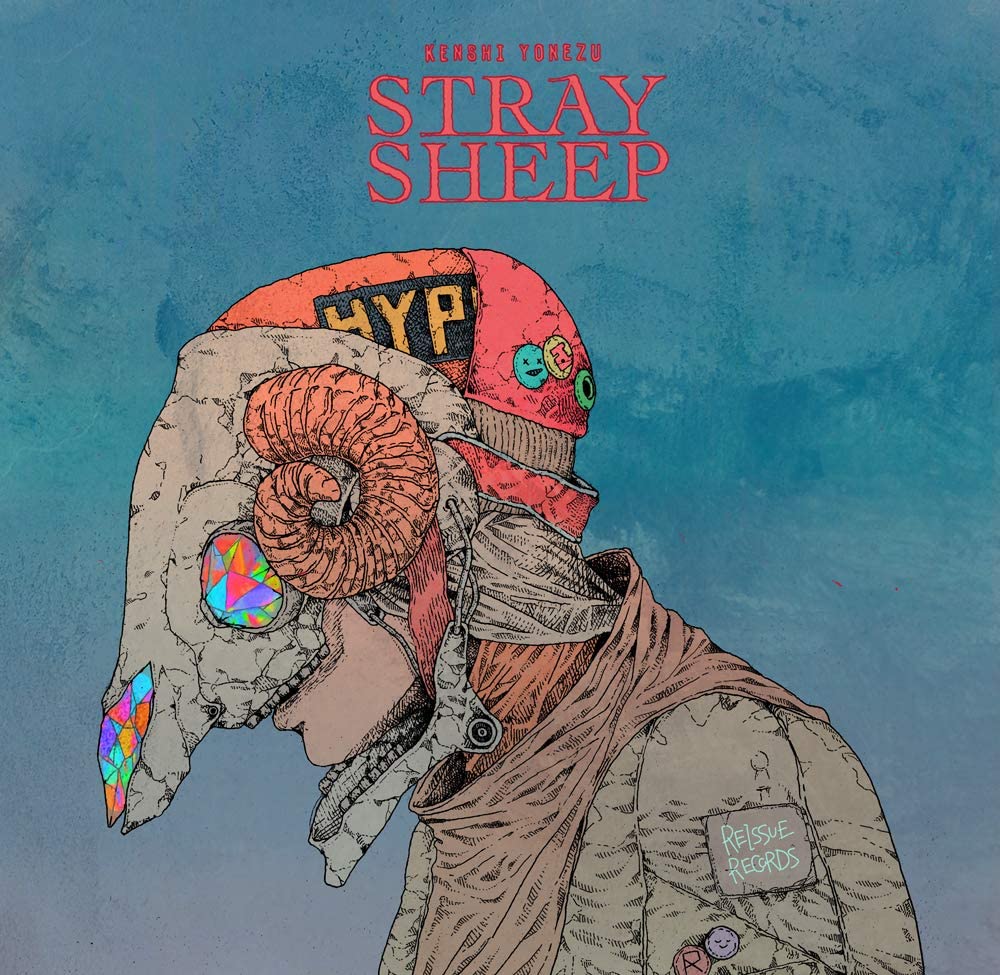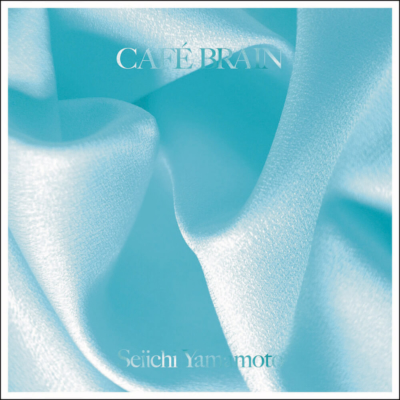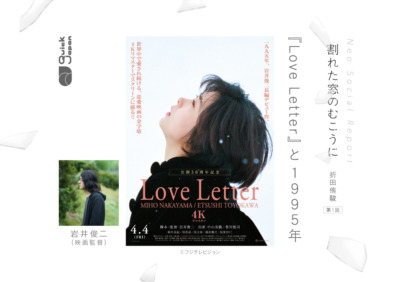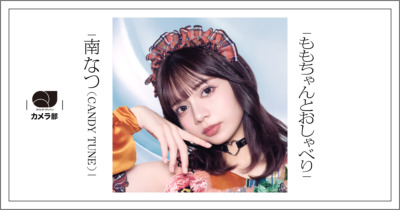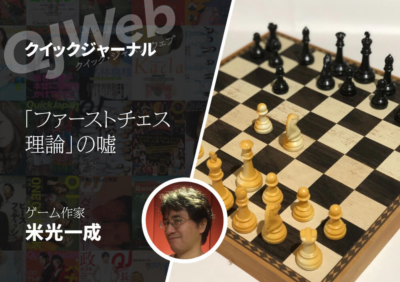“声の拡張”の先にある『STRAY SHEEP』はいまだ通過点なのか?
前作『BOOTLEG』では、メロディの起伏や緩急はより豊かになった(「orion」の歌メロのダイナミックさ!)ものの、米津のヴォーカル自体に大きな変化があるわけではないように思う。むしろエレクトロニクスの比重が上がったサウンドに惹かれるアルバムだ。しかし、初音ミク、池田エライザ、菅田将暉といったフィーチャリングヴォーカルの存在は、米津玄師作品における声の拡張として捉えることもできるだろう。また、「Moonlight」「fogbound」でピッチシフトされた自身のヴォーカル、また最終曲「灰色と青」における、プリズマイザー的なコーラスといった、効果的に変調された声の活用は注目すべき点だろう。いわば、シンガーとしての声を確立したあとの模索がここには聴き取れる。
そう考えると『STRAY SHEEP』に聴かれるチャレンジはおよそ『BOOTLEG』までの延長線上にあるといえる。しかし、前作ではバッキングのコーラスに用いられるに留まったプリズマイザーが「海の幽霊」で歌メロを覆い尽くし、幽霊のように米津の声に憑依している様には、ひとつの壁をぶち抜いたようなインパクトがある。ほかにも同様の変調された声は本作の至るところに聴き取れ、たとえば「まちがいさがし」のセルフカバーでもサビ前の印象的な一節で同じエフェクトが活用され、自らの声のひとつの表現として活用していることも窺える。また、「優しい人」で聴かれるファルセット(への移行)の柔らかさを始めとして、着実に歌唱のスタイルが確かさを増しており、米津のキャリアを声の観点から振り返った場合の「集大成」を随所に感じるアルバムである。もう一点、「Flamingo」や「Lemon」に聴かれる歌ならざる声(鳴き声を含む)の侵入が、本作初出の「感電」にも現れるのは興味深い。
本作は以上のような観点から集大成のような性格を持つが、同時に新しいフェーズを感じる作品でもある。「海の幽霊」以降タッグを組む坂東祐太のコアレンジ(共同編曲)やストリングスアレンジは、本作の聴きどころのひとつ。アフロビーツ調に更新された「パプリカ」をはじめとしたエレクトロニックなサウンドから「感電」のファンク、そして何より「海の幽霊」での、坂東率いるEnsemble FOVEによる演奏も印象的な、エレクトロニックとアコースティックの巧みな融合は本作のハイライトである。
が、もともと「海の幽霊」以来米津と坂東のコラボレーションに期待をかけていたとはいえ、本作にはちょっとした困惑を覚えていたのも正直なところだ。具体例を挙げると、「感電」にはいまいち乗れなかった。何かちぐはぐな印象が拭えなかったからだ。たとえば、楽曲を貫くグルーヴとメロディの動きがどこか噛み合わないような。しかし、特にサビ後半の「稲妻の様に生きていたいだけ~」のくだりでの、米津のヴォーカルとストリングスのなめらかで優雅な流れが際立つのは、このアレンジゆえのこととも思う。そこには、違和感と快感が同居したむずがゆいスリルがある。それが狙いなのか、単に自分の趣味がそう思わせているだけなのか、未だに判断がつかずにいる。
シンガーとしてのひとまずの完成に辿り着き、新たなコラボレーターを得て制作された本作。数字の面から見てもクリエイティヴな面から見ても、キャリア上重要作となるであろうことは間違いない。とはいえ、どこか歪(いびつ)さを湛え、特にアルバムとして考えたときに潔く傑作というには躊躇するところもある。そうしたアンビバレンス――最大の成功がある種の掴みどころない逡巡のもとにある――もまたポップの宿命なのかもしれない。ようやく道具を使いこなし出した、その次の段階とはいかなるものだろう、と想像がふくらむ。