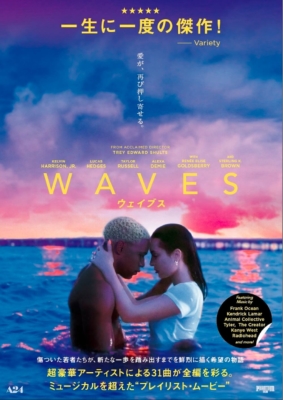幅広いリスニングの経験と音楽を熟聴する力を持った監督
おもしろいのは、ラップやR&Bと並んでオルタナティブミュージック/インディロックが重用されている点。レディオヘッドの「True Love Waits」はとても重要な場面で象徴的に使用されているし、ファック・ボタンズ(ブリストルのエクスペリメンタル・エレクトロニック・デュオ)の未来的でノイジーな「Surf Solar」を不安感を煽るシーンに寄り添わせたかと思えば、キリキリとした緊張感を強調するためにコリン・ステットソン(モントリオールのサックス奏者。ボン・イヴェール作品への参加でも知られ、映画やドラマの劇伴を多数制作している)のミニマルでダークな「The Stars In His Head (Dark Lights Remix)」が印象的に使われている。
おもしろいことに先述のテーム・インパラ「Be Above It」のシーンは、スタジオ版とライブ録音がミックスされているという。既存の楽曲を映画で使用する、というのはもちろんありふれたことだが、映画のためにスタジオ版とライブ版をミックスしてしまうなんて、前代未聞の試みだ。
さらにリミックスバージョンを使ったり(「Be Above It」はエロル・アルカンによるリミックスがもう一度登場する)、曲のテンポを落としたり(ケンドリック・ラマー「Backseat Freestyle」)、わざわざリマスター版を使用したり(フランク・オーシャン「Mitsubishi Sony」)、リリース前のライブ配信で見つけたというインストゥルメンタル版を持ってきたり(フランク・オーシャン「Rushes」)……。

とにかくシュルツは、その楽曲の意味やムードだけでなく、音そのものにものすごくこだわっている。これほどまでの強いこだわりは、先に挙げたタランティーノやライトのような映画と音楽を同期させた作品を撮る作家たちとも異なる個性だ。端的に言って、新しい。
これらの音楽の使い方はシュルツが単なるラップファンやインディロック好きではないことの証しとなっているし、幅広いリスニングの経験と音楽を熟聴する力、そして想像力を持っていない限り、こういった音楽と映像との組み合わせを発想することすらできないだろう。単純に、選曲だけをとってもほかにない個性を発揮している(ひとつよけいなことを書くと、シュルツの趣味はちょっと「Pitchforkっぽい」のでとても共感する)。
シュルツは脚本のシノプシスを執筆する段階から最後の仕上げまでに、プレイリストの選曲や歌詞の書き込みを行っているという。さらに台本には曲へのリンクを付して、俳優たちにその場面を説明するのだとか。

であるからこそ、映画を通して音楽がないシーンは少ない。ひたすら音楽が鳴り響き、別々の曲がシームレスにつながれるところもある。なので、音楽が鳴っていないシーンを目にすると落ち着かない気分になる。なんとも不思議な映画だ。
関連記事
-
-
Furui Rihoが『Letters』で綴った“最後の希望”「どんなにつらい日々であっても、愛は忘れたくない」
Furui Riho『Letters』:PR -
4年目の今、重荷だった「王子様」を堂々と名乗れる。Last Princeが語る、プリンスを背負う勇気と楽しさ
Last Prince:PR