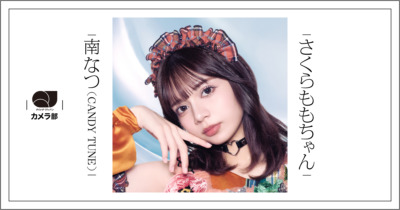自主制作映画のコンペティションとして42年の歴史を誇る「ぴあフィルムフェスティバル」。“新人監督の登竜門”と呼ばれ、これまでに『害虫』の塩田明彦、『愛のむきだし』の園子温、『百万円と苦虫女』のタナダユキ、『溺れるナイフ』の山戸結希ら数多くの優れた映画監督を輩出してきた。個人的な思いや情熱をスクリーンに託した「自主映画」の一本一本と向き合い、真摯に評価してきた映画賞である。
そして2019年、495本の応募作の中から審査員の満場一致でグランプリを獲得したのは中尾広道監督『おばけ』だ。監督・脚本・撮影・編集・録音をほぼひとりで手がけ、映画制作に取り憑かれた自身の姿を映した異色のセルフ・ドキュメンタリー。わくわくするようなストーリーもなければ、今をときめく美しい俳優も登場しない。スクリーンに映るのは、ひとりで撮影に没頭する孤独な男の姿だけ。それでもこの作品に心を揺さぶられるのは、彼が「映画」という壮大な文明にたったひとりで戦いを挑んでいるからだ。
※6月19日追記:緊急事態宣言の自粛要請に伴い、当初4月を予定していた劇場公開が延期されていましたが、7月11日(土)からポレポレ東中野で公開されることが決定しました。
途方もない制作プロセスからにじみ出る映画愛

中尾監督は8年ほど前に友人の映画撮影を手伝ったことがきっかけで、自主映画の道に進んだという。「誰かと一緒にやってもケンカしてしまうから」といっさいスタッフを雇わず孤独に映画と向き合う彼の作品づくりは、本人の言葉を借りれば「映画を探すこと」だ。
たとえば『おばけ』においても、三脚で固定したカメラの前を自転車で駆け抜ける場面では、ひとりで何度もテイクを重ね、モニターで何度も映像を確認し、ようやくひとつの「映画らしい」カットができあがる。そんな単純な映像のなかに、中尾監督は自身が理想とする「映画」の姿を探し求めている。だからこそ執拗なまでにモニターをチェックし、自らの足でフレームインとフレームアウトを繰り返す。
現代の映画では、当たり前のように使われる単純な技法に過ぎない。しかし、たったひとりでは1分の映像を仕上げるまでにどれだけの時間と労力を要することか。本作には、そんな途方もない映画制作のプロセスと真正面から格闘している中尾監督の姿が収められている。その繰り返しの果てににじみ出る彼の深い映画愛こそが最大の魅力と言えるだろう。
金属バットが軽妙な関西弁で、観客の声を代弁
広大な森の風景を捉えるロングショットから自身の心情を映し出すクローズアップにいたるまで、彼は映像表現の細部にわたって心血をそそぐ。フィクション、ドキュメンタリー、オーディオコメンタリーなど、演出の手法も自由自在だ。中尾監督は、これまで映画が発明してきたさまざまな映像表現を自身の作品に注ぎ込む。まるで映画の歴史そのものを分解し、自らの手で再構築していくかのように。

そんな中尾監督のストイックな姿にオーディオコメンタリーのように軽快なツッコミを入れるのが、「宇宙の星たち」という不思議な役どころで登場するお笑い芸人・金属バット。何度もテイクを重ねる中尾監督に対して「さっきと一緒やろ」「一緒やな」と、軽妙な関西弁のやりとりで観客の心の声を代弁してくれる。ふたりの視線は撮影現場を見つめるプロデューサーのようでもあり、私たちと同じく純粋に映画を楽しむ観客のようでもある。
異常なまでに制作に没頭する中尾監督に茶々を入れつつも、彼らの言葉にもまた映画への愛が宿っていた。そして本作をつらぬく「映画愛」は、星たちの軽妙な会話をきっかけに壮大な宇宙空間へとアプローチしていく。