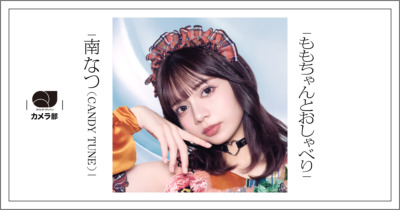『ルポ 川崎』などの著書を持つライターの磯部涼が、毎月「音楽のなる(鳴る、生る、成る)場所」を取材し、思考する連載。4年ぶりの最新第2回。
2024年2月19日、BAD HOPの解散公演、東京ドーム。
彼らに初めて取材したのは2014年5月、最初のミックステープ『BAD HOP ERA』を自主制作して間もない頃。翌年、自分は『ルポ 川崎』という連載を始め、ぱっとしないライターの自分にとっては珍しくヒット作となった。しかしBAD HOPは、それとは比べ物にならない勢いで売れていった。
「川崎区で有名になりたきゃ/ひと殺すか ラッパーになるかだ」(「Kawasaki Drift」)その後の10年──。
2024年2月19日、BAD HOPの解散公演当日
長い列がようやく入り口に辿り着くと、目に飛び込んできたのは血溜まりだった。トイレの手洗場のひとつで水が流しっ放しになっていて、赤く濁った水が泡立つ。その前には若い男性が立ち、鼻から鮮血が流れ出る様子が鏡に映る。彼の手にあるのはかつてティッシュペーパーだった塊。それを絞っては顔にあてるが、とうに吸水力は限界を超え、役に立っていない。経験上、血液の量からしても自然に出たわけではないだろうな、と思う。ただすぐに医療処置が必要なほどの状態にも見えなくて、むしろ彼の、周囲を気にする素振りが痛々しかった。5年半前、日本武道館のトイレの入り口、上下ジャージ姿で脇にセカンドバッグを挟み、両手でタオルを持って直立不動、通りすがりのひとたちにくすくす笑われていた若者の無表情を思い出す。
2024年2月19日。BAD HOPの解散公演当日。朝から空はどろどろとした雲に覆われていて、雨は午後には弱まったが、地下鉄・水道橋駅から東京ドームの前に出た途端、土砂降りになった。全国より一張羅で集まった若者たちが悲鳴を上げ、走り出す。ずぶ濡れで関係者受付に辿り着くと、そこはいかついひとたちでごった返している。人混みの中に川崎から沖縄へ飛んだと聞いていたA君の姿を見かけた。帰ってきていたのか。その時、目の前の男性が受付の担当者に向かって、オレのゲスト枠はどうなっているんだと怒鳴り出した。気を取られている内にA君の姿は消えていた。
ライヴの終盤、BAD HOPのリーダー格である双子の片割れ=YZERRは言った。「オレたち、ほんとガキの頃から一緒で。まさかこんな、東京ドームに立てるなんて思わなかった」。2時間半、熱狂し続けていた5万人が静まりかえる。「最後にひとつだけ言わせて欲しいんだ。なんかいろんなもん抱え込んでる奴とか。クソみたいな環境で生まれた奴とかたくさんいると思うんだよ。『あぁ、オレたちはこのままでは抜け出せない』とか。オレも地元で貧困ばっか見てきて。まともになれた奴なんて少ねぇけど。全員にひとつだけ言いてぇのは。BAD HOPはここに立っているっていうこと。それだけは忘れないでくれよ」。
そして彼は叫ぶ。「オレたちがどっから来たか知ってんだろ!」。歓声が渦巻く中、サウンド・システムのキャパシティを超えた地鳴りのようなビートが響く(*1)。「川崎区で有名になりたきゃ……」。双子のもうひとり、T-Pablowは彼らのキャリアを代表するラインを観客に歌わせる。「ひと殺すか、ラッパーになるかだ!」。ふと思う。さっき鼻血を流していた若者は、川崎から飛んだA君は、いまどんな気持ちでこの光景を観ているのだろう。あるいは5年半前の武道館公演の際、トイレの前で見かけた若者はここにいるのだろうか。
2014年5月、BAD HOPへの初取材
東京ドームでのBAD HOP解散公演の約1ヶ月前、メンバー=8人にインタヴューをする機会を得た。彼らがラスト・アルバム『BAD HOP』の配信と同時に配布を計画していた『BAD HOP MAGAZINE』のために依頼された企画で、結局、同誌はアルバムのCD版や東京ドーム公演を収めたDVDとのセットという形で、オフィシャル・サイトでの販売が始まっている(*2)。スタジオで半日かけて、撮影と並行しながら代わる代わる立て続けに話を聞いていくという過酷な仕事だったが、それは解散前の彼らに対面する最後の、貴重な場となった。
BAD HOPに初めて取材したのは2014年5月、彼らが最初のミックステープ『BAD HOP ERA』を自主制作して間もない頃だ。
地元=川崎市川崎区の工場地帯でのハードなライフ・スタイルを描写するヒリヒリとしたラップは、まるで日本のアンダークラスの現状をまだ10代の若者たちが告発しているようで衝撃を受け、すぐにインタヴューを申し込んだのだった。
頭上を飛行機が行き交う工場地帯に程近い公園に集合してくれた彼らは、「あとで録音データを聞き返した時に発言者が誰だか分かるようにまずは自己紹介を」とお願いすると、誰かが照れ臭そうに「ヨーヨー、オレは……」とフリースタイルを始め、別の誰かが「いや、ここは普通に名前を言えばいいんだろ!」と突っ込んで、皆で爆笑するぐらいまだ取材に慣れていない、一見、普通の若者たちだったことが印象に残っている。しかしそこで聞いた結成に至るまでの話はラップと同様、実に生々しいものだった。以来、定期的に取材をするようになり、翌年に連載を始めた『ルポ 川崎』(*3)へ繋がる。同企画はぱっとしないライターの自分にとっては珍しくヒット作となったが、BAD HOPはそれとは比べ物にならない勢いで売れていった。
10年後。インタヴューのロケーションは工場地帯の公園から恵比寿の撮影スタジオへと変わり、彼らは史上初、東京ドームでライヴをするラップ・グループにまでなった。もちろんグループを巡る状況は相変わらずトラブル続きで、取材当日も前年秋に勃発したビーフがまだじゅうじゅう音を立てている頃だった。その話題を振ると、T-Pablowは急にギアを上げるように熱くなったが、すぐに冷静さを取り戻し、いまは諍いがある人たちも、自分たちと同じように日本のヒップホップを盛り上げてきたという点で敬意を払っている、と。一方、YZERRは不敵な笑みを浮かべながら、BAD HOPが言われっぱなしで解散公演を迎えるのは嫌なのでやり返して欲しいというファンも多いし、それならそうしてもいいかな、と語った。ビーフに対するアンサーソング「guidance」(*4)がまずBAD HOPのラジオ番組で公開されたのはその約1週間後のことだ。
(*2)https://badhopofficial.com
(*3)https://www.shinchosha.co.jp/book/102841/