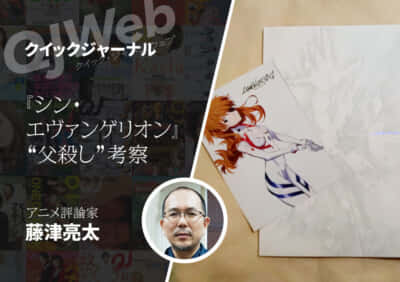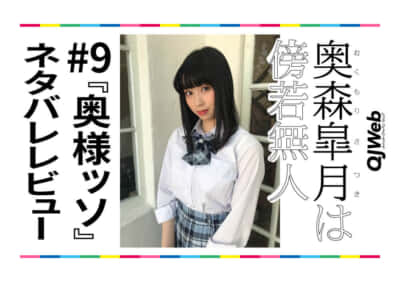ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まり、毎日毎時、言葉を失うようなニュースが流れてくる。アニメ評論家・藤津亮太は、2月21日に開かれた国連安全保障理事会の緊急会合で演説したケニアのキマニ国連大使のロシアの軍事行動を明確に否定する言葉に『太陽の牙ダグラム』(1981年)の登場人物の言葉を重ねた。あれから世界は進歩していると信じたい。
キマニ大使の言葉から想起したサマリン博士
政治とは言葉である。
ロシアのウクライナ侵略を報じるニュースに触れながら、日々その思いを強くしている。自らの正義を訴える言葉がさまざまに飛び交っている。人間は自らのよって立つところ、どこへ向かうかを説明し、仲間を増やすには言葉を使うしかない。
なかでも、強く印象に残った言葉は、2月21日に開かれた国連安全保障理事会の緊急会合でケニアのキマニ国連大使が行った演説だった。
キマニ大使は演説で、アフリカの国境線がかつての帝国主義による分断の結果生まれた一方的なものであることを改めて指摘し、国境線を超えて「同胞と一緒になりたいと思わない人はいないし、同胞と共通の目的を持ちたいと思わない人はいない」とその思いを語った。そしてその上で「しかし、そのような願望を力ずくで追い求めることをケニアは拒否する。私たちは、二度と支配や抑圧の道に陥ることなく、今はなき帝国の残り火から、回復を遂げなければならない」と、ロシアの軍事行動を明確に否定した。
※演説の翻訳は毎日新聞の報道による(2022/2/23「ウクライナは「私たちの歴史と重なる」 ケニア大使の演説に高評価」)
キマニ大使の演説には、人類が歩んできた歴史の過ちとそこから何を学んだかということが凝縮されて語られており、どのような未来を目指すべきかが端的に語られている。
キマニ大使の語る「私たち」という主語は、第一にケニア国民を指すのだろうが、そこには同時に帝国主義に侵された苦難の歴史を持つアフリカの人々を含み、さらにいえば人類全体にも当てはまり得る普遍性を持ったものだった。「私たち」の主語が大きいというより、「今はなき帝国の残り火から、回復を遂げなければならない」という“述語”の射程の範囲が大きいのである。
政治の言葉の多くは、自らのバックにある組織(例えばそれは政党や国家や民族だったりする)の枠組みに縛られるが、そういう意味ではキマニ大使の言葉は大きく「人類」という枠組みを見据えたものになっていた。
キマニ大使の言葉は僕に、デビッド・サマリン博士の言葉を思い出させた。サマリン博士は、歴史学者であり、植民惑星デロイアの独立運動指導者を務めた。1981年から放送された『太陽の牙ダグラム』の登場人物だ。
『ダグラム』の主人公はクリン・カシムという少年。彼は地球連邦評議会議長(地球連邦の実質的最高権力者)のドナン・カシムの三男だが、ドナンの植民地政策に反発を感じ、デロイアの独立運動に身を投じることになる。その独立運動の指導者——軍事面の指揮もとらなくもないが、理論的指導者の側面が強い——がサマリン博士である。つまりサマリンはクリンのもうひとりの“父”ともいうべき存在だ。
クリンはこのふたりの“父”の影響の下で生き、親離れをしていく。最終回で武装解除を受け入れる時、自らの愛機である戦闘用ロボット(コンバットアーマーと呼称される)のダグラムを自らの手で破壊するのは、まさに「移行対象」との決別だ。移行対象とは、もともと子供が乳離れする時に、母親代わりに愛着の対象となるぬいぐるみや毛布などを指す言葉。児童文学などの世界では、これをもうちょっと広くとらえ、思春期などの親離れの時に主人公の側に現れる人間でない存在なども指すことが多い。移行対象は乳離れの文脈で言及されることが多いが、『ダグラム』の場合は父離れの物語が背景にあるのが特徴的だ。
ドナンはなぜデロイア独立を認めないのか
そもそも地球連邦とデロイアの対立は次のような構図で描かれている。
地球連邦がワームホールの先にあるデロイアを植民星として約130年。現在、地球は食料資源の40%、鉱物資源の80%をデロイアに依存するようになっている。地球の生命線となったデロイアはそれ故に自治権を認められず、地球連邦軍の第8軍から行政官が選出され統治にあたるという体制だった。このような状況で、民族資本も成長してきたデロイアに独立の機運も高まるのは当然だった。
では、ドナンはなぜデロイア独立を認めないのか。大きい柱になるのが「ひとりではできない喧嘩もふたりならできる」という論理。さまざまな歴史の果にようやく地球連邦という統一政府を達成したにも関わらず、デロイアが独立をしたら、再び対立関係が生まれ星間断絶になる未来も考えられる。それはデロイアが地球の生命線である以上認められない。
また秘密情報ではあるが、デロイアを足場にすれば同じ星系内の別惑星を開発することが可能であることが確認されていることも大きい。デロイアがここの開発を主導すれば、植民星と地球は2対1の関係となり、地球はさらに不利になる。
そこでドナンは、第8軍の大佐でデロイア出身のフォン・シュタインを自らの傀儡としてデロイア代表に据え、デロイアを8番目の自治州として認める形でガス抜きを行った。そしてその一方で、反発する独立派の取り締まりを強化した。
ドナンの政治姿勢は、地球連邦に属する48億人の生活と未来を安泰なものにするためという大前提があり、そのための必要な犠牲としてデロイア人を位置づけるというものだ。
当然ながらサマリン博士は、そこに対して「地球とデロイアは対等の関係であるべきだ」という政治姿勢をとっている。
しかしサマリン博士の政治姿勢は、それは単にデロイアに正当で平等な地位を与えるべき、という考えにとどまるものではなかった。そこに彼のユニークさがあるが、おそらくそのことを理解していた人物はデロイアの人民解放軍にもいなかったのではないか。
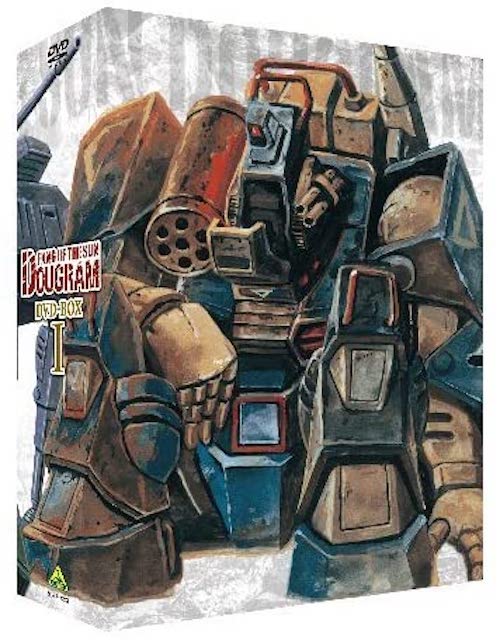
「人類」という概念の枠組みをアップデート
人民解放軍が優勢となっていく過程で、サマリン博士を中心とする主戦派とヘシ・カルメルを中心とする和平派の対立が深刻化する。そしてサマリン博士は軟禁され、カルメルを中心に地球連邦との和平が進められる(これは連邦側の策略でもあるのだが、ここでは細かくは触れない)。その偽りの和平に反発したクリンたちは、サマリン博士を奪還し、戦闘を続けようとする。しかし、サマリン博士は若者の未来を守るため、一命を賭して治安軍(人民解放軍から改められた)の攻撃を止める。その上でクリンたちにも武装解除をして、未来に生きろ、と説得する。
亡くなる直前サマリンは次のようなことをクリンたちに語る。
「私はこのデロイアを、地球とは違う人間社会にしたかった。だが、それにはあまりにも地球の生き方、考え方に毒され過ぎていることに気づいた。」
「しかし私はまだ、絶望はしていない。君たち若者が、私達にはできなかった新しい人間社会を作ってくれると私は信じるからだ」
「私がダグラムに、デロイア人ではない地球人であるクリン君に乗ってもらったのも、新しい人間関係を作りたかったからだ。ダグラムにデロイア人が乗れば、デロイア人というだけで戦える。だがクリン君が乗れば、同じ地球人に銃を向けることになる。迷いも痛みもきっと生まれるだろう。しかし、それを乗り越えてこそ、真の敵は何か、真の道は何かを知ることができるのだ。」
ここでサマリン博士が語っているのは、デロイア独立を通じて「人類」という概念の枠組みをアップデートしたかった、ということだ。「地球人類」は他者を持ったことがない。しかしデロイアが独立して「デロイア人」という他者が成立したとすれば、その他者との対話(そこには衝突も含まれる)を通じて、新しい倫理・新しい政治が形作られるはずだ、と。そこにサマリン博士は人類の希望を見ていたのだ。ドナンの言葉は、デロイアという新しい環境も含めて旧来の「地球人類」の枠組みで語っているのに対し、サマリン博士は「地球人類」と「デロイア人類」のふたつを大きく統合する「人類」というものをイメージしている。
そう考えると、第9話でドナンとサマリン博士が対面した時、サマリン博士が「あなた過去から学ぶのが歴史だと思ってらっしゃる。それも大事だ。だが私の歴史は未来です。(略)過去に人間が果たし得なかったものを作るのです」とドナンに応じた理由もよくわかる。サマリン博士はこの時、「あなたが過去の歴史を代表しているように、彼(クリン)は未来を代表している」とも語っている。
人を殺す言葉があるということは
『ダグラム』の監督・原作の高橋良輔は、アニメのいいところは、実写だと気恥ずかしくて言えないようなことを正面から描くことができる点と話していた。最終回のサリマン博士の、未来への希望などその典型といってもいいだろう。
目の前の問題から始まり、最終的に「人類」という大きな枠組みへと視野を広げてくれる言葉。その点でキマニ大使の言葉とサマリン博士の言葉と重なって見えたのだ。これと対比するとロシアのプーチン大統領の言葉は明らかに「過去」に属した言葉で出来上がっている。
小説家の高橋源一郎は『ことばに殺される前に』(河出新書)の表題エッセイの中で、カミュを引きながらこう記している。
『ことば』は人を殺すことができる。だが、そんな『ことば』と戦うことができるのは、やはり『ことば』だけなのだ。
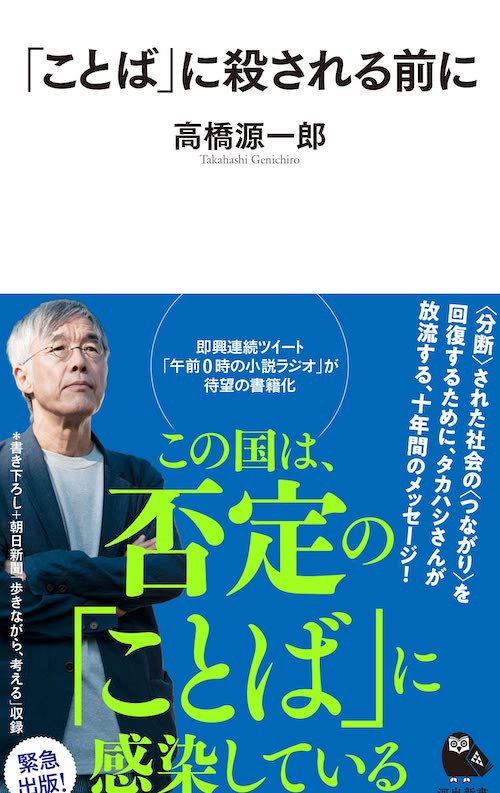
政治は言葉だから、人を殺す言葉があるということは、つまり人を殺す政治、人を殺さざるを得ない政治がそこにあるということだ。ならば、そんな言葉を打ち消すような、「新しい人間社会」を目指す言葉もまた必要なはずだ。サマリン博士の言葉が発せられたのは1983年。それから40年弱経ち、今は「人類」という大きな主語を使っても、かつてほど気恥ずかしくはならない程度に世界は進歩したはずだ。そう信じたい。
関連記事
-
-
浅野いにお×内田怜央(Kroi)の共鳴する“反骨精神”。新しい世界を構築するため、ぶっ壊したいもの
Kroi『Unspoiled』:PR