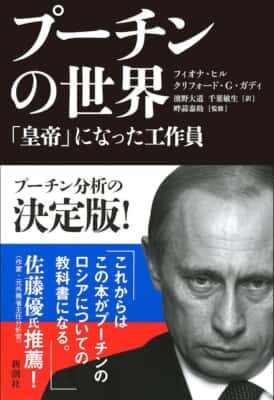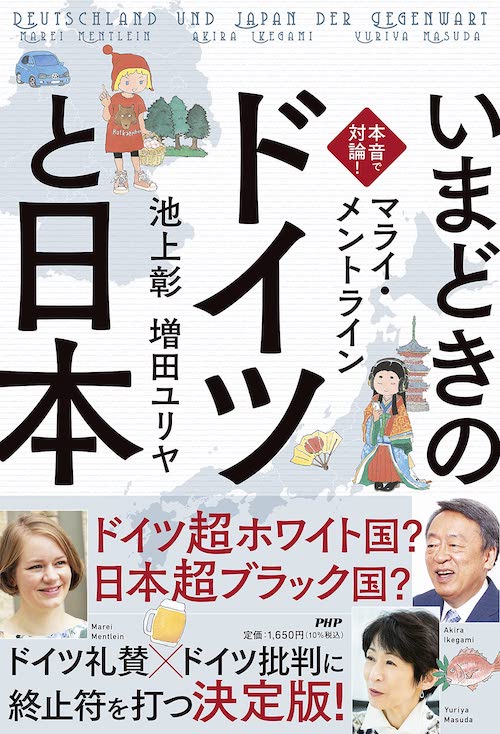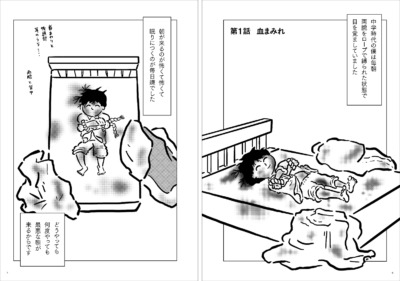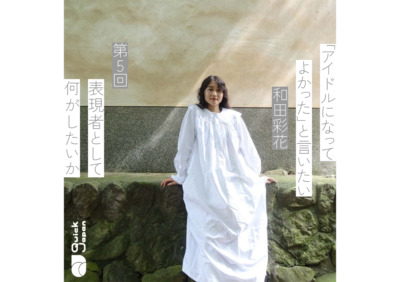平和の祭典「北京オリンピック」が開催される一方で、緊迫するウクライナ情勢。ロシアがウクライナへの軍事侵攻に踏み切ったら、世界を巻き込む大惨事になってしまう。「軍用ヘルメット5000個提供」のニュースで世界をざわつかせたドイツの真意とは? 日本在住ドイツ人、マライ・メントラインが「意外なほどに潜在的プーチン支持・擁護のマインドが強い」現代ドイツ社会を分析する。
目次
ロシア依存のシステムがそのまんまな理由は?
ウクライナ危機にしろ何にしろ、ロシアが仕掛ける西欧への各種の揺さぶり策に対して「いちおう西欧のボス」みたいな立場にいるドイツは、世間的な期待水準に比してどうにも消極的というか弱腰というか、煮え切らない態度を示すことが多いです。その理由については「天然ガスなどエネルギーの輸入元としてロシアを強く頼っているから」という根拠からさんざん説明されているのですが、
そもそも何故そこまでロシア依存のシステムになったのか? ていうか、急所を握られながら何故そのまんま状態でいるのか?
という、より重要な点についてはろくな解説がないまま毎日が過ぎています。この状況はイマイチだよなということで、先日「JAM THE PLANET」(J-WAVE)というラジオ番組でいろいろ語ったのですが、語りきれるわけもないので今回この記事にまとめなおしてみようと思う所存です。
中東への依存すなわちアメリカ合衆国への従属
「ドイツをロシア・エネルギー依存体質にさせる」ロシア側からのアプローチとして、表面的には大物政治家や社会的キーマンの買収が目立つところです。SPD(ドイツ社会民主党)で政権を担ったゲアハルト・シュレーダーが首相退任後、ロシアのエネルギー産業の取締役に就任し、天然ガスパイプライン「ノルドストリーム」などの運営に様々な便宜を図った(そして輸入天然ガスの55%がロシア産となるに至った)事例はその代表的なものでしょう。しかし、それだけで依存体質が定着・継続するものではない。もっと広範な「潜在的合意」につながる社会的マインドが必要であり、実はその点が日本ではあまり、というかほとんど知られていません。
まず、いまドイツ社会や世論の主導権を握っているのは(これはどこの国でも同様かもしれないが)50歳代の「冷戦末期~ポスト冷戦初期」に価値観の原型がある世代で、彼らにはエネルギー調達問題にて、いわゆる中東産油国に依存したくない!という地味ながら強固な意識があります。なぜなら中東への依存はすなわちアメリカ合衆国への従属につながるからで、政治的にも社会文化的にも「それはイヤ」という感覚がおそろしく根強い。また、伝統的に中東諸国との折衝はめんどくさくて厄介というイメージがあり、それだったら、文化・対話基盤の共通性が高い(とドイツ人は思っている)ロシアのほうがまだいいじゃん。経済的な相互依存関係も深いし。こちらが弱みを握られる代わり、向こうの弱みも握っているから「もし何かあってもなんとかなる」だろう、という理屈があるのです。個人的にそれはロシアとプーチン政権を甘く見過ぎている気もするのですが、冷戦とポスト冷戦の外交・経済関係の積み重ねがそういう認識を生み、現在に至るのです。
潜在的プーチン支持・擁護3つの要因
この「冷戦末期~ポスト冷戦初期」的な記憶というのはなにげに大きなポイントで、ロシア側に目を転じてみるとたとえばフィオナ・ヒルの名著『プーチンの世界』で強調されているように、プーチンの対欧米強硬路線を支えているのは旧ソ連ブロック解体への危機感だけでなく、冷戦終結後の混乱期に西側の政治家や企業家に騙されて相当ひどい煮え湯を呑まされた怨念だったりもするわけで、そのへんの「物語」は実は、ロシアでもドイツでも今なお現役稼働しています。
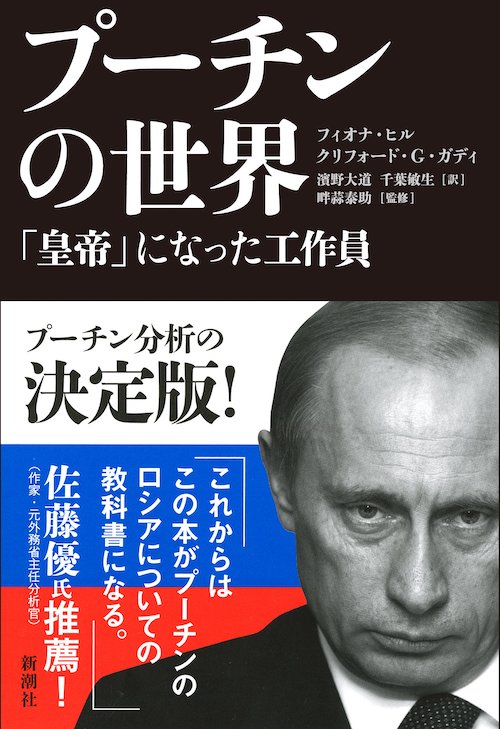
それを踏まえて、現代ドイツ社会では意外なほどに潜在的プーチン支持・擁護のマインドが強いのです。日本であまり報道されていない話ですが、端的にまとめると要因は以下の3つとなります。
1.先述した欧州の内面的「反米志向」にとって、一種のヒーロー視が可能である。
2.ロシアの対外メディアは「ポスト冷戦時代、西側諸国に収奪された犠牲者・ロシア」という物語の拡散が(西側エンタメをさんざん分析した成果なのか)極めて巧みで、「ゆえにロシアはいま、生存のため、やむなく攻撃に出なければならない!」という論理を、かなり多くのドイツ人が無自覚に受け入れている。これはドイツ統一後の旧東独エリアの「収奪」をめぐる葛藤と相似するため強い説得力を有するが、いずれにせよ「ハイブリッド戦争」としてよく語られるロシア的情報戦の成功面といえる。
3.やたら情報量が多い現在の日常生活にて、自力で国際情勢を理解・解釈しおおせるのは困難だ。ぶっちゃけ手っ取り早く状況についての納得感を得たい、そして「他人とちょっと違う観点から、ありがちな主流的価値観に対してマウントを取りたい」というドイツ的インテリ市民文化のしょうもないニーズにとって、よくできたロシアのプロパガンダ的「物語」コンテンツはたいへん魅力的だったりする。
ドイツ「まあ、ロシアの武力行使はないっしょ」
……と、これがドイツ人にとってのロシアイメージというか「ロシア活用法」の現状です。こうして改めて纏めてみると、知的精神的にロシア側の影響力というか主導権が拡大している感がありますね。
西欧に突きつけられた直近のロシアがらみ難題といえば、現在(2022.2.6時点)進行中のウクライナ危機です。ロシアは武力行使に出るのか、否か?
ドイツでは意外なほど「まあ、武力行使はないっしょ」という見解が優勢です。そもそもあのロシアの挙動の主因のひとつが、現連立与党であるFDP(ドイツ自由民主党)による、天然ガスパイプライン「ノルドストリーム2」計画からの撤退方針であると踏んでいて、ゆえに「ドイツがノルドストリーム2計画を再び推進する」ことと引き換えに、ロシアが「ウクライナ国境から軍を撤収」させるだろう、とみているのです。
「戦後ドイツ」の真価が真に問われる局面
軍事的マチズモの活用はロシア外交のお約束であり、ある意味、プロレスの試合のように「筋書きのあるドラマ」がここに成立する、と言えなくもない。しかし今回、そして将来、ずっとそんなお約束の延長の駆け引きだけでやっていけるのか、自分としてはやや不安な印象を持たずにいられません。今般のウクライナ危機についても、「紛争地域には武器を輸出しない」ルールに基づく「ヘルメット5000個提供」策など、どの立場からも反感と失笑を買うだけで、しかもそれを自覚していないドイツの無神経さがヤバいです。
いっぽうロシアはロシアで、いつまでも武力を「第一の対外的影響力」要素に据えておくわけにはいかず、もっと魅力的な国際的ビジネスモデルを構築・アピールする必要が不可避的に出てきます。そこでドイツが何かポジティブな役割を演じることができるのか、というのが、実は「戦後ドイツ」の真価が真に問われる局面だったりするのかもしれないと思ったりする今日このごろです。
関連記事
-
-
マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】
『DAIENKAI 2025』:PR -
ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】
『DAIENKAI 2025』:PR