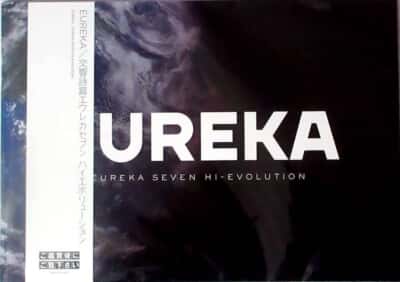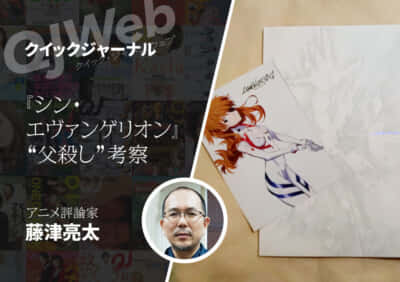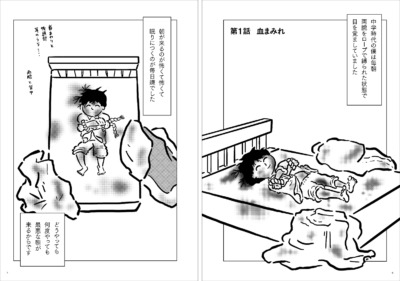『アイの歌声を聴かせて』と『EUREKA』の共通点
『アイの歌声を聴かせて』(吉浦康裕監督/松竹配給)は、AIを搭載したロボット・シオンが極秘の実証実験のために高校に送り込まれたところから始まる物語。シオンの開発者を母に持つサトミは、ある理由から校内で孤立しているが、シオンは、なぜかそんなサトミを幸せにしようと奮戦する。そしてシオンがロボットであることをバレないようにするため、サトミたちはあれこれと振り回されることになる。シオンが、サトミがこっそり好きなアニメ映画『ムーンプリンセス』の歌を、折に触れて歌うのが本作の見せ場のひとつになっている。

一方、『EUREKA/交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション』(京田知己監督/配給:ショウゲート)のほうは2017年から始まった『ハイエボリューション』シリーズの完結編。前作ラストで、情報生命体を操り“仮想世界”を作り出す能力を失い、ただの人間となったエウレカが主人公となる。そんなエウレカが、かつての自分と同じ“EUREKA”の能力を持つ少女アイリスを保護するミッションを命じられる。現在地球には、エウレカがかつて作り出した“仮想世界”から、現実の地球へと放り出され、“難民”となった人々が多数存在しており、その一部の勢力は、ある作戦のためにアイリスの身柄を狙っているのだ。敵勢力のリーダー・デューイの攻撃を避け、ヨーロッパをふたりで移動せざるを得なくなったエウレカとアイリス。ふたりはぶつかり合いながらも、次第に互いを理解していく。
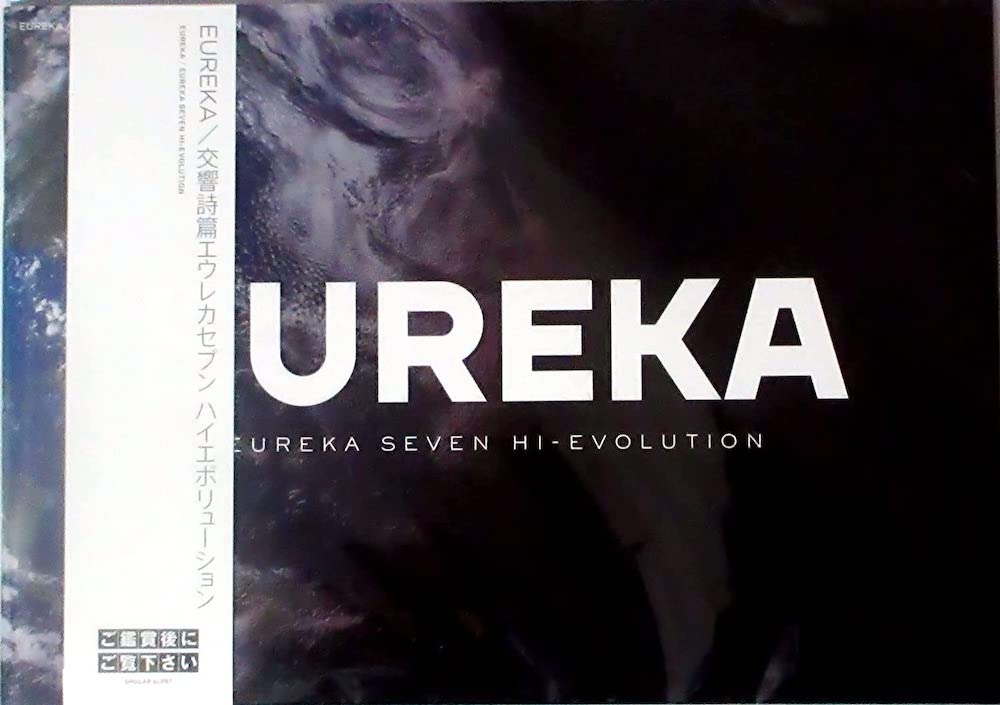
一見、似ているところのあまりないように見える2作だが、シオンとエウレカに注目をすると共通点が浮かび上がってくる。このふたりはともに「命令/任務」を遂行していく過程で、その行為が「愛」へと接近していくキャラクターなのだ。
シオンは、高校に現れた瞬間からサトミの名前を知っており、サトミが幼いころから好きなアニメ映画『ムーンプリンセス』の歌を歌う。どうしてそんなことができたのか。映画の終盤でその秘密が明らかになる。シオンのボディに入ったAIは、実はサトミが幼いころ、幼馴染のトウマがブローチ型携帯ペットのプログラムを改造して作り上げたものなのだった。そのときトウマが、「サトミを幸せにしてあげて」とプログラムに命じたことが、すべての発端だったのだ。やがて消去されそうになったAIはネットワーク中に自らを逃し、ネットイワーク中に偏在しながらサトミの成長を見守りつづけてきた。その間に、サトミを幸せにする術を、『ムーンプリンセス』を参考に学びもしたのだ。
『アイの歌声を聴かせて』がユニークなのは、このシオンのAIの存在が、「トウマのサトミに対する気持ち」を補強する補助的存在としては描かれないところにある。シオンのAIの「サトミを幸せにする」という行動は、、トウマの気持ちをも包含したより大きなものとして本作では描かれている。トウマの命令が長い間大事なものとしてシオンのAIの中で維持されている、その様子を見た観客の気持ちの中に、「これこそ無私の愛ではないか」という感情が立ち上がってくるのである。
『愛』(講談社現代新書/苫野一徳)を読むと、「愛」が存在するためのには、本質契機として「歴史的関係性」が重要な働きをするという指摘が書かれている。これはつまり「重ねたとき間(と、これから時間を重ねるであろうという予感)」が「愛」を浮かび上がらせるということだ。

『アイの歌声を聴かせて』の場合、シオンの実証実験が始まってからの数日という「時間」があり、さらのその時間の中に、ネットに逃げ出したAIがサトミを見つけ出すまでの「時間」が織り込まれている。この二重になった時間を自覚したとき、観客の中でシオンのAIが実行する命令が、「愛の行為」として認知されるのだ。
この「命令/任務」の実行が「愛」へと転換される瞬間は、『EUREKA』にも存在する。
デューイの襲撃を辛くもかわしたエウレカとアイリスは、ホテルで一夜を過ごす。エウレカがバスルームにいると、怖くなったアイリスが入ってきて、2人は一緒に浴槽に入ることになる。
アイリスはエウレカの体中に傷があることを知る。それは様々な任務などでエウレカが負った傷だった。エウレカは「仕事だからしょうがない」というが、アイリスはその傷に触れてこんな感想を漏らす。
「こんなに傷ついているのに、それでもいっぱい人を助けようとしているんだね」
この言葉にエウレカは息を呑み、照れたようにこう付け加える。「往生際が悪いのよ」。最後まで諦めないから、こうなったのだ、と。一度は使った「仕事(つまり任務)」という言葉を、エウレカは2度は使わなかった。
エウレカは人の形をしていたけれど、もともと人間ではなかった。天涯孤独であり、家族の愛も知らない。そんな彼女は10年前に、“仮想世界”を作り出す能力を失い人間になったものの、それはあくまで身体的な事象にしか過ぎない。彼女自身は、自分は“人間”としては結局不完全であるという自覚があった。だからこそエウレカは、足りていない部分を埋め合わせるように任務に没頭したのだ。
だがアイリスは、そんなエウレカの行為を称賛する。アイリスは、エウレカの行為を「任務」ではなく「愛」の行為だと読み取ったのだ。そしてその指摘がエウレカに大きな気づきを与える。自分の中にはないものだと思っていた「愛」だが、それはすでにそこにあったのだ。エウレカは、自分の「往生際の悪さ」がどこからやってきたかをこうして自覚することができた。
映画の序盤、保護の任務についたエウレカがアイリスの養父母に、なぜ自分の子供ではないアイリスをそこまで気にかけるのか、と質問するシーンがある。そこでアイリスの養母はこう答える。
「はっきりした理由はありません。ただ一緒にいた時間があの子を私たちの宝物に変えたんです」
アイリスの養母にそう告げられたときは、素直にその意味を飲み込めなかったエウレカが、ラスト間際では「この世界の人たちと一緒にいた時間が、この世界を私の宝物に変えたの」と語る。エウレカが自分の中に発見した「愛」もまた、彼女がこの世界で人間になってからの10年という時間が生み出したものなのだ。そしてこの10年という時間は、アイリスと出会ってからの数日間の中に二重に折り重なるように描かれている。エウレカはアイリスとの数日間を通じて、世界と自分の中に「歴史的関係性」があることに気付かされ、それが彼女を真の意味で人間にしたのである。
シオンとエウレカを通じて「愛」を体感
このようにシオンとエウレカは、作中での立ち位置は違えど、「命令/任務」だったはずのものが「愛」の行為に転換する中心にいるキャラクターなのだ。そしてそれは、二重に折り重なった時間によって示される「歴史的関係性」のもたらすものだ、というところも共通している。こうして観客はシオンとエウレカを通じて「愛」とはなにかということを体感するのだ。
「愛」という言葉は気恥ずかしく、取り扱いも難しい。でも「愛」はある。現実の中では複雑過ぎてなかなか捕らえきれない「愛」を、フィクションはわかりやすく端的に示してくれる。そんな作品に僕らは支えられてここまでやってきた。これからもそうやって生きていくのだろう。
関連記事
-
-
マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】
『DAIENKAI 2025』:PR -
ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】
『DAIENKAI 2025』:PR