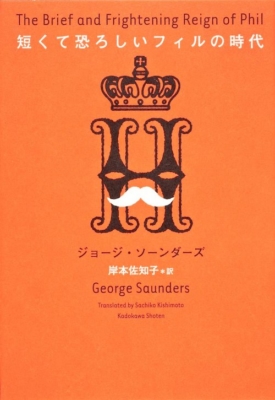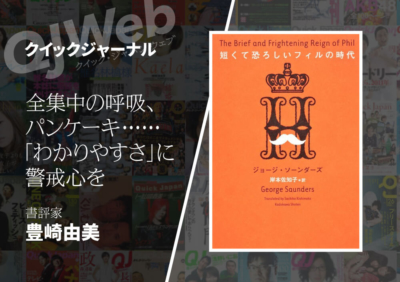糸井重里のいくつかのツイートに、書評家・豊崎由美は違和感と不信を覚えた。かつて雑誌の反戦特集号で「まず、総理から前線へ。」と痛烈な権力批判のコピーを放った当人がなぜ、コロナ禍に苦しむひとたちへに嫌味のようなことしか発信できないのだろうか。輝かしい功績を見てきた世代として、韓国の傑作『こびとが打ち上げた小さなボール』を、殿上人になってしまった糸井さんに届けたいと痛切に願う。
糸井重里はかつてたしかにスターだった
2018年から「ほぼ日5年手帳」を愛用しています。1日分の見開きが5年分に分割されている、A6のサイズ感と紙質が気に入っているからです。ただ、ひとつだけ不満があります。それは、右ページの一番下に誰かが放った言葉が記されていること。
左に仕事の予定や締切を記入し、右に書評で取り上げた本のタイトルやその日あったことを簡単に記しているわたしにとっては、その“お言葉”によって最終年にあたる2022年の右ページの余白が存在しなくなってしまう。つまり、「ほぼ日5年手帳」が「ほぼ日4年手帳」になってしまうわけです。
『ほぼ日刊イトイ新聞』のストア側からすれば、手帳を開くたび、心に響く言葉(選んでいるのはどうせ糸井重里なんでしょう)が目に入ってくるって素敵じゃない?「おいしい生活」じゃない?ってことなんでしょうが、わたしにとっては「知らんがな」です。素敵な言葉は自分で探すし見つけるし、自分でメモりたい、手帳は手帳として、粛々と手帳の役割を果たしてほしいと思うだけです。
こういう善意というか、ある種の価値観の押しつけを、押しつけと思わずやってしまえる無邪気さは、糸井重里が1980年代に当代きっての人気コピーライターとして活躍していた前身が関係することは間違いありません。広告は、コピーは、価値観を消費者に押しつける仕事だからです。
1961年生まれのわたしは、その前身時代における糸井重里の華々しい活躍をリアルタイムで見ています。沢田研二の「TOKIO」の作詞をしたり、サブカル誌の『ビックリハウス』で「ヘンタイよいこ新聞」を担当したり、『週刊文春』で読者投稿型の「糸井重里の萬流コピー塾」を家元として主宰したり、「不思議、大好き。」や「おいしい生活」といった本職のコピーで脚光を浴びたり、傑作ゲーム『MOTHER』を作ったり、徳川埋蔵金を探したり、テレビ番組のMCをしたりetc.etc. 糸井重里はかつてたしかにスターだったし、輝くマルチタレントだったんです。
あの頃、多くの若者や消費者は、糸井重里が差し出す価値観を喜んで受け入れていました。今もその層が厚いのは『ほぼ日ストア』の成功が示しているのではないでしょうか。でも、時々ほころびが見えたりすることもあります。その例が、忘れもしない2017年、「阪神淡路大震災を乗り越え、記念すべき開港150年を迎えた今年の神戸から、東北へ、熊本へ、そして世界中へ(略)復興と再生のメッセージを届ける」との意図で、樹齢150年の木を掘り起こしてクリスマスツリーにし、展示後は伐採して加工したグッズを販売するというプロジェクトの企画に参加した時のことです。
「輝け、いのちの樹」というサブタイトルをつけておきながら、木を殺すのはなぜなのかといった疑義が沸き起こり、糸井重里にも批判が殺到。その時、糸井がツイッターで「冷笑的な人たちは、たのしそうな人や、元気な人、希望を持っている人を見ると、じぶんの低さのところまで引きずり降ろそうとする。じぶんは、そこまでのぼる方法を持ってないからね。」(2017年11月16日)と発信し、火に油を注いでしまったのは記憶に新しいところです。
かつて学生運動を経験し、『ビックリハウス』の反戦特集号では「まず、総理から前線へ。」というコピーを書いた糸井重里が、新型コロナウイルス感染対策で後手後手に回っている政府の批判をする人たちに向け、「わかったことがある。新型コロナウイルスのことばかり聞いているのがつらいのではなかった。ずっと、誰ががが(引用ママ)誰かを責め立てている。これを感じるのがつらいのだ。」「責めるな。じぶんのことをしろ。」(共に2020年4月9日)というツイートを放ったのも、なかなか衝撃的でした。
関連記事
-
-
マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】
『DAIENKAI 2025』:PR -
ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】
『DAIENKAI 2025』:PR