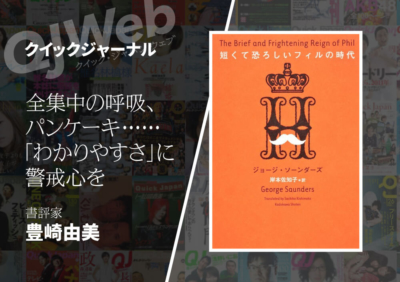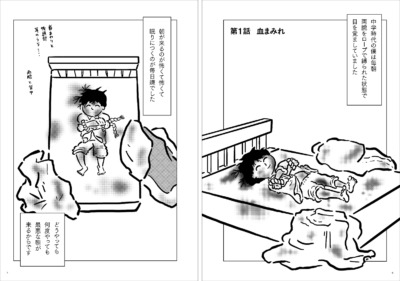都合のいいように語り直される「物語」

〈クイズです。この中にいくつ「物語」が隠れているでしょう?〉という問いかけから始まる作品の中で、作者の松田さんは物語と「物語」の違いをまず明確にしてくれています。
〈物語は時を超え、民から民でと語り継がれ、歌い継がれ、とても大切にされていました。(中略)どんな時も、民は物語とともにありました。物語があることで、民は愛を、慈しみの心を、希望を捨てず、生きることができたのです。そうです、物語は素晴らしいものでした〉
対して「物語」はというと
〈「物語」は物語界のファストフードでした。手軽で、驚くほど安い値段で(多くの場合、無料でした)、すぐに手に入るのです。新しい技術が、「物語」の拡散をとても容易なものにしました。「物語」は生活の隅々まで紛れ込むことで、民が探す手間を省いてくれました〉
〈さらに素晴らしいことに、この「物語」には、参加することができました。民の一人が「物語」だと言えば、誰かがどこかから「物語」を発見してくれば、すぐにそれは「物語」として認められました。ゴールドラッシュもかくやという勢いを持って、民は「物語」に群がりました〉
〈民は思うままに事実を取捨選択し、「物語」を纏めることができました。主観や偏見、社会通念が「物語」を支配しました。もちろん、物語にも古来そのような側面は常にあったのですが、「物語」では、この点がさらに一目瞭然になりました〉
〈「物語」の応酬で日々は祭のように賑やかなことこの上なく、また、その一連の応酬が一つの「物語」として、ネットワーク空間に、民の海馬に刻まれることになりました。民は「物語」を主食として喰らう怪物と化したのです〉
こうして、「物語」がいかなるものかを明らかにした後、松田さんは具体的な「物語」と「物語」から逃亡する人たちの存在を提示していくんです。
会社で働く女性・風間行子のことを〈きみは〉と呼びかけ、脳内で勝手な「物語」を作り上げていく存在〈わたし〉。彼は、風間行子に対して故意に誤ったデータを付与し、自分の中の「女はこういうものだろう」という「物語」を押しつけようとします。風間行子がその「物語」から逃れようとするたびに、「物語」を自分の都合のいいように語り直し、彼女を逃そうとはしません。女は流行り物が好き、女はフワフワした恋愛映画が好きでアクション映画を見ない(見ちゃいけない)、女が化粧をするのは彼氏のため、女はデートであるならハイキングでも白いワンピースを着ていきたがる、デートの日は上下で色を揃えた色気のある下着をつけるetc.etc.
しかし、〈わたし〉によって「物語」の主人公にされてしまった風間行子もついに怒りを爆発させます。
〈静かに聞いてれば、こっちが我慢してれば、好き勝手にいろいろ言って、しかも周りの人たちに言わせるような、自分じゃないですみたいな、卑怯なやり方で。(中略)あなたの「物語」はなんて退屈なの。逃亡生活を送りたくなるのも当たり前〉〈なんでもかんでも都合のいい、安っぽい「物語」にするのはやめて。たいして愛着もない癖にいっぱしの気分になって。ずっとずっと逃げたかった。あなたの曇った眼鏡が世界を曇らせる、全部一緒にしてしまう。磨いてください、その眼鏡。できないんだったら、私をあなたの「物語」に登場させないで。放っておいてください〉と。
しかし、〈わたし〉は反省したりしません。次から次へと犠牲者を見つけては、懲りもせず自分の「物語」を押しつけつづけます。そして、自分の「物語」の中では“こうあるべき”女性、女学生、若い男性、夫婦、孫の姿を押しつけ、そのたびに登場人物たちから「NO!」を突きつけられることになるんです。
それは男が選んだ男の傑作だ
ひと言で言って痛快至極です。でも、この自分の「物語」を他者に押しつける〈わたし〉は、豊崎由美自身の似姿であるかもしれない可能性に気づいて、痛快至極な気分はすぐに沈んでしまいます。人の振り見て我が振り直せ、なのです。また、こうも思ってしまいます。作者の松田青子さん自身もまた、この作品を通じて〈わたし〉に忌むべきタイプのおじさんの「物語」を押しつけることになってはいないか、と。そう考えると、松田さんが作品冒頭で解説した「物語」から、わたしたちが逃げ切るのは不可能なのかもしれません。「物語」を批判するときに他の「物語」を用いてしまっては、「物語」から逃れるどころか「物語」に呑み込まれることになりかねない……。そんなあれこれが頭の中に渦巻く、これは素晴らしい問題提起作なのです。
女性の体や制服に向けられる性的な視線。女の子に強要される従順さや無邪気さ。何か事が起きれば、女性にそうさせている男性にではなく女性に対して向けられる非難。女性が大きな声で抗議すれば、「感情的になるなよ」と小バカにする風潮。そうした理不尽に、想像力で立ち向かっている作家が松田青子です。ですから、この最新短篇集に収録されている11篇も、先に紹介した「「物語」」をはじめ、男性中心社会の中で昭和のがさつで無神経なおじさんタイプが発する言説のあれこれにうんざりさせられている女性や、昭和のがさつで無神経なおじさんタイプの言動を批判的に見ることができる男性にとって、心励まされる作品になっています。
中学生のとき、洋画チャンネルで発見した80年代後半のアメリカ映画『恋しくて』。表題作の主人公はそこで〈まるで男の子のような格好をしたショートカットの女の子の虜に〉なります。〈かっこいい。かっこいい。かっこいい。男の子になりたかった女の子になりたかった女の子の全身が叫び続ける〉。その一方で、彼女は世の中で傑作とされている映画の多くに登場する〈性的に登場し、性的に動き、性的に扱われる〉女性にはまったく共感は覚えず、〈それは男が選んだ男の傑作だ〉と思うんです。
あるいは「桑原さんの赤色」における、大学生の夜野がアルバイト先の不動産屋で出会った〈両のまぶたに真っ赤なアイシャドウをたっぷりと塗って〉いる中年女性の桑原さん。後年、26歳になった夜野がこの色の意味をはっきり自分のものとして認識する瞬間は、自分にもいつかどこかにあったと気づき、はっとさせられる人が多いのではないでしょうか。
「そうっ! そうそうそう!」と快哉を叫んでしまうのは「許さない日」。この小説の中で、作者の松田さんは〈あのおぞましい〉ブルマの生地を、想像のハサミで細かく切り刻んでくれます。なんであんな動くとパンツがはみ出てしまうような性的な代物を体操着として身につけなければならなかったのか。還暦を迎えた今も忘れられない屈辱感と怒りを、この小説はわたし(そしてある年代に属する女性)と共有してくれるんです。
ユキという漢字が違うけれど同じ名前を持つふたりの女性。同じ団地の向かい合わせの部屋に住む、彼氏と同棲している20代終わりのユキと、充足したひとりの人生を送っている40代半ばのユキの数年間の生活と淡き交わりを描いた「向かい合わせの二つの部屋」。コロナ禍の中、まだ赤ん坊の我が子と共に、問題のある夫から逃れて見知らぬ土地の生活型ホテルに隠れ住んでいる女性の不安と希望の日々を綴った「誰のものでもない帽子」。
この作品集にはざまざまな声で描かれたさまざまなタイプの女性が登場し、読者であるわたしたちはその中に自分の似姿や知人の顔を見つけたり、そうであったかもしれない自分、そうなるかもしれない自分と出会ったりしながら、すべての物語を近しいものとして摂取していくことになります。「物語」ではない、物語に出会うことができる一冊なのです。
関連記事
-
-
マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】
『DAIENKAI 2025』:PR -
ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】
『DAIENKAI 2025』:PR