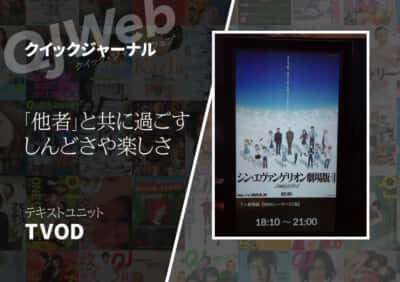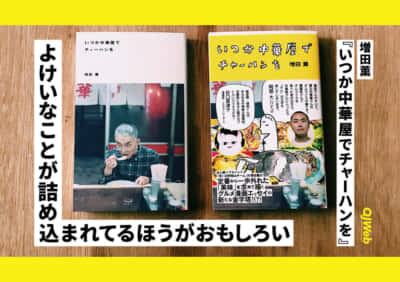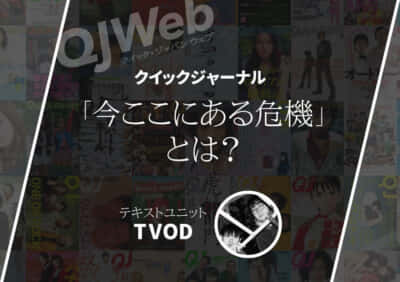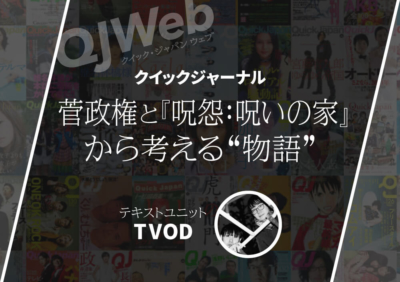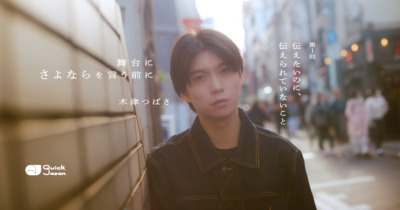なあなあな判断の集積が招く混乱
コメカ この作品には描写を「現実の社会問題に近づける」ために捨象したものが色々あると思うんだよね。明らかに、表現を簡略化して伝わりやすくしている部分がある。それは「伝えたいものがあるから」だとぼくは理解していて、それでは本作はいったい誰に何を伝えようとしているのか?というところで少し疑問があるのよ。それこそツイッター的に言うと、エコーチェンバー的な、「すでに問題理解のあり方を共有している人にしか伝わらない物語」になってしまっていないか?と思ったわけ。
さっき言った「抑圧される側がむしろ積極的にそれを支持することでこそ成立する抑圧システムへの視座」の欠如、つまりポピュリズム的なエネルギーが持つ得体の知れなさへの感覚の欠如を感じるのも、その理由のひとつ。権力の被抑圧者として自己や大衆を理解している人には確かにこの「メッセージ」は、(現状認識の再確認として)届く。
でもたとえば、果たして私たちは本当にただ受動的に抑圧されているだけなのか、大衆は能動的に、ある程度熱を入れて空疎な権力を支持してしまってはいないか、というような視点は(とりあえず現段階では)ここにはない。ぼくはやっぱり物語表現にはより深く、さまざまな角度から現状や問題をえぐるような力を、一観客として勝手に期待してしまっている。なので不満を言うことになってしまう。
パンス 積極的に支持する「抑圧される側」とは、何を指しているのだろう? このドラマの中では描かれていない、新聞部ではない「大多数の学生」が当てはまるかもしれない。そこが描かれていたら、さらに奥行きが出そうではあるね。それと、この物語の軸になっているのは、何か大きな力が抑圧を生んでいるというより、組織の中の個々人による判断が結果的に状況を打開できない、停滞に至っている姿だと思うけどね。
そこから何かメッセージを生み出すとすれば、たとえばこの中の誰かが反旗を翻す、といった展開によって成立するかもしれない。学長が決定事項を撤回する第3話には、そういう部分があったね。しかし最後にお酒を飲んで「いや〜大変だったよ〜」ってとこに帰結させるのがおもしろいと思った。表に出ているメッセージのみでは捉え切れない複雑さが示唆されている。理想の追求の大切さと並行して、よるべなき現実を描くことを忘れない、という。
パンス ちょっと現実に敷衍させて考えてみると、ポピュリズムという言葉が普及して久しいけれども、こと日本において起きている抑圧というのは、ヨーロッパにおけるポピュリズムの傾向とは異なる点が多い。単純に言うと、特定のキャラクターが世論を持っていっちゃうという形式ではなく、集団における空気の読み合いとか、それまである構造に沿ったなあなあな判断の集積が混乱を招いているというパターンになりがち。それこそ、Covid-19に対する政府の対応で全面展開しているわけだけど。
コメカ 言ってしまうと、神崎真という主人公は、周囲からのボンヤリとした好感度しか持ち得ない、状況に翻弄される無自覚な男として描かれるわけだけど、こういう奴こそが能動的に世論を持っていくキャラクターになり得るよな~と思うんだよね(笑)。新聞部ではない「大多数の学生」のような人々が、そういう空洞の扇動者を支持する未来というのを、現実では小泉進次郎や吉村洋文の存在が先駆けている部分があると思うし。
ただ確かに「組織の中の個々人による判断が結果的に状況を打開できない、停滞に至っている姿」が、この作品の描写の軸だとは思う。そこで神崎がある意味で「無垢な存在」として描かれていることに、自分の中では違和感があった、ということだね。「よるべなき現実」においては、神崎のような人間も、ある意味でもっと酷薄な生活者的リアリティの中で生きているんじゃないか?と思ってしまったんだよね。こういう「すでに気づいている人/まだ気づいていない人(=神崎)」という二項対立的な視座は、本当に現実を捉えているんだろうか?と疑問に感じた。
そして確かに、現状の日本においてはポピュリズム的キャラクターすら成立していないというのはある。さっき名前を出したふたりも実際のところセルフイメージの管理はうまくいっていないし、小池百合子も結局その試みにおいて肝心なところでつまずきつづけている。菅義偉に至ってはそういう類の才能は1ミリもない政治家だし。政府や地方自治体のコロナ禍対応が行き当たりばったりで根拠に欠けるいい加減なものにしかならないのも、「それまである構造に沿ったなあなあな判断の集積」に基本的には起因している。
しかし、案の定憲法改正論者がこの機に乗じて火事場泥棒的な気炎を上げているように、だからこそ「ポスト・Covid-19」時代においては、いよいよ空洞のポピュリストが期待されてしまうんじゃないかなあ……とは思うんだよね。「好感度」という主題を持ってきたドラマだったから、そのあたりの視座への期待を個人的に、勝手にしてしまったってところはある。「今ここにある危機」とは、むしろそういう類の危機なんじゃないか?と。
パンス 神崎が自身の好感度に翻弄されている状態のまま、周囲をどんどん巻き込んでのぼり詰めていくというストーリーだったら、それこそブラックユーモアとしてイイかも。今の日本って、現在ある権威というものの次が想像できないんだよね。小泉進次郎に象徴されるように、権力の中心に巨大な空洞が位置して、既存のシステムだけが回りつづける……というのはなんかSFっぽいけど、現実的な問題でもある。
パンス さて、ちょっと話をズラすけど、今ネット記事のタイトルに「強烈な違和感」が連発されてるなんてツイートを読んでおもしろかったんだけど、「違和感」とか「モヤモヤ」というのが現在の重要なキーワード。『モヤモヤさまぁ~ず2』が始まった2000年代後半のころは好奇心の表れだったけど、最近はちょっとネガティブなニュアンスがある。これ自体が、ある問題に対する即ジャッジが求められる時代を表していると思う。一瞬ではジャッジし切れないのでペンディングするけどなんかダメだと思う……という意思が反映されているように見えるのね。
それらをどう言葉にしていくか。たぶんそれには長々と話す必要があるし、この原稿もその実践のつもりなんだけど。『今ここにある危機とぼくの好感度について』においても、即結論を出す/メッセージを発する、という態度を保留しながら物語を進めているようなところがあり、今後どう展開するか、僕は楽しみに見守ってます。