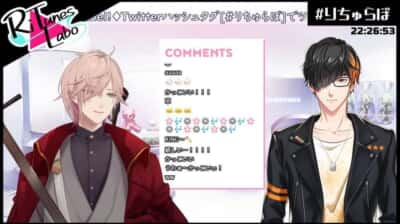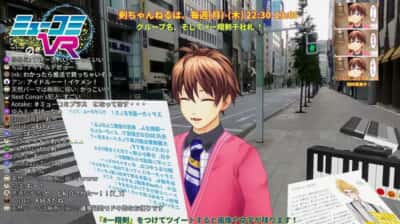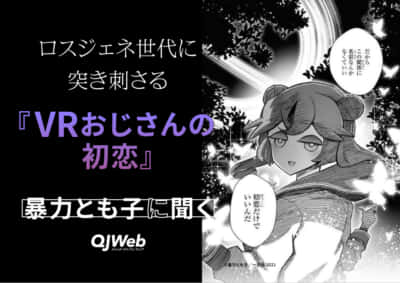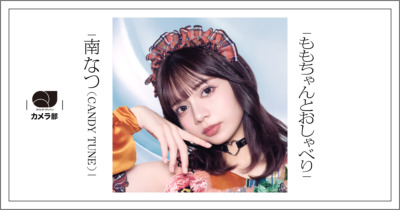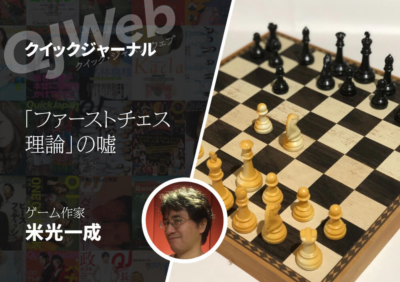身を守るリテラシーとして
たとえば中田敦彦のアバターも、VRchatに入り込むとかVR空間で講義を行うとかで使用するとしたら「新しい中田敦彦の顔」としてプラス要素になったはずだ。本人がアバター化を決意した際に言っていたように、生身ではできない表現ができるのがアバターの強みだ。
現在VTuberが増えつづけているのは、最初から自身の姿を見せず、自分の理想の姿で活動ができるからだ。性別を変えたい、人間ではなくなりたい、好みの見た目になりたい、物語を作りたい、というミラクルを叶えることができる。新たな活動でより都合がよくなるための衣装だ。今までの活動と別の人格で使い分けたい、という願いもこれで叶う。
中田敦彦は「失敗」とは言ったものの、彼が警鐘を鳴らした1点は頭に留めておきたい。「顔という個人情報」「デジタルタトゥー」の危険性だ。
彼は冒頭で挙げた動画でこう語っている。「プライバシーの問題ってよりヘビーになってきてる」「全員がカメラを持って全員が写真を撮って全員がツイートできる時代になってるじゃないですか。発信して顔を出して名前を出してやるリスクってけっこう大きい」
今は配信者がめちゃくちゃ増えている時代。大人も子供もホイホイと顔を出しできてしまう。インスタグラムやツイッターのみならず、今はスマホ1台で簡単にライブ配信ができるアプリが山ほどある。
一般人の子供たちは、顔を情報コンテンツとするタレントではない。身を守るためのリテラシーとして、顔を隠すアバター文化は教育を通じて、あるいは有名人の活動を通じて、浸透していってほしい。そしてアバターになれば、より新しいVR・AR体験ができる時代は、すぐそこまで来ている。
『サマーウォーズ』で、普段PCを使わなさそうなおっちゃんたちもアバターを持っていたシーンを思い出す。『どうぶつの森』でSNS的にオリジナルアバターを使う感覚が今の世代にはすでに身についているのだから、そこまで難しい話ではないはずだ。