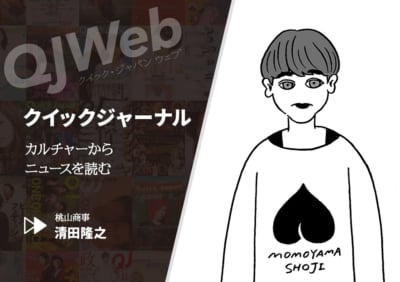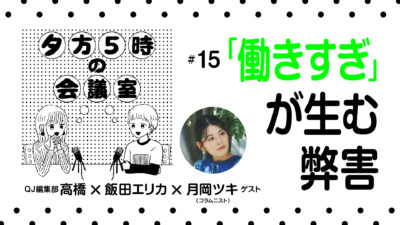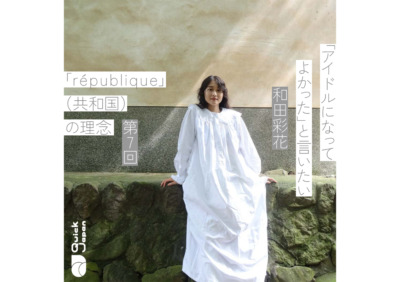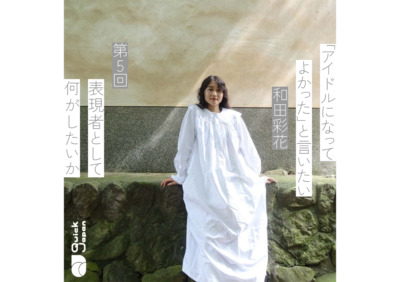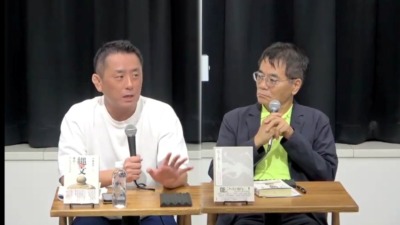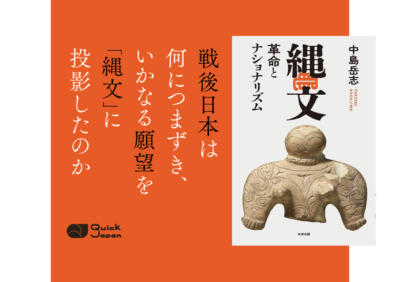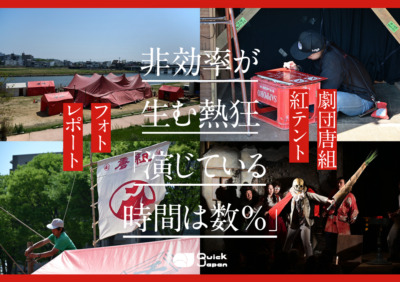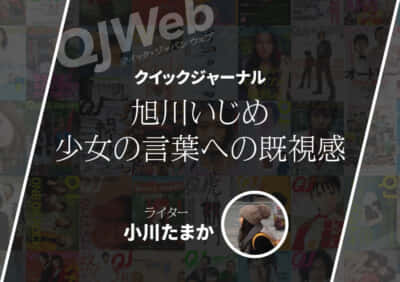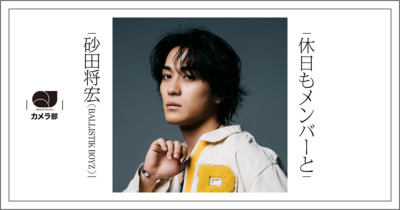「話の通じなさ」に付随する絶望感の正体

話が通じないとはどういうことだろうか。たとえば妻が夫に「手洗いうがいをちゃんとやって欲しい」と求めたとする。夫側に心当たりがあるなら「了解」と言って行動を改める。もしないなら、「自分ではやってるつもりだったけど足りてないかな?」などと妻側の考えを聞いてみる。これならば話は通じたことになる。
しかし、ムスッと黙ってしまう、「気にし過ぎじゃない?」「大丈夫っしょ」と返答する、「俺をばい菌扱いするのか」「お前だって完璧じゃないだろ」とキレる……といったリアクションをした場合、相手から「話が通じない」と思われても仕方ないだろう。あるいは「了解」と返事をしたのに行動が改まらない場合も同様の印象を与えるはずだ。
話し合いにならない。問題に向き合ってくれない。意味や意図を理解してもらえない──。こういった感覚こそ、「話の通じなさ」に付随する絶望感の正体ではないかと考えられる。
男性たちは今こそジェンダーを学ぶべき
くり返しになるが、男性ばかりが悪者と言いたいわけでは決してない。しかし、コロナ離婚やコロナ破局にまつわる声を眺めてみると、著書の元になった800のエピソードとめちゃくちゃオーバーラップするし、コロナはあくまで引き金のひとつであり、原因は平常時から蓄積・潜在していた要素のほうにあるのではないかと私には思えて仕方ない。
事例に挙がっていた衛生観念の低さや家事育児への不参加などが男性に顕著な傾向だとするならば、それは個々人の資質や意識による部分もあるだろうが、同時に「ジェンダー(=社会的・文化的に構築された性差)」の問題でもあるように思えてならない。身体意識の希薄さや家事能力の低さというのは、ジェンダー学の世界で散々指摘されてきた「男性性」の特徴だ。
コロナウイルスは未知なる脅威であり、専門家ですら混乱している中にあって、我々一般市民が状況や対策を正確に把握することは不可能だ。いきなり「外出を自粛せよ」と言われたら困惑するのが当然だし、していいこと/してはいけないことの判断を何に則って下せばいいかの基準も共有されていない。さらに今回は自分だけの問題にとどまらず、他者に感染させ、最悪の場合は死に至らしめてしまう可能性すらある。
誰もが不安を抱える状況下で時間を長く共にすれば、意識や価値観の差異が浮き彫りになったり、喧嘩が起こってしまったりするのはむしろ当然のことだろう。本来であれば政府が、明確な目的や具体的な期間、不安を和らげるための補償や対策、判断の基準となる情報などを国民にしっかり提示すべきだと思うが、現状それがなされているとは言い難い。
それはそれとして政府には厳しく声を上げていくべきだが、こんな今だからこそ、男性はジェンダーについて学ぶべきではないかと私は考えている。そこでは我々男たちの行動様式や思考パターンが極めて論理的に分析されている。自分の意思やこだわりだと思っていたものが、実はジェンダーの呪縛によって生産されていたという発見に満ちあふれている。自分を客観的に省みることで俺たちは「話の通じる男」になれるのかもしれない。
関連記事
-
-
4年目の今、重荷だった「王子様」を堂々と名乗れる。Last Princeが語る、プリンスを背負う勇気と楽しさ
Last Prince:PR