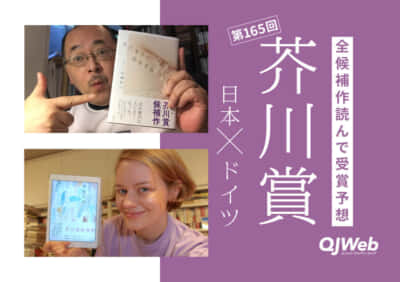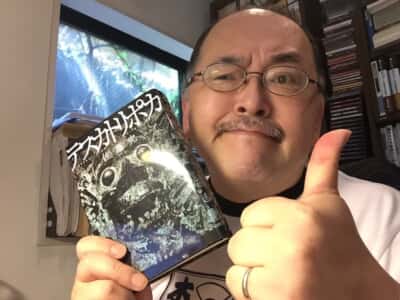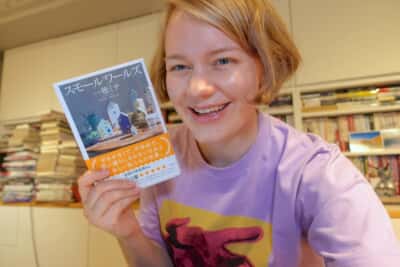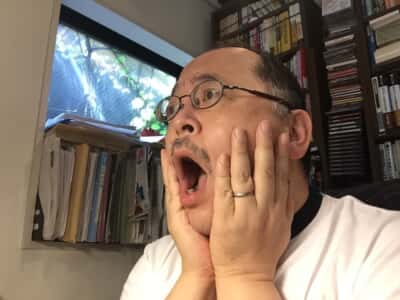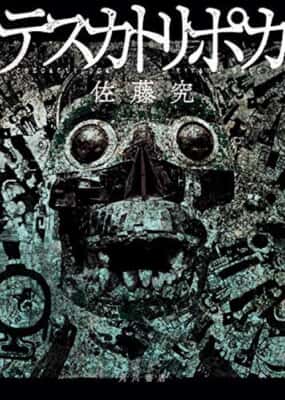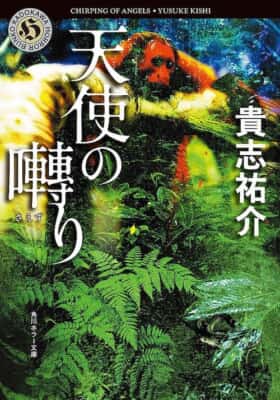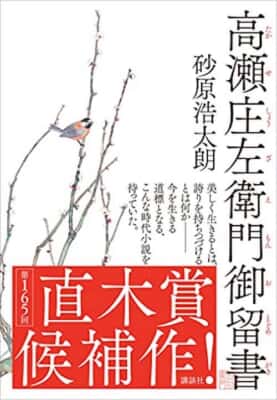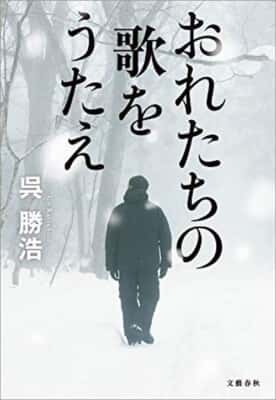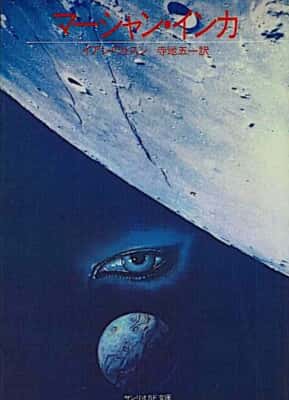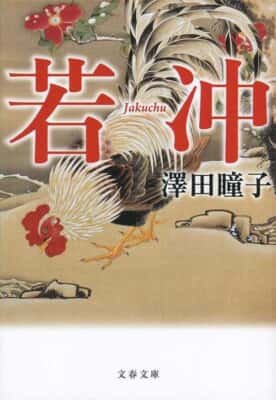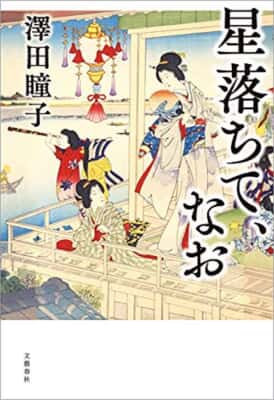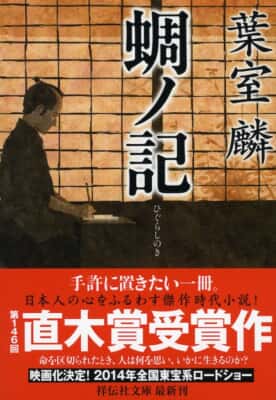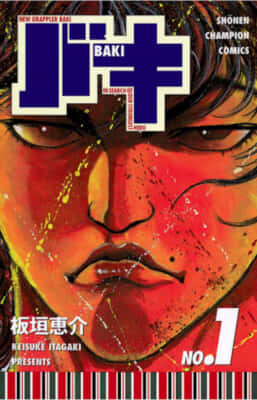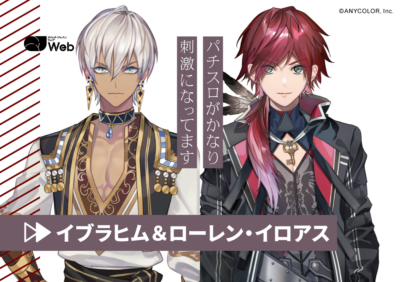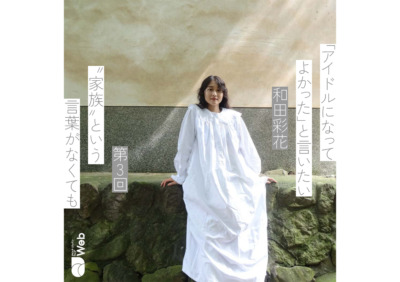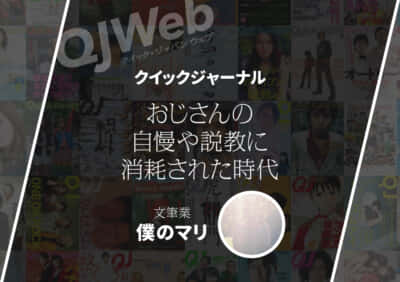「画鬼」を活かしきっていない『星落ちて、なお』
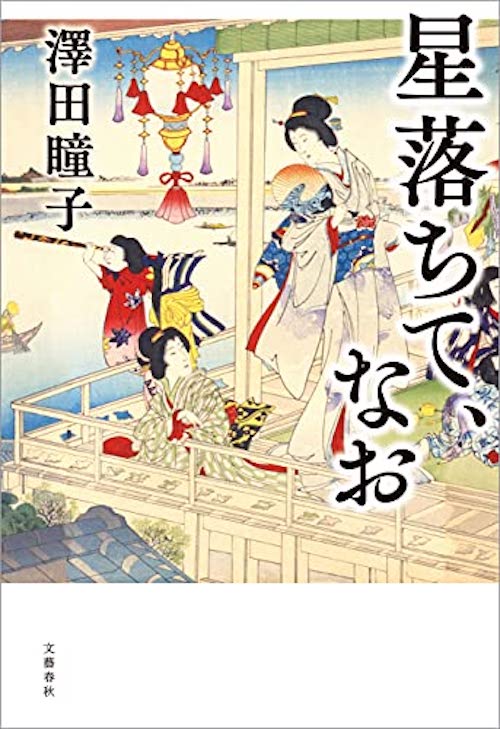
澤田瞳子『星落ちて、なお』あらすじ
1889(明治22)年、天才絵師・河鍋暁斎が没した。娘のとよは河鍋の画風を引き継いで生きることを決心するが、兄・周三郎と自らの間にある才能の隔たりに苦悩する。西洋画を貴ぶ時代の風は、狩野派の流れを汲む河鍋の者にとっては生きづらいものになっていた。
杉江 澤田さんは『若冲』『火定』『落花』『能楽ものがたり 稚児桜』と過去4回候補になっていて、今回芥川・直木両賞通じて最多です。ご専門が仏教史なんですが、日本の古典美術や芸能を主題にした歴史小説が多い。特に書き手の少ない古代や中世を舞台にした作品を手掛けておられる、稀有な存在でもあります。
マライ 澤田瞳子先生といえば前々回に候補になった『稚児桜』ですが、あれに比べるとずいぶん普通というか、あれは平安時代の庶民生活を書いた小説でしたが、今回は類書の多い領域だなという印象です。正直、インパクトに欠けるなと。
杉江 河鍋暁斎当人ではなくて娘が主人公で、時代は明治大正期という特徴はありますが、おっしゃることはわかります。以前候補になった『若冲』と基本的な造りは同じなわけです。主人公が絵師一家に生まれたゆえの煩悶を描いたり、時代遅れとされてしまう日本画の文化的な意味を訴えてみたり、というこの作品ならではの評価点はあるんですけど、前にも同じようなものはあったよね、という声は出てきてしまうでしょうね。この小説で評価がいちばん分かれるのは、主人公のとよが凡人だということだと思うんです。
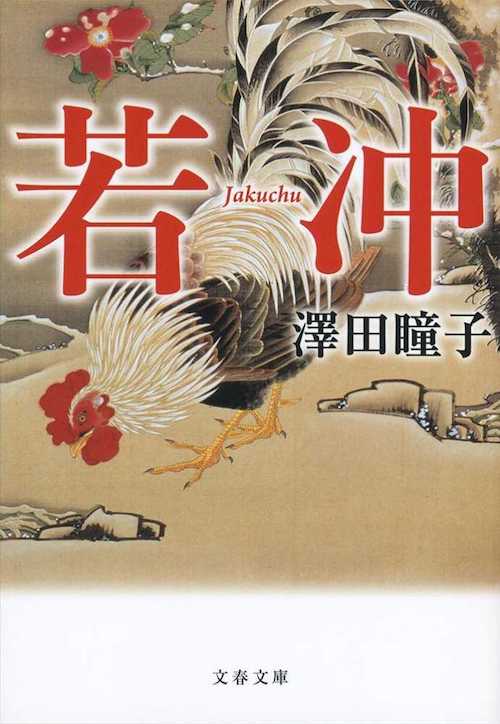
マライ そう。映画『アマデウス』みたく「天才vs優秀な凡人」の構図があるんで、凡人たる主人公がどう突破するかに関心を持ったんですけど、突き抜けずに終わってしまったのが、うーん。ジェンダー物語的な要素も加わって総花的になってしまった印象もあります。河鍋暁斎を指して言われた「画鬼」というファクターを活かしきっていない。
杉江 「画鬼」が、小説の中では父と兄に対する劣等感の裏返しでしか使われない概念なんですよね。そこが惜しい。
マライ そう。画鬼系の要素を有する人は世にいて、たとえば近著の表紙と挿絵をお願いしているイラストレーターのモリナガ・ヨウさんです。打ち合わせしたときに「ドイツ車には、買ってから3年後に初めてその存在に気づく謎収納スペースがあったりする」という話が出たらモリナガさんは高速スケッチを始めていて、最終的には「ドイツのIV号戦車の砲塔内部、主砲の取付手法は、本当はこうでなければいけなかったハズだ!」という、本とまったく無関係な話をしながら砲塔と取付ボルトをひたすら描いているんですよ(笑)。モリナガさんは「画鬼」感濃厚でありながら温厚なのがまたすごいのですが(笑)、とにかくああいう方を直に見ると、「画鬼」というのは『星落ちて、なお』で描かれるよりもSFじみて奥深くおもしろい存在なんじゃないかなーとか、思ってしまうわけです。
杉江 没後の物語なので仕方ない面もありますが、河鍋暁斎がどのように絵を描いた人なのか、どういう作品があるのかというのが読者に伝わりにくいのも、もどかしいです。
マライ 言えてますね。「画鬼」って、イデア的に脳内把握している形態の、肝に当たる部分を論理的に筋が通ったかたちで自分の手で描けないと気がすまない衝動が湧き立っているからああなるんですよ。だから多作だとか構図や色使いが大胆流麗だとか、そういう表面的な部分ではなくて「画鬼の目には何が見えているのか」という面に踏み込んでほしかったな、というのがちょっとあります。
杉江 奇矯な着想が好事家に受けた、という部分だけが印象に残るようだと、暁斎自体の魅力はわからないですね。それって、音が聞こえてこない音楽小説と同じで、絵画小説としては致命的な欠陥のような気がします。
マライ 「娘もがんばりました」だけで終わってますからね。
杉江 「北斎だけじゃなくて暁斎にも娘がいました、終わり」でこの小説の趣旨は説明できてしまう。前回マライさんがイチオシだった『稚児桜』のほうが私も好きですね。あれは少なくとも、謡曲に書かれた原曲に対する関心を惹き出しましたから。
マライ そう。異界との地つづき感がおもしろくてよかったですし。
杉江 日本の古典芸能及び民俗学愛好家としては同感です。
『高瀬庄左衛門御留書』凡人が凡人であるゆえの美しさ
『高瀬庄左衛門御留書』あらすじ
郡方で50石。神山藩士・高瀬庄左衛門は自らになんの幻想も抱くことのない、絵を描くことだけが楽しみの男だった。嫡男の啓一郎が亡くなり、庄左衛門は老骨に鞭打って勤めをつづけなければならなくなる。郷村廻りをつづけて見聞した出来事がやがて藩を揺るがす大事に。
マライ 地方の初老(といっていいのかな)お役人侍の地味な生活に起きた、ちょっとした波乱をめぐる物語ですね。この主人公って、『子連れ狼』だと柳生の陰謀の絡みか何かで真っ先にやられちゃいがちなタイプのキャラですよね。それを活用するのが妙味で、この領域に対する関心が薄めの私も、それなりにおもしろく読み通せました。
杉江 これ、まわりの人が絶賛していて、書評もけっこう出たんです。そういう意味では期待されている書き手でもあります。私はまあ、おもしろくは読みました、というくらいの印象で。
マライ 杉江さんは知識あり過ぎゆえ、仕方ありませぬ。作品としての主たる主張は「家族とは何か」「血族こそ最高のきずなといえるのか」というもので、さりげなくイマドキ的な要素を突きつけているのかもしれない。そこがウケた可能性もある。
杉江 凡人が大きな動乱に巻き込まれてしまい「正直者は正直に生きるしかできんのじゃ」みたいな実直さが描かれる小説ではたとえば葉室麟の直木賞受賞作『蜩ノ記』がありますよね。遡れば山本周五郎や藤沢周平作品もあります。そういう意味では時代小説ファンが最も好むところを突いているとは思います。
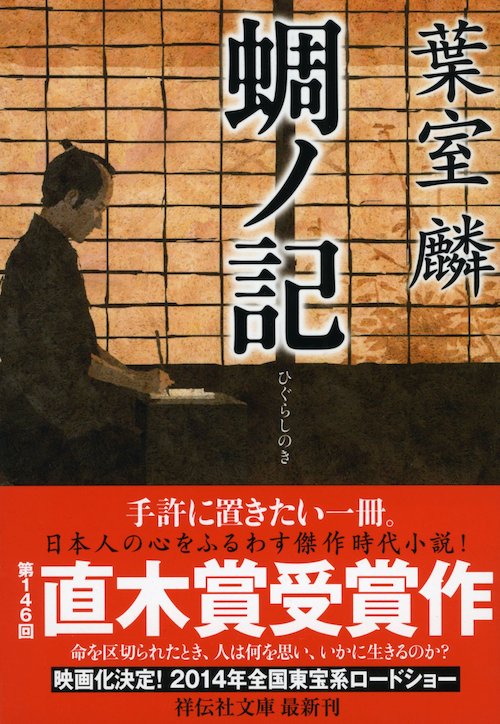
マライ 時代小説業界の読者って、世代交代とかあるんでしょうか。
杉江 そうでもなくて、みんな少しずつ加齢している気がします。
マライ うーん、そうですか。やっぱりちゃんと古典から読んでるのかなとか、気になります。
杉江 みんながみんな読んでいるわけではないと思いますね。でも昭和から平成初期にかけて主だった古典はほぼドラマ・映画化されているので、それで二次体験ができているんです。今はその映像化作品による二次体験が少なくなっているので、過去作のエッセンスを宿した作品はもっと出てきても大丈夫なんじゃないかと思います。『高瀬庄左衛門御留書』は「山本周五郎と藤沢周平といった先達に連なるのではないか」という声もありますが、そういう路線の需要はずっとあるからいいんじゃないでしょうか。
マライ さっきの話題で言えば、業界常識が欠落した読者層が台頭してきている状況を視野に入れても、戦略としては正解ということですね。
杉江 本当は葉室麟さんがそういう存在になるはずだったと思うんですが、早世しちゃったんですよ。ある程度お年を召してからのデビューということもあったんですが、非常に残念でした。砂原さんはまだ50代だし、時代小説主流の書き手として版元は期待しているでしょうね。正直、今回の作品が飛び抜けていいとは思わないんですが、砂原さんが掘っているのは間違いなくエンタメ時代小説の大鉱脈ですよ。このままつづけてもらいたいです。
マライ しかし、今回は中米の暗黒神がいますから、あれに勝つのは厳しいような。
杉江 いや、わからないですよ。直木賞には鬼が棲みますから。よくわからんマヤ文明の神よりもこっちの実直な侍のほうがいいぞ、とがんばる選考委員は出てくると思います。
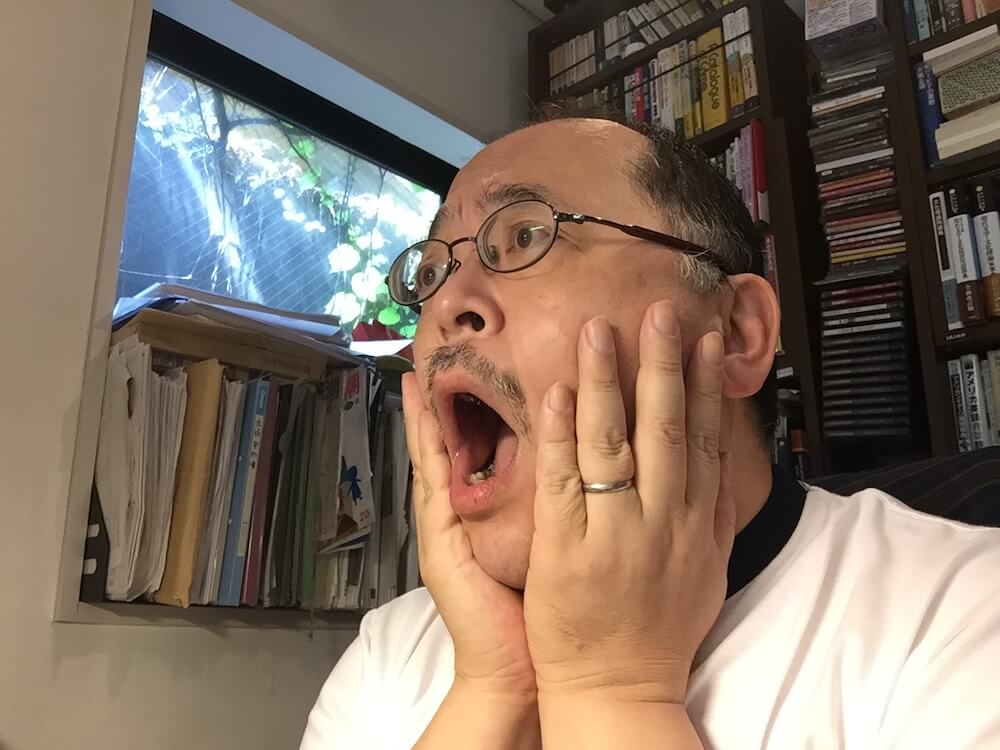
マライ 確かに。普通の情景をあえて求めるニーズはある気がします。
杉江 凡人が凡人であるゆえの美しさ、という小説ではありますしね。あと、読み終わってから気がついたんですが、舞台になっている架空の「『神山藩シリーズ』第1弾」と帯に書かれているのはちょっと驚きました。作者にそういう構想があるのか、それとも出版社が先走っているのか。いずれにせよ、期待されているということなんでしょうね。だから時代小説の新たなスタンダードを求める出版界の集合無意識が暗黒神に勝つ可能性はありますよ。『スモールワールズ』と『高瀬庄左衛門御留書』同時受賞、アリでしょう。
マライ 時代は動くか否か!
直木賞選考の器そのものが最大の注目点
杉江 マライさんの問題提起で、そういう観点からしか今回の直木賞は見られなくなってしまった(笑)。ということで直木賞も、マライさんから全体の所感をお願いします。
マライ 最近、知的エンタメよりも現実のかっ飛び具合が激しいので大変だ、言霊力を備えたいまどき仕様の国際ルポルタージュにエンタメは勝てるのか? 的なことを考えててQJWebの記事にもしたんですけど、その懸念は、少なくとも今回は『テスカトリポカ』によって払拭されたとみてよいでしょう。まぎれもない現代性に立脚した見事な作品です。
マライ しかし、いざフタを開けてみれば直木賞としての今回最大の焦点は、先ほど沸いたように、ネット民・スマホ民的な感性に深く寄り添う『スモールワールズ』の価値がどう評価されるか、であるように思います。今まで巧みにかわしてきた「非文壇的」な何かの精髄が、賞選考のレギュレーション内についに食い込んできたというか。であれば受賞するにせよ外すにせよ、どんな基準と判断でそうなったのかが重要となる。つまり直木賞選考の器そのものが最大の注目点となるわけで、それは賞の今後の存在意義や、文芸界の勢力図的なものにも影響してゆくと思うのです。端的に言えば「本屋大賞的な文化ベクトルと本格的にどう付き合うか」ということになるわけですが、今まで地味に牽制し合うだけでなかなか明確な動きが無かったこの関係がどう動いていくのか、注目したいと思います。

杉江 まさしくおっしゃるとおりで、今回はマライさんの指摘で新たな視野が拓けた気がします。心配なのは、直木賞は新しい革袋を準備しても旧い酒を入れたがる傾向があるところで、『スモールワールズ』が象徴するような時代性とどこまで向き合えるか。『テスカトリポカ』とジャンル小説ファンとして『おれたちの歌をうたえ』を応援しつつ、見守りたいと思います。
関連記事
-
-
マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】
『DAIENKAI 2025』:PR -
ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】
『DAIENKAI 2025』:PR