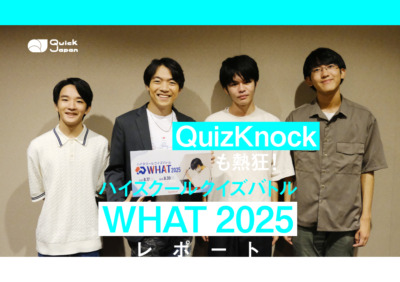人が思い出を回想するとき、不思議とその時代にラジオから流れていたヒット曲やお気に入りの曲と結びつくという経験は、誰にでもあるはず。音楽評論で知られるスージー鈴木が、70年代〜90年代の名曲に重ねて、自らの人生の歩みを赤裸々に描いた私小説=『恋するラジオ』は、そんなラジオにまつわる懐かしい記憶を呼び起こす。ラジオ放送が開始されて100年の今、ラジオと音楽をめぐる物語は、どのように生み出されたのか。スージー鈴木に聞いた。
ラジオで知った名曲は人生と切り離せない
――この小説は人生で出会った「大事な曲」をめぐる物語ですね。
スージー 70年代から90年代のポップ・ミュージックを題材にしています。僕の人生における、いくつかの決定的場面で聴いた、思い入れの深い大事な曲ばかりです。
――アリスやサザンオールスターズ、山下達郎などの邦楽からクイーンやビートルズまで、さまざまなアーティストが登場しますね。時代は違っても、誰もが親しめる音楽ばかりが選ばれているので、読みやすいと思いました。
スージー 人生の中で思い出が深い出来事と、ラジオで聴いた音楽って、密接につながっていると思うんです。それって僕だけじゃなくて、40代以上であれば、誰しもが持っている経験だと考えます。だから、あのころ熱心に聴いた音楽を軸にすれば、たとえ私小説でも、多くの人に開かれたものになるという自信がありました。
――物語に出てくるのは昔の懐かしいヒット曲が多い。けれど今はさまざまなかたちで音楽にアクセスできる時代ですし、作中のヒット曲を体験していない読者が読んでも甘酸っぱい気持ちになりますね。
スージー そうですね。小説に出てくる楽曲を、サブスクや動画サイトで辿りながら読んでくれるとうれしいです。選ばれた作り手からの物語ではなく、どこにでもいる普通の聴き手からの物語なのです。その時代その時代の聴き手の気分になるには、登場する曲を聴いていただくのが一番です。
――甘酸っぱいといえば、主人公の青春時代である80年代は、FMラジオが輝いていた時代でもありますね。
スージー もう本当に、どれだけFMを聴きまくっていたか。呆れるほど始終聴いていました。今や死語の「エアチェック」全盛期でもありまして、カセットテープを入れっぱなしにしてFMでかかった曲で気になったものがあれば、曲の途中からでも、片っ端から録音ボタンを押していました。小説の中にも書きましたが、そうしてでき上がる、色んな曲がつぎはぎで入った謎なカセットテープを、また始終聴きつづける(笑)。

ラジオだけが社会へと開かれた「扉」だった
――古い洋楽を教えてくれたラジオ番組を回想する描写も、素敵ですよね。「高校生だったころのあの部屋の光景がぐっと浮かんできた。夕暮れに聴いたゾンビーズ。真夜中に聴いたレッド・ツェッペリン、そして心がつまずいた高2のころ、何度も何度も聴いたクイーン」。
スージー これは高校生時代の話ですね。当時の自室は兄貴との相部屋で、兄貴がいないときに、クイーンやツェッペリン、ゾンビーズの『ふたりのシーズン』を爆音でかけるのが日課でした。そして母親に怒られる。「なんや、この気持ち悪い音楽は!」って(笑)。
――作中の「ラジオは『東京人』の無表情に閉ざされた社会の、向こう側に突き抜ける窓だった」時代ですね。
スージー 1986年に上京してすぐはテレビを買う金もなくって、大阪から持参したラジカセで、『三宅裕司のヤングパラダイス』(ニッポン放送)を聴くのだけが楽しみでした。木造の湿った部屋で聴く、三宅裕司のトークだけが「東京」に開かれた扉でした。
――その一方で、この小説は悶々としながらも輝かしい青春時代を描いただけの作品ではないですよね。後半は子供の受験に付き添ったり、肉親の死に向き合ったりする、ほろ苦い大人の物語でもあります。
スージー 僕は今年で54歳ですけど、今でもラジオやサブスクで、のべつまくなし音楽を聴いていますので、『恋するラジオ』にも書いたように、息子の受験や両親の死に際しても、私の耳には山下達郎や細野晴臣が流れていました。そういう体験に遭うときでも音楽は切っても切り離せないのです。
――作中の「俺にも、ロックンロール、聴かせてえな、お母さん……」というセリフが印象的です。中学校の先生をしてらっしゃった、バリバリ関西人のお母さんとの思い出と、加藤和彦の音楽が絡むのが、とてもおもしろいと思いました。
スージー 大学生のころに、サディスティック・ミカ・バンド『黒船』を初めて聴いたときは、そりゃもう強烈だったけど、40歳を超えて、加藤和彦の本質がわかってくると、子供のころ、ザ・フォーク・クルセダーズ系の曲を口ずさんでいた母親との思い出と、加藤和彦が交錯し始めたのです。そういう経験も盛り込んでいます。