ミニシアターの社会的価値とは?
――4月13日に配信された「ミニシアター・エイド基金 × DOMMUNE キックオフイベント無観客記者会見」では、全国のミニシアターの方々がリモートで出演されましたね。坪井さんが「3カ月休館がつづくと閉館」と発言したような窮状はあらかじめ共有していたと思うのですが、あの会見の体験は、おふたりにとってどんなものでしたか。
濱口 ヒアリングして状況自体は多少知っていたので、僕は……こんなセンチメンタルな話でいいのかわかりませんが、「みんな、いい顔をしているな」と思いながら見ていた、というのが正直なところです。Zoomのギャラリービューでは、みんなの顔が並んで見えるんですよね。本当に個性豊かな面々が、今こうやって一堂に会していて、普段はそれぞれ違ったところで、違うやり方で映画を上映している。多様性というものは、たとえばこういうことなのだな、と強く思いました。多様である、豊かであるというのは、まさにこの画面のようなことだな、と。
深田 すごく個性がありますよね。もちろん、シネコンの映画館に個性がないとは言いませんが、構造的に会社の大きな方針の中でプログラムが決まっていくのに対して、ミニシアターは館主がプログラムディレクターであり、経営もしている。独立した存在だし、癖の強い人も多い。こうした場が失われていくのは、単純にすごく寂しいと感じます。
――「多様性」や「個性」といったキーワードがすでに出ていますが、ミニシアターの「社会的価値」をどう考えていらっしゃいますか。たとえばおふたりの極私的な体験において、「社会的価値」を感じた経験があれば教えてください。
深田 父親が映画好きで、家にVHSが数百本あり、早い時期からケーブルテレビにも入っていたので、中高生のときはテレビでばかり映画を観ていました。そのときに出会った、今でも自分にとってずっと大切な映画が、ビクトル・エリセの『ミツバチのささやき』なんです。ほかにはアッバス・キアロスタミやエリック・ロメールといった監督たちの作品とか……もちろんハリウッド大作も大好きですが、こうした大事ないわゆるアート映画を、僕が初めて観たのはテレビです。
でも考えてみると、そもそもこれらの作品にきちんと日本語字幕がついて、輸入されているという状況の入口として、絶対にミニシアターがあったはずなんです。ミニシアターという文化が日本に存在しなければ、輸入される機会さえなかっただろうと思いますし、自分の映画体験も、まったく違ったものになっていたことでしょう。
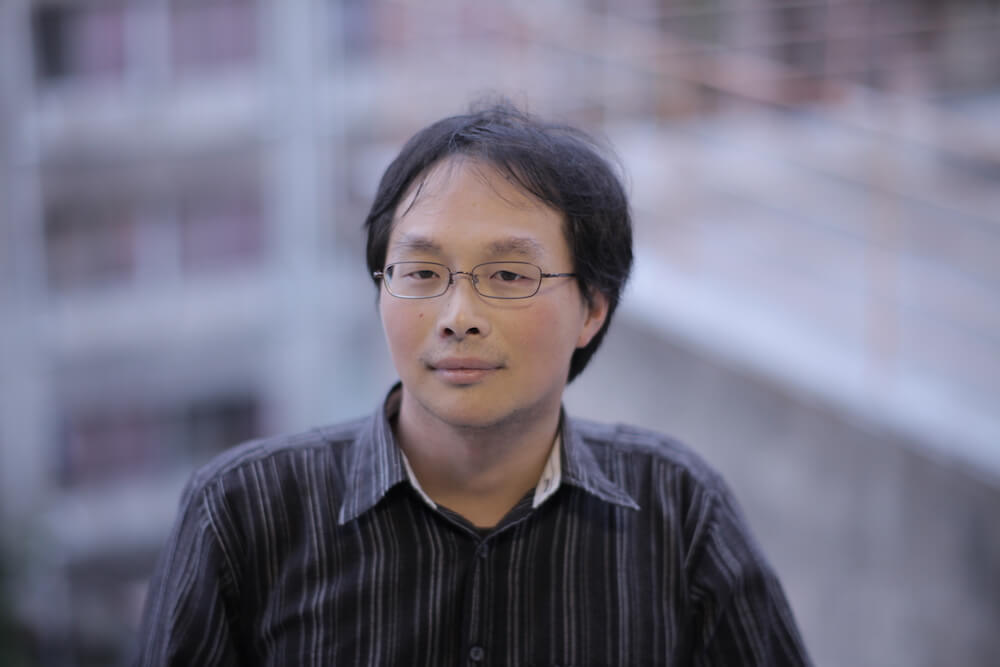
濱口 とてもいいお話ですね。僕も極私的な体験をひとつ挙げるとしたら、渋谷のシネ・アミューズ(2009年閉館)でやっていた「カサヴェテス2000」という、ジョン・カサヴェテスの特集ですね。自分が映画監督になることを真剣に考え始めたきっかけではあります。人生がひとつ変わってしまった。ただ、それがミニシアターの社会的な価値を証明するものかどうか……というのはちょっとわかりません。
逆に、「社会的価値とは、いったいなんでしょうか」と問うてみたい気はします。今回、クラウドファンディングで多くの支援者の方たちの声が集まって感じるのはごくごく単純なことで、「一人ひとりの思いというものがある」ということです。「culture」の語源は「耕す」に通じていますが、映画が一人ひとりの心を耕してきたからこそ、それが今芽を吹いて、社会的なうねりになっている。
個人的には常々、「社会的な」価値は何か、という問いに答え過ぎると、誰の身体感覚に比しても少し大きな言葉になり過ぎてしまうのではないだろうか、という危惧を抱いています。あくまで個人的な体験がまずある。一人ひとりがその体験にほかに代えがたい価値を感じている。本来、それは人に言語化して示すことも、共有することもとても難しいものです。
ただ、今回のアクションはとてもシンプルで、自分が価値あると思うものを支えるために可能な範囲の額を支払えばいい。それができなければ、思いを発信すればいい。その一つひとつが寄り集まって、社会的なアクションと呼べるものになっています。ただ、それがひとつの方向に向かう大きな流れとなれたのは、その体験が「ミニシアター」という場で起こった、という共通の土台があるからです。僕に言えるのは、作品と自分が結んでいる関係性と、それを生み出すミニシアターという場自体がとても大切なものなのだ、という一つひとつの個人的感覚がこれに先立ってあった、ということのみです。
その社会的価値を誰にでもわかるように語ることは、本来はやはりとても難しいことなんだと思います。ただ、あくまで結果としてですが「社会的価値がある」と提起できるぐらいの少なからぬ数値を可視化できた、そのことが今回のアクションのひとつの成果だとは思っています。それぐらい濃密な個人の体験がミニシアターという場を通じて、そこかしこでこれまで起きていたのだ、ということですね。

深田 今後、いわゆる社会的な話も出てくるという前提のもとで、濱口さんの意見に賛成です。たとえば僕はよく民主主義について語るのですが、「映画は民主主義のためにあるんじゃないだろう」とよく言われます。実際、そのとおりです。誰もが自由に作品を作って発表できる環境を準備すること自体が大事で、それが結果的に民主主義を守ることにつながっていく。そこを短絡的に考えてしまうと、民主主義のために映画がある、というようなすごく縮まった言葉になってしまって誤解を生むので、なるべく気をつけてしゃべるようにしています。民主主義のために映画があるのではなく、民主主義が映画を必要としているのです。






































