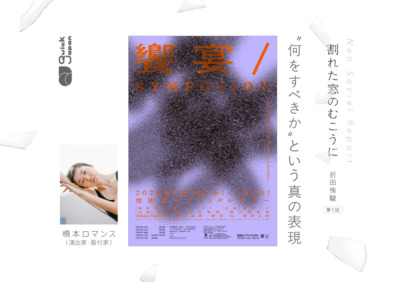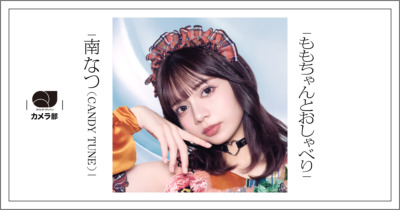ユーゴーの『レ・ミゼラブル』が160年前に示していたこと
『レ・ミゼラブル』の冒頭には、ワールドカップの勝利を祝ってパリ近郊から人々が凱旋門広場にやってくるシーンがある。若者の中には、体にフランス国旗を巻きつけている者もいる。広場を埋め尽くす彼や彼女らの多くは三色旗を手にしている。しかし、それは、個々人を「国民」としてひとつに束ねてしまう統合する国家に忠誠を表明するためではない。国家別に戦うといっても戦争ではなく、自分の意志で参加したゲームのために「国家」を利用しているにすぎない。国家への付き合いを強制されるとき、彼や彼女らは、歓喜の徒から「暴徒」に変貌するだろう。

(c)SRAB FILMS LYLY FILMS RECTANGLE PRODUCTIONS
この映画の舞台となるモンフェルメイユは、ヴィクトル・ユーゴーが『レ・ミゼラブル』に描いた時代とは異なり、マルチレイシャルな都市になっている。白人もいるが、アフリカ系が多数派を占める場所にサーカスのロマ(ジプシー)、ヤクザ、イスラム……が危なっかしい対立を保ちながらやっと存続している。が、この危なさは同時に可能性でもある。ステファンが「初仕事」で行かされるケバブショップ(アルマミー・カヌーテが演じるサラーの店)のような場が多数生まれ、しかも共存できるなら、ここには組織も国家も不要な世界が生まれるかもしれない。
その意味で、映画の終わりに引用されるユーゴー『レ・ミゼラブル』の言葉は意味深い。
「友よ、よく覚えておけ、悪い草も悪い人間もない、育てる者が悪いだけだ」
しばしば引用され、今ではおごそかな響きを帯びてしまったが、小説『レ・ミゼラブル』で、マドレーヌと名を変えてこの街で暮らすジャン・ヴァルジャンが、蕁麻(いらくさ)を収穫している農夫に向かって、ぽろりと彼が農業にも従事していた人間であることを漏らすシーンである。が、この言葉は、ユーゴーによる「序文」に呼応していることはたしかだ。
法律と風習とによって、ある社会的処罰が存在し、それが人為的に文明社会のさなかに地獄をつくり、さらに世間的不幸によって、神聖な人間の運命を紛糾させているかぎり――下層階級なるがゆえの男の失格、飢えによる女の堕落、陽の目をみないことによる子供の萎縮、それら三つの問題が解決されないかぎり――つまりある方面において、社会的窒息が生じる可能性のあるかぎり――言葉をかえていえば、また広い見方をすれば、地上に無知と悲惨とがあるかぎり、本書のような書物も、おそらく無益ではないだろう。
ヴィクトル・ユーゴー『レ・ミゼラブル』(斉藤正直訳、平凡社)
ラジ・リは、いわば、20年間「黄色いベスト」運動のさなかにあると言ったが、この運動は、ユーゴーが1862年1月1日にこの序文を書いたときにすでに起こっていたのである。

(c)SRAB FILMS LYLY FILMS RECTANGLE PRODUCTIONS
しかし、160年前と、また20年前とも異なるのは、国家自体がトランスローカルな(つまり微細なローカル単位の同時共存)ネットワークの網の中であえぎ、個々人が国家や既存の組織に依存しないでも人と人とがつながれる条件が広がっていることである。その意味でこの映画で最も未来を感じさせるのは、ラジ・リ監督の息子アル=ハッサン・リが演じるバズという「ドローン少年」である。こういう面にもちゃんと目配りしているラジ・リのこの映画は、再見するたびに発見があるだろう。
映画『レ・ミゼラブル』
2020年2月28日(金)新宿武蔵野館、Bunkamuraル・シネマ、ヒューマントラストシネマ有楽町ほか全国ロードショー
原題:Les Misérables
監督・脚本:ラジ・リ
出演:ダミアン・ボナール、アレクシス・マネンティ、ジェブリル・ゾンガ、ジャンヌ・バリバール
配給:東北新社 STAR CHANNEL MOVIES
※Bunkamuraル・シネマは2月28日(金)〜3月10日(火)の間、休館予定です。開館状況は各映画館のホームページでお確かめください。