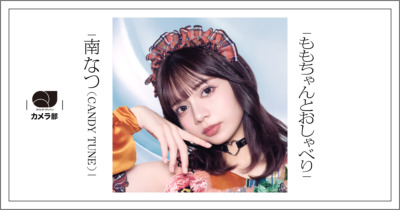板谷由夏が主演を務める映画『夜明けまでバス停で』が10月8日に公開された。本作は、2020年11月16日に東京・幡ヶ谷のバス停で起こった凄惨な事件をモチーフにしている。
ライターの折田侑駿はフリーランスで働く当事者として、コロナ禍がもたらした“悲劇”を他人事とは思えず、この映画を通して「真の『共助』と『連帯』」について考えさせられたという──。
2年前に東京で起きた事件をモチーフとした映画
2020年11月16日──この日、渋谷区・幡ヶ谷のバス停で起こった事件に酷くショックを受けた。ほんの2年前のこととあって、当時の報道の様子をよく覚えている方も多いだろう。64歳の路上生活者の女性が見ず知らずの男に殺害された、あの事件である。
筆者が受けた「ショック」というのは、凄惨な事件の内容に対してだけではない。なによりこの悲劇に襲われた女性のことが、とても他人事のようには思えなかったからだ。メディアを通して多くの人々に伝播した「ショック」は、筆者が感じたものに近いものだったのではないかと思う。日本がコロナ禍に見舞われてからまだ1年と経っていなかったあの当時、いつ、誰が、今ある生活を失ってしまうかわからなかった。それは同時に、いつ、誰が、彼女を襲ったような悲劇に直面してもおかしくないことを示していた。そしてそのような状況は、いまだつづいている。
高橋伴明監督による『夜明けまでバス停で』は、この事件をモチーフとした作品だ。
実際の事件はあくまでもモチーフであり、本作はそれを再現しているわけではない。しかし、事件の被害者と同じように“社会的孤立”を余儀なくされてしまうひとりの女性を主人公とし、映画は彼女を追いつづけ、その内面にも肉薄する。
事件が起きてから、まだたったの2年だ。モチーフであって再現ではないとはいえ、「こんなに早くにやるべきだったのか?」という疑問はどうしても生じてしまう。被害者遺族や関係者が心の傷を癒やす時間としてはあまりにも短過ぎ、場合によっては映画が二次加害になってしまうことだって考えられる。
しかしやはり、少しでも早くやるべきだったのだろうと、本作を観た今思う。なぜならそれは先に記しているように、いつ、誰が、彼女を襲った悲劇に直面してもおかしくはない状況にあるから──思い切って言ってしまえば、多くの人がこの事件の当事者だからである。

主人公の姿と重なる、フリーランスの現実
この物語の主人公・三知子(板谷由夏)は、住み込みのパートとして居酒屋で働きながら、昼間はアクセサリー作家として活動する日常を送っていた。別れた夫の借金を肩代わりしていることもあり生活は楽ではないが、グチを言い合える友人もいて、日々はそれなりに充実している。ところがある日、不意に訪れたコロナ禍。彼女は仕事と住む場所を一度に失ってしまうことになる。
新しい仕事は見つからず、緊急事態宣言の発令によって夜をしのぐ場所も見つからない。やむなく三知子は路上で生活を送るようになり、人影のない静かなバス停で夜を明かすようになり……。
2020年当時、この三知子のような人々が連日のように報道番組で取り上げられた。仕事を失った人、住む場所を失った人、三知子に近い状況に追いやられた人は、けっして少なくなかった。報道を目にするたびに、息が詰まったものだ。恥ずかしながら、意識的に目を向けないようにしていたところもあると思う。
筆者は文章を書く仕事をしているが、フリーランスのため、コロナ禍のように何かがあったときに補償がないのは三知子と同じだ。実際、仕事を失う恐怖も、住む場所を失う恐怖も嫌というほど味わった。筆者のまわりにはフリーランスで働く者が多いが、夜になっても眠れない者、新型コロナウイルス感染症そのものとは無関係な体調不良に悩まされる者など、あの当時は誰もが心や身体に支障をきたしていた。
現在もフリーランスで働く人々の多くが、あのつらさを理解することができると思う。似た経験を持つ者同士だけが解り合える苦しみというものがあるだろう。いや、誰ももう思い出したくもないかもしれない。筆者だってあのころにはもう二度と戻りたくはない。けれども一度経験してしまった以上、いつまたあのころのような状況に、あるいはもっと最悪の状況に陥ってもおかしくないことを理解している。
だがそれでも、ここまでなんとかやってこれた。これは運よく仕事にありつけたからだというわけではない。どうにかサバイブするために情報共有し合える人々の存在が、筆者と社会との接続点になっていたからだと思う。
関連記事
-
-
4年目の今、重荷だった「王子様」を堂々と名乗れる。Last Princeが語る、プリンスを背負う勇気と楽しさ
Last Prince:PR