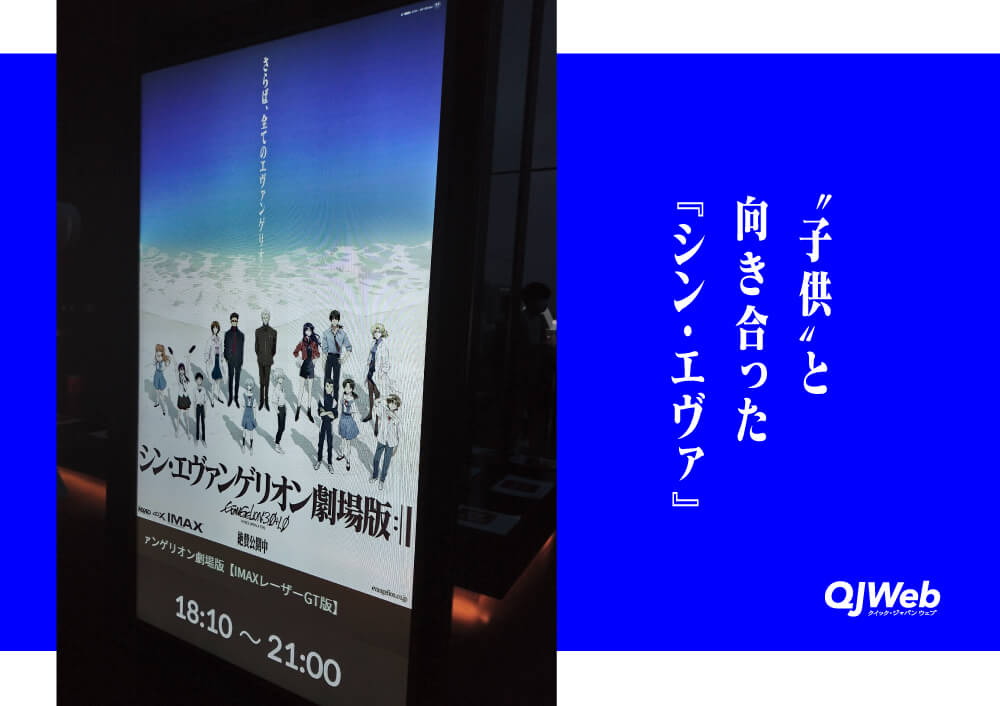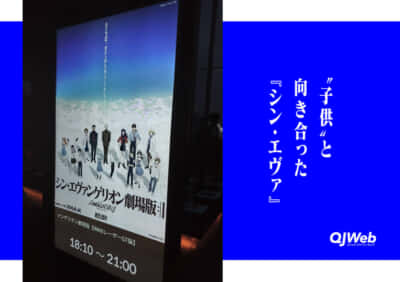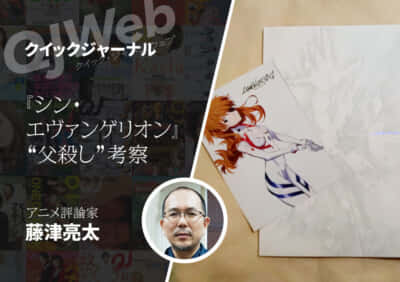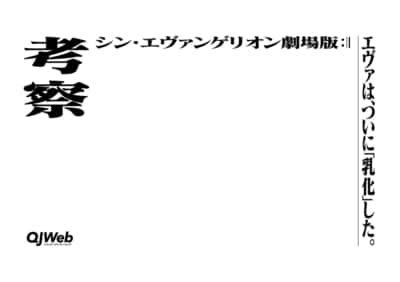1995年に誕生したアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』。そのシリーズを完結させた『シン・エヴァンゲリオン劇場版』が大ヒットを記録し、4月11日には庵野秀明監督の舞台挨拶が発表されるなど、引きつづき話題を集めている。
本稿では、ユースカルチャーについてさまざまな媒体で執筆しているライターのヒラギノ游ゴ氏が、“子供”の表象という観点からエヴァシリーズを考察した。
※この記事は映画『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』と『シン・エヴァンゲリオン劇場版』のネタバレを含んでいますのでご注意ください。
2021年に観る『:Q』の違和感
『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』は衝撃だった。
予告していた内容を「あーそんなこと言ってた時期もありましたね」程度にすっ飛ばして威風堂々丸っきり別の展開を繰り広げる胆力、そんな掟破りなやり方を許させてしまう圧倒的な物語の密度、有無を言わさず惹き込む画面の力。
そして観客にネタバラシを控えさせることで作品の価値を高めるPR戦略。一見してこのソーシャルネットワークの時代に適さないやり方に思えたけれど、結果として箝口令は忠実に遵守され、ファンダムの忠誠心、作品が築き上げてきた信用の高さが証明されることになった。
ただ、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』公開に備え2021年に改めて『:Q』を観直したとき、強烈な違和感を覚えた。
年齢を重ねるごとに作品から感じ取ることが変わっていくというのはエヴァに限らないことだけれど、社会が成熟したことによって『:Q』公開時にはさほど取り沙汰されなかったエグみがより顕著に感じられるようになった。「子供」の描写だ。
「子供」を描く前提
エヴァは思春期の心のありようを描いてきた作品だ。アイデンティティの希求、愛着形成の不全、大人への不信や見捨てられ不安など、思春期の子供の心理に起こるさまざまな事件を、世界の様相と紐づけてきた。……という話はさんざん語られてきていて、これからも語られていくだろう。だからこの記事で掘り下げることはしない。
この記事の本題はその一歩手前の話、子供を描くにあたっての「前提」の話だ。
端的に言えば、『:Q』ではシンジが、子供が子供として扱われていない。思春期の繊細な機微も葛藤も成長も、描くのであればまず子供が正しく子供扱いされているという前提がクリアされた上でだ。でないと大本が破綻した状態での作劇になる。2021年に観る『:Q』はその点で大きな凝りを感じざるを得なかった。そして、2021年に公開される続編の『シン・エヴァ』ではその点をクリアする描写がなされているのか?
『:Q』に限らず本シリーズでは、エヴァンゲリオンのパイロットとして選ばれた14歳の少年少女たちに世界の命運が託されている。子供に大人と同等以上の役割・働き・成果を期待しているわけで、大人と子供の健全な関係性ではない。ところが大人たちはどうにも”申し訳なさそうにしていない”。そして、子供たちのほうも与えられた役割にアイデンティティが依拠していく。そのくせ大人と子供の非対称性を補完する要素があるわけでもなく、アンフェアな関係性を土台にしたコミュニケーションがつづいていく。
もちろん、こういったアンフェアな構図が取られる物語はエヴァに限ったものではない。というか少年漫画誌に掲載されている作品の多くがそうだろう。うずまきナルトが市区町村(里?)の児童福祉課からケアを受けているような描写はついぞ見受けられなかったし、エルリック兄弟も公助の対象とされていたような描写はなく、彼らの養育は地域社会の共助に丸投げされていた。
ただ、『:Q』はこういった“子供をちゃんと子供扱いしない”描写が格段にひどかった。
オズワルドが2020年の『M-1グランプリ』で「声を張らないほうがよかった」「もっと声を張ったほうがよかった」と真逆のジャッジでキャリアを左右されたように、シンジは自身の生殺与奪権を握る相手たちから「エヴァに乗れ」「二度と乗るな」と矛盾する指示で撹乱させられ、意思決定能力を奪われた。そして、置かれている状況をろくに説明されず、情報面でアンフェアな立場を強いられ、にもかかわらず責任だけは徹底的に追求され、社会的制裁を受ける。
「とにかくシンジがひどい扱いを受ける」ということ自体は公開当時からまじめにもネタ的にも触れられていたけれど、このひどさの根幹は“子供をちゃんと子供扱いしない”姿勢によるものといえる。
10代について言い慣わされてきた“子供でも大人でもない”といった表現はシンプルに誤謬だ。子供は子供だ。こういった詩情に見せかけた無反省さが、子供というものと向き合う上でのミスリードを脈々と生み育ててきた。
社会の成熟に伴ってこういった点に抵抗を覚えるようになってきた人は少なくないだろう。本邦のエンタメ市場においても徐々にそういった点に対するコンシャスな姿勢が垣間見られるようになってきている。
少なくとも、うずまきナルトが去ったあとの『週刊少年ジャンプ』を牽引している緑谷出久を取り巻く環境は、木の葉の里より少しばかり進歩的だ。彼の能力「ワン・フォー・オール」は前任者から脈々と継承されていく性質のもので、エヴァンゲリオン同様に世界の命運を左右し得る強大な力だ。ただエヴァの大人たちと違って、歴代のワン・フォー・オール継承者たちは彼に力と責務を背負わせることについて“申し訳なさそう”に言葉を選ぶ。明確に自分たちの任命責任を自覚した物言いだ。
海外エンタメでは、“子供をちゃんと子供扱いする”ことについてのエクスキューズはずっと前から行われてきている。代表的な例としては『バットマン』におけるロビンの描かれ方がある。
バットマンからクライムファイターとして(暴力行使の)手ほどきを受けた歴代のロビンたちの中には、そのあとバットマンに反発し袂を分かった者や、ヴィランに身をやつした者などがいる。こうした描写はバットマン=ブルース・ウェインの保護者としてのあり方が少なくとも手放しで称賛されるようなものではないと示唆していると取れる。そして、ライターたちが子供に大人同様の役割を担わせること、子供になんらかの力を与える責任といったイシューに自覚的な姿勢が窺い知れる。