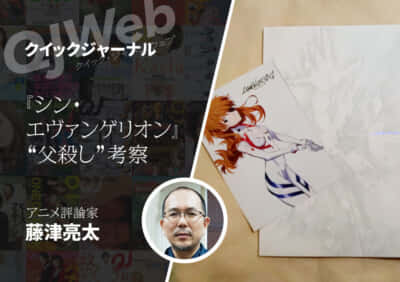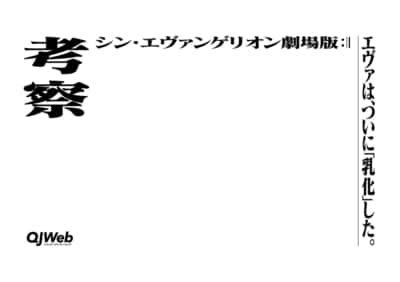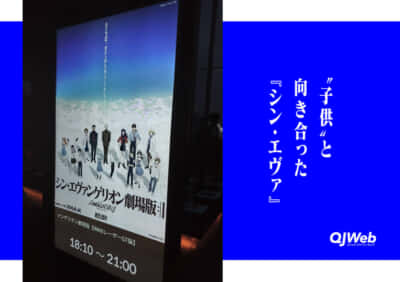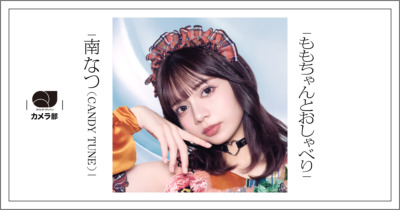『シン・エヴァ』、「わかった」
『シン・エヴァ』を観て何より衝撃だったのが、「わかった」ことだ。何を描こうとしているのか、めちゃくちゃわかりやすかった。
これまでのエヴァは、「ATフィールド」「L.C.L.」「セントラルドグマ」といった用語の羅列や、理解されることを放棄したような抽象的な作劇で知られている。その「わからなさ」の塩梅の絶妙さ、「効果的なわからなさ」とでも呼べるものこそがこの作品を社会現象と呼ばれるまでに押し上げた。
それは新劇でも大枠変わらないだろう、“わからないなりにどう読み解くことができる”だろうという姿勢で劇場に足を運んだ人が大半ではないだろうか。
ところが、少なくとも大筋の部分は驚くほど簡潔で、“わかった”。
「サービスサービス」と言うわりにさんざん顧客の理解を度外視した作風だったものが、ここへきてものすごくサービス精神旺盛なプロットで決着した。こういう伏線回収もあるのか。
そして、この記事の本題である“子供をちゃんと子供扱いする”という点に向き合う姿勢がはっきりと見て取れた。第3村での暮らしがそうだ。
14歳のまま心身の成長が止まっているシンジは、年齢を重ねたかつての同級生たちとの生活の中でようやく“子供扱い”される。
さまざまな経験を積み大人として成熟したトウジやケンスケは、シンジに対して一歩引いて接する。まわりを拒絶し、厚意を受け入れないシンジの姿勢を「今はそれが必要なんだろう」と受け入れた。子供が子供じみたことをするのは当然だから。子供が子供らしくあることを正しい・順当なことだと歓迎し、保護者として最低限の責任を守り、その上で気の済むまでただ意思を尊重してやる。こうした接し方、保護者のあり方は、今まで何十年もの間彼が享受できなかった当然の権利だ。それを受けシンジはようやく順当な発達段階を踏み、主体的に意思決定できる人間に成長を遂げる。そしてこの描写をもって、長らくこの物語に自身の中の子供を重ね、囚われてきた大人たちもまた巣立ちの時を迎えた。少なくとも物語側はそう意図していて、観客たちに“巣立ちのときが来た”と通告しているように思えた。
また『シン・エヴァ』では、不可能だと思われていたゲンドウとの対話が実現した。不可能だと思われていたというか、この作品はシンジとゲンドウの対話不可能性に立脚していて、対話が破綻した上でいかに決着させるかの物語だと思っていた。
こうした所感は、実際の機能不全家庭の子供たちが自身の保護者に対して感じているのと相似のものだろう。
この作品はゲンドウと話し合えれば終わる物語だ。そして実際に話し合えてしまったので終わった。終わった! マジかよ!
しかも、ゲンドウは虚栄心や恥の意識で覆われて正視してこなかった自身の子供時代を顧みるところまで急成長を遂げる。あまつさえそれをシンジに語り聞かせることまでした。あのゲンドウが徹底的に自己開示した。
この描写は、エヴァに囚われてきた大人たちへのダメ押しの一発になっただろう。
あのゲンドウでさえ、あの子供じみた碇ゲンドウでさえちゃんと大人になったのだから。
『シン・エヴァ』の先
ただ、腑に落ちない点はある。
シンジが急激にひと皮剥けた最大のきっかけとして、アヤナミレイ(仮称)の消滅が象徴的に描かれているけれど、彼女がそこまでの衝撃を与えるほどシンジの中で大きな存在だったのかどうかは疑問が残った。
また、あの幼稚なゲンドウが急に「暴力ではなく話し合いで解決」なんて大人なことを言い出し、自己開示し始めたのはなぜか?の背景もまたじゅうぶんに描写されていないように思う。
つまり、この作品における最大の問題児ふたりの成長がなぜ起こったのかという理由の説明がやや不充分に感じられるということだ。
ただ、そういった点については本作に影響を受けた後続の作品たちが、より解像度高く表現していくだろう。そうして、脈々とつづく「物語を作る」という人間の営み全体として見たときに、補完がなされていく。
さらに言えば、本作はそういった成長の要因の説明が意図的に端折られているようにも感じられる。そこにフォーカスするよりも、終わらせること自体に重きを置いたと取るならば、一定の成功は果たしているといえるだろう。
そして、最大限好意的に見れば、「理由なんてなんでもいいからお前らもさっさと終わらせろよ」というエールに近い何かも感じ取れる、と言うと肩入れし過ぎだろうか。
なんにせよ、作品側から一方的に通告するのではなく、「エヴァを終わらせる」という儀式を観客がある程度主体的に行うことにこそ本質があるように思う。
片手ずつ前に出して卒業証書を受け取って一礼、という儀式をしなくても卒業はできる。ただ、観客たちがこの終わりに参加できる仕組みを作り、一緒に儀式の過程を経て自ら卒業していくことこそ最良の終わりだと、庵野秀明は考えたのではないだろうか。
ラストシーンで声変わりを迎えた碇シンジ同様、長年この物語に囚われてきた視聴者たちもまた、大人として自分の足で歩いていく時を迎えた。
ただ、大人でいることは楽しい。神話になれなかったかつての少年たちの日々の暮らしの実話は、存外悪くないスペクタクルなはずだ。