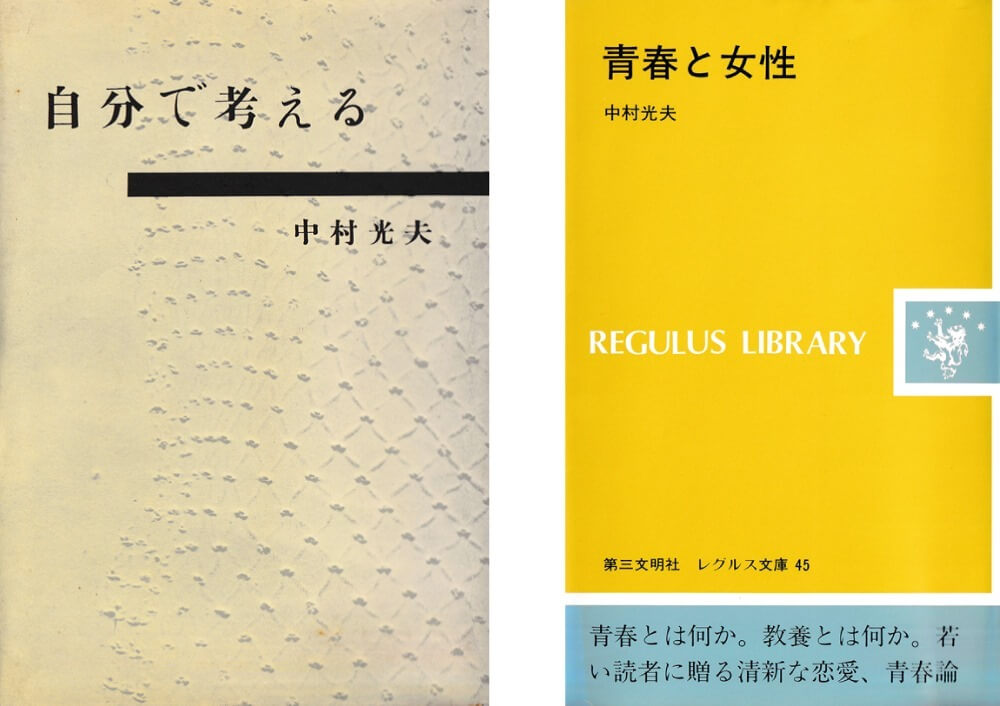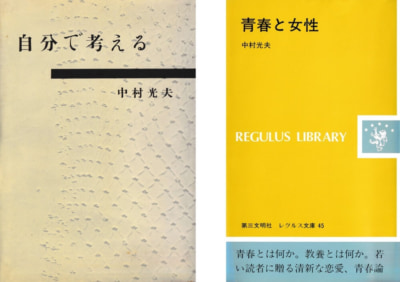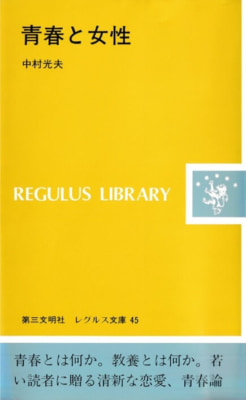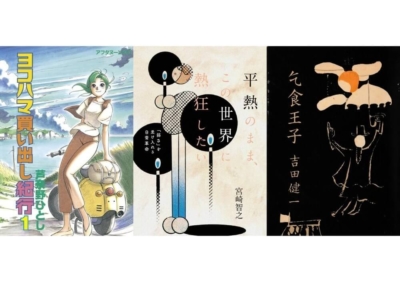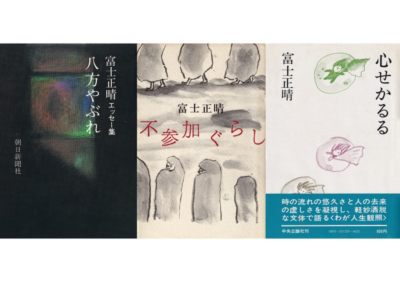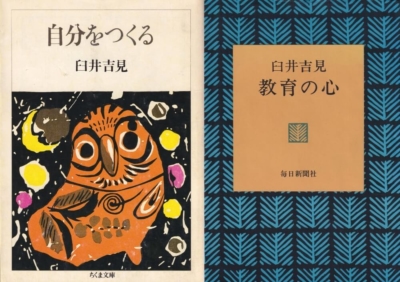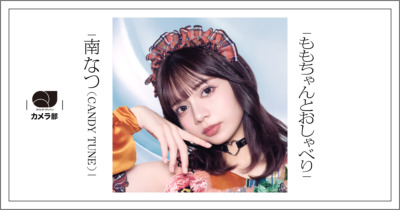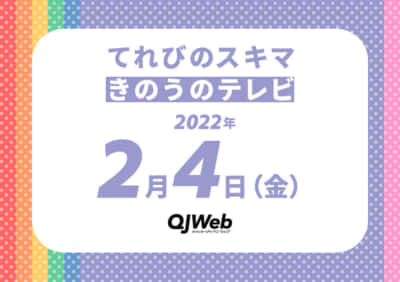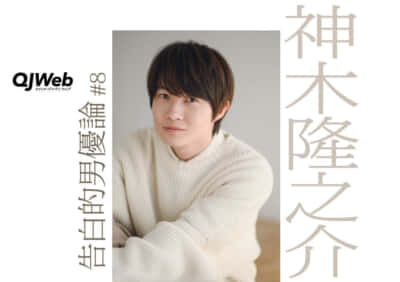本はたくさん読めばいいというものではない。ダイエットや片づけに関する本を千冊読もうが、そこに書かれているのは「増えた分だけ減らしなさい」である。世の中には一冊読んで千を知る人もいれば、千冊読んで一を知る人もいる。
わかったとおもったところからわからなくなるのが文学の醍醐味
残念ながら、わたしは後者のようだ。昔から同じような本ばかり読んでしまう癖がある。貧乏もしくは自堕落な生活から自分を立て直し、平穏な日常を求める話だ。人生、進歩なし。これでいいのか。
そんな気分に陥っていたとき、中村光夫著『自分で考える』(新潮社/1957年)所収の「私の読書遍歴」を再読した。60年以上前の文章だが、今でも有意義な意見が書かれているとおもったので紹介したい。
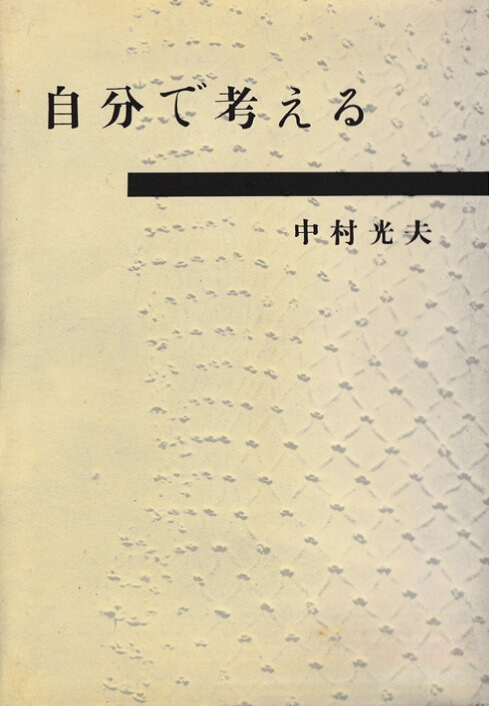
たくさんの知人よりひとりの友人こそ人生において求めるべきであるように、読書においても多読はただ精読の対象を見出すまでの手段にすぎないでしょう。
『自分で考える』「私の読書遍歴」中村光夫/新潮社
長年の乱読生活を経て、そのことを痛感している。多くの本を読むのは自分の好きなもの、特別なものを見つけるためなのだ。バランスよくなんでも知ろうとすると、どうしても散漫になってしまう。
『自分で考える』には「読書の方法」というエッセイも収録されている。これも今の自分のもやもやとした気分に響いた。
小説を読んだ感動は、すべて僕等の内心にふれる感情と同じく、ひどく言いあらわしにくいのが普通です。(中略)だから僕等の感動がどんなに深く、相手のそれがどんなに浅薄であっても、彼がそれを巧みに言い表す方法を知っていれば議論はこちらの負におわります。まずいことは浅薄な感想や型通りの理解ほど雄弁に語るに適しているのです。
『自分で考える』「読書の方法」中村光夫/新潮社
議論に強いことは虚栄心を満たすことはできても、文学を愛することにはつながらない。わたしは文学作品を読み終わったあとも思案がつづく。あれこれ思索している途中で「それはちがう」「まちがっている」と言われるのはあまりいい気分ではない。答えをすぐ出せる人となかなか出せない人がいる。早く出せればいいというものではない。わかったとおもったところからわからなくなるのが、わたしは文学の醍醐味だと考えている。
1911年生まれの中村光夫が「読書遍歴」を書いたのは40代半ばなのだが、彼は40歳になったとき、文芸評論家の仕事に対し、中年期以降「若い作家の愛だの恋だのいう小説を読むのはきっついわー(意訳)」みたいな愚痴もこぼしている。
わたしも40代になったころ、似たような気持になった。
小説を読んだときに生じる感情はそれこそ無数にある。同じ人が同じ作品を読んでも、そのときどきの体調や心境によって感想もちがってくる。年齢によって自分の関心事も変わる。何かひとつの基準を想定し、それに合うか合わないで作品のよしあしを決める人がいるが、文学をより深く楽しむためにはおすすめできない方法だ。
新しい価値観がどれほど優れたものであっても、過去の書物を否定したくない